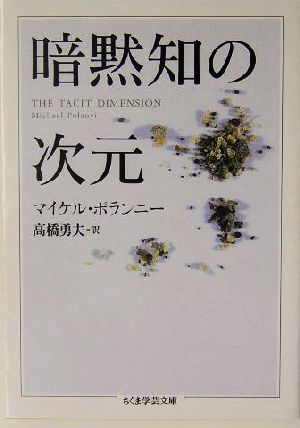暗黙知の次元 の商品レビュー
二種類の、実在のレベルの関係性から成り立つ明示的ではなく暗示的に発見を促すような、知の根源だという暗黙知 精々主観的なものだろうと侮っていたら寧ろ社会的であり、更には… 「私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができる」 問題があれば、それを解いて答えを出すのは当たり前で...
二種類の、実在のレベルの関係性から成り立つ明示的ではなく暗示的に発見を促すような、知の根源だという暗黙知 精々主観的なものだろうと侮っていたら寧ろ社会的であり、更には… 「私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができる」 問題があれば、それを解いて答えを出すのは当たり前で簡単 でもその問題がなかったら解きようが無い その問題を見つける―暗示的に知らせてくれる―のが暗黙知の機能という画期的な観点に今更感動した 決して簡単な本では無いが、本が薄いため、丹念に読んでも、読書体力が無い人でも読めると思う(ボクもそう) 先述のように分厚い本では無いが、ポラン二ーが「明示した」暗黙知についての理論は他の分野・領域においても応用できるもののため読んでおくといい
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
第Ⅰ章で紹介されている無意識の回避行動実験が面白い。 p.048「いまだ発見されざるものを暗に予知する能力が私たちに備わっている」 p.106「通国科学概念が教えるところによれば、科学は観察可能な事実の集積であり、しかもそれは誰でも自力で検証可能なものなのだという。私たちはそれが、たとえば病気の診断の場合のように、熟練した知識の場合には当てはまらないことをすでに見てきた。しかしそれはまた物理が科学の場合にも当てはまらない。そもそも、一般人が、たとえば天文学や化学の記述を検証するための装置を手に」するなど、とうていかなわぬ事なのだ。もしあなたが、どうにかして天文台や化学実験室を利用できたとしても、たぶん観察活動を行う前に、そうした施設の装置に修理不能な損傷を与えてしまうのが落ちだろう。また、万が一あなたがあある科学的記述を検証するための観察に成功し、その科学的記述に反する結果を得たとしても、あなたの方が間違ったのだと考えるのが筋というものだ。」 p.107「一般人が科学的記述を受け入れる行為は、権威に基づいている。そしてそれは、ほとんど同じ程度において、自分の専門外の科学分野の成果を利用する科学者たちにも当てはまる。科学者たちは自らの発見した事実を裏付けるために、同業の科学者たちに大いに依存しなければならないのだ」
Posted by
AIは人間の知を超えるか、という今どきのテーマについて考えていて、この本に答えがあったと思い出し、再読。 20代に読んだ時には、この本の真価が、全く分かっていなかったことに気づかされた。 というより、安冨歩が「経済学の船出」と「合理的な神秘主義」の中で、ポランニーについて言及し...
AIは人間の知を超えるか、という今どきのテーマについて考えていて、この本に答えがあったと思い出し、再読。 20代に読んだ時には、この本の真価が、全く分かっていなかったことに気づかされた。 というより、安冨歩が「経済学の船出」と「合理的な神秘主義」の中で、ポランニーについて言及しているのを読んで、暗黙知理論の射程の大きさとその理論的意味の大きさに目を開かれた。 暗黙知の理論では、私たちが言葉にできる以上のことを知っているということを示すと同時に、知るプロセスそのものを明示化することは原理的にできないということを示す。 知るプロセスそのものがプログラム化されているAIとは、知の構造そのものが根本的に違うのである。 ポランニーは、個々の諸要素を感知し、その感覚に依拠することによって(近位項)ある包括的存在(遠位項)を理解するプロセスを創発と呼び、この創発概念を進化のプロセスそのものに適用するという壮大な試みを行なっている。 そして人間の精神の働きがそれなくしてはあり得ない実在という形而上学的次元と、人間の倫理的責任にまでこの暗黙知の理論を敷衍する。 壮大で、かつ、希望に満ちた洞察の書である。
Posted by
「暗黙知」という言葉はご存知ですか。人は「言葉にできるよりも多くのことを知ることができる」とこの本では表現されていますが、人は必ずしも言葉では説明できないけれども、思考に基づいて様々な行動を表出させています。それを著者は「暗黙知」としています。 この本では、暗黙知には機能的側...
「暗黙知」という言葉はご存知ですか。人は「言葉にできるよりも多くのことを知ることができる」とこの本では表現されていますが、人は必ずしも言葉では説明できないけれども、思考に基づいて様々な行動を表出させています。それを著者は「暗黙知」としています。 この本では、暗黙知には機能的側面、現象的側面、意味論的側面、存在論的な側面の4つの側面があると説明されています。そして、暗黙知が発揮される仕組みや、暗黙知の構造が人間の動作を包括する仕組みなどについても論じられています。 人の思考や行動を捉えようとする研究などでは、暗黙知という視点は欠かせないと思います。人の思考や行動などに興味・関心がある方は、ぜひ一度読んでみてください。 (ラーニング・アドバイザー/教育 FUJI) ▼筑波大学附属図書館の所蔵情報はこちら https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/opac/volume/4093079
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
専門性の高い仕事をどうやってシステム化するかということにおいて暗黙知の形式知化というのは大きなテーマだ。もともとプロフェッショナルサービスの生産財としての情報を提供するシステムについての開発マネジメントを研究テーマとしていたことが背景としてあり、先日紹介してもらったので読んでみたのがマイケルポランニーの暗黙知の次元だった。 読んでみると、いや難解!(汗)150ページくらいだからさらっと読めるだろ、と夏休みの読書の1冊でほかにも3冊くらい読めると思っていたんだけど、実際に夏休みに読めたのは上野千鶴子著「情報生産者になる」とこの本の2冊だけ。 「私たちは言葉にできることより多くのことを知ることができる」といういわゆる暗黙知の事実が議論の起点になっている。1章で暗黙知の基本的な構造について対象を知ることと方法を知ることから現象的、意味的な考察として論じているのだけど、いったん読んでノートに話の構造を書き出してみないともうついていけない・・・。なんでこんな言葉使いで訳されているのだろうと思うくらい無駄に難解な言葉で書かれている印象を受けた。認識論とか認知心理のような考え方の理解としてはとても参考になった。へぇ、と思ったことをいくつかまとめておこうと思う。 「あけすけな明瞭性は複雑な事物の認識を台無しにしかねない」 これは、シンプルに本質に迫ろうとしたらそぎ落としてはいけない部分まで捨てられてしまいかねないという意図だと理解できる。暗黙知を形式知化する過程で必要なところまで落としてはいけないよ、という注意だけど確かに暗黙知として形式知化したときの価値を考えるとなるほどと思える。 「全ての研究は問題からはじめなければならない。見えないものが見えること、見ると信じることを暗に認識している。これが事実なら問題が妥当なものになる」 これは、上野千鶴子著「情報生産者になる」にもあった研究の実行可能性の検討と同じようなことを言っていると思う。確かに暗黙知としてそこに存在はしているけど、認識されていないものや見過ごされているものにスポットライトを当てるということが、研究で明らかにするということなのだと考えたらもっともな話だ。そうか、見えないものが見えると信じることを暗に認識している、というのはものすごい観念論だけど、確かに研究者としての個性はそこにあるんだろうなと思う。 文章自体の構成は難解だけどしっかりしているのに、自分の語彙力のなさからなのかなんか読みづらさ満点だったな、と感じてしまった。国語が得意な人にレクチャしてもらいたい。時間がたったらまた読んでみようと思う。ノートで復習して読んだらもう少しすんなり分かるかな。
Posted by
咀嚼できていないと思うが、人の顔を見て、誰かは分かる、しかし、それを言葉にすることはできない。味もそうだし、感覚もそう。それが暗黙知。今まで暗黙知は悪しきことで、形式知化を目指すものと考えていたが、そうではない、暗黙知であるからこそ、の利点。ここが咀嚼できていない・・
Posted by
んー... 難しい!笑 部分部分の言いたいことはなんとなくわかりました。 何回も読み直して理解する必要がある本だと思います。
Posted by
今まで暗黙知について誤解していたかもしれない 。「その人しか知らないこと」のようなイメージでいたが、 『私たちは言葉にできることよりも多くのことを知ることができる』 という一節の通り、言葉と言葉の間の見えないその人自身も認識できていない「知」が暗黙知ということなのかもしれない。
Posted by
「木の中に仏様がいて自分はそれを取り出すだけなんだ」 我々はすべてを知っているから無知なのであり、次元を超えて進化しなければならない 理解をするという目の前の段階から、生命の定義、人類がどこに向かうのかまでが、この短い一冊のたった一つの理論の中に詰まっていると思うと人の知能のす...
「木の中に仏様がいて自分はそれを取り出すだけなんだ」 我々はすべてを知っているから無知なのであり、次元を超えて進化しなければならない 理解をするという目の前の段階から、生命の定義、人類がどこに向かうのかまでが、この短い一冊のたった一つの理論の中に詰まっていると思うと人の知能のすごさと優美さを感じます
Posted by
正直難しすぎて何言ってるかわかりませんが、頑張って読み切りました。 暗黙知とは、言葉にすることのできない認識のことである。 暗黙知が機能しているとき、私たちは何か別のものにむかって注意を払うために、あるものから注意を向ける。 人の特徴として感覚をもっている。 一つの世代から後続の...
正直難しすぎて何言ってるかわかりませんが、頑張って読み切りました。 暗黙知とは、言葉にすることのできない認識のことである。 暗黙知が機能しているとき、私たちは何か別のものにむかって注意を払うために、あるものから注意を向ける。 人の特徴として感覚をもっている。 一つの世代から後続の世代への知識の伝達は、主として、暗黙知的なものである。このことから、大人の振る舞いのうちに隠された意味を子供は推測する。
Posted by