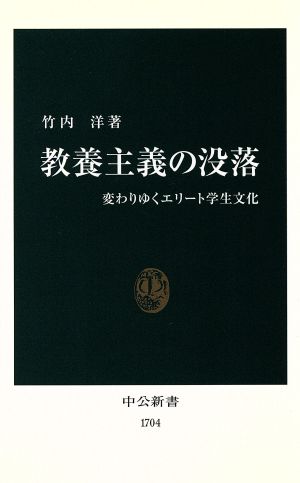教養主義の没落 の商品レビュー
教育学の分野では結構、参考文献にあがるのだが、実際に読んでみると、あれれという感じがしないでもない。 西洋における上流階級を日本では築き得なかった。農村に対する都市階級の非常に中途半端な「主義」がつく教養。 そして、大学の大衆化が進み、それが消えていく。 これは大学に少し長く...
教育学の分野では結構、参考文献にあがるのだが、実際に読んでみると、あれれという感じがしないでもない。 西洋における上流階級を日本では築き得なかった。農村に対する都市階級の非常に中途半端な「主義」がつく教養。 そして、大学の大衆化が進み、それが消えていく。 これは大学に少し長く居れば分かるような気がする。 大切なことはそれを大量の文献を元に整理したことなのかな。 最近思うのだが、こういう本を面白いと感じない自分が、院に進学してよいのかな・・・。
Posted by
教養を見に付けることが文化規範として機能し、マルクス主義との接合を経て、70年以降教養主義が没落していくまでを論じた本。教養?それカネにならないっしょ、っていうのが現代。教養主義がマルクス主義と結びつくあたりがおもしろい。ちょっと長いけど。
Posted by
なかなかきつい…。教養主義が咲き誇っていた大正時代、あるいは旧制一高から現代までの教養主義の変遷が描かれている。ひとつ前の小谷野さんもそうだけど、こういう本を書く人の読書量は半端じゃないんでしょうね。これが学者というものですか。『グロテスクな教養』(ちくま新書)とも内容は似ている...
なかなかきつい…。教養主義が咲き誇っていた大正時代、あるいは旧制一高から現代までの教養主義の変遷が描かれている。ひとつ前の小谷野さんもそうだけど、こういう本を書く人の読書量は半端じゃないんでしょうね。これが学者というものですか。『グロテスクな教養』(ちくま新書)とも内容は似ている。
Posted by
前半は戦前からの左派傾向にあった学生の移り変わりが記述されている。インテリ=左派傾向であったため、このような図式だが、本当にそうだったのだろうかと疑問に思う。現在の60歳代の気概はおおむね右派な訳で。 そもそも教養主義の没落は単に本当に一部のエリートだけが進学可能だった大学...
前半は戦前からの左派傾向にあった学生の移り変わりが記述されている。インテリ=左派傾向であったため、このような図式だが、本当にそうだったのだろうかと疑問に思う。現在の60歳代の気概はおおむね右派な訳で。 そもそも教養主義の没落は単に本当に一部のエリートだけが進学可能だった大学が誰でも入学できるようになったため、価値が希釈したからでしょう。 第4章の「岩波書店という文化装置」は現在の岩波書店から考えると、非常に驚く内容だと思う。 内容そのものは☆4.5くらい。個人的な評価は☆3つ。これはエリート学生文化っていう言葉が微妙だから。
Posted by
大正時代から続いた教養主義がどんなもので,なぜ栄え,なぜ流行らなくなったかがよく解説してあります。ただ,ちょっと冗長というか,既にあった材料をつなぎあわせたような構成で個人的には少し読みにくかった。純粋に論理的にアイディアだけ伝えるなら100ページもあれば十分だったんじゃないか...
大正時代から続いた教養主義がどんなもので,なぜ栄え,なぜ流行らなくなったかがよく解説してあります。ただ,ちょっと冗長というか,既にあった材料をつなぎあわせたような構成で個人的には少し読みにくかった。純粋に論理的にアイディアだけ伝えるなら100ページもあれば十分だったんじゃないか。僕の苦手なタイプの社会学っぽいせいか,やや頭に入りにくかった。(2007年1月)
Posted by