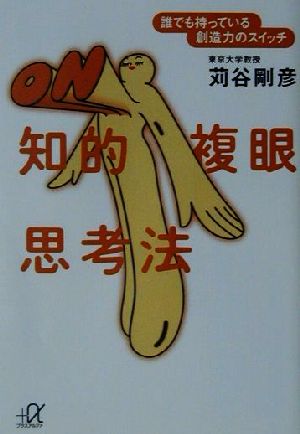知的複眼思考法 の商品レビュー
大学時代に読んだ本。 もともとそんな考え方だったような。。この本を読んでレポートを書いて実践していったからなのか? 今の自分はこの本で形成されているような気がしてならないです。 しかし、自分がどんどん頭でっかちな人間なのではないか?と思ってしまう節がある。 世の中、そんな深く...
大学時代に読んだ本。 もともとそんな考え方だったような。。この本を読んでレポートを書いて実践していったからなのか? 今の自分はこの本で形成されているような気がしてならないです。 しかし、自分がどんどん頭でっかちな人間なのではないか?と思ってしまう節がある。 世の中、そんな深く細かく知っていたり考える人って理屈っぽくて厄介というか、煙たがれる傾向にありません?? どうも角が立っちゃって。。 でも、全面に自分の考えを押し出さず、世の中の空気に準拠しつつ 自分を少しずつ出していく技を身につければ、きっと素敵な力を手に入れられると思います。
Posted by
自分の頭で考えて行動・発言したいと考えているが、では、実際に自分の頭で考えるには具体的にどのような思考過程を踏めばよいか。 このような問題に対して、丁寧に、わかりやすく、どうすればよいかを説明してくれている。具体例も豊富なのも親切。ただ、すでに自分で物事を考える習慣がすでにある...
自分の頭で考えて行動・発言したいと考えているが、では、実際に自分の頭で考えるには具体的にどのような思考過程を踏めばよいか。 このような問題に対して、丁寧に、わかりやすく、どうすればよいかを説明してくれている。具体例も豊富なのも親切。ただ、すでに自分で物事を考える習慣がすでにある人にとっては陳腐なものにみえるかも。 周りにいるステレオタイプの思考しかできていない人に勧めてみては。
Posted by
1996 一時期話題になってかなり売れたようだ。400頁近くある厚さだが、内容が薄いために1時間で読み終わった。簡単にまとめると"critical reading"のススメ、物事の多面性に注目せよ、ということだ。中学生でも無意識レベルで実践してるんじゃなかろう...
1996 一時期話題になってかなり売れたようだ。400頁近くある厚さだが、内容が薄いために1時間で読み終わった。簡単にまとめると"critical reading"のススメ、物事の多面性に注目せよ、ということだ。中学生でも無意識レベルで実践してるんじゃなかろうか、と思うことを懇切丁寧に解説している。ロラン・バルトの『神話作用』を読むほうが100倍刺激的なので読む必要はない。悪い本ではない。おそろしく退屈なだけだ。
Posted by
著者によると、ステレオタイプにとりつかれ、物事を一面にしか見ない思考を単眼思考という。いわゆる常識にとりつかれた思考である。一方、ステレオタイプから抜け出して、それを相対化する視点を持つことを複眼思考と言う。複数の視点を自由に行き来することで、一つの視点にとらわれない相対化の思考...
著者によると、ステレオタイプにとりつかれ、物事を一面にしか見ない思考を単眼思考という。いわゆる常識にとりつかれた思考である。一方、ステレオタイプから抜け出して、それを相対化する視点を持つことを複眼思考と言う。複数の視点を自由に行き来することで、一つの視点にとらわれない相対化の思考法である。 この思考法と同様、人間の目も複眼である。なぜ、人間の目が二つあるのかというと、右目と左目が違う映像を脳に送り、それが脳で合成されることにより、物が立体的に見えるからである。つまり、思考も同じである。複数の目で、ある現象を観察することによって、その現象が立体的に見えてくる。そうすることにより、平面と違う新たな発見がもたらされる。 本書では様々な例題とともに、複眼思考が学べるようになっている。本書を読めば、情報を正確に読みとる力、ものごとの筋道を追う力、受け取った情報をもとに自分の論理を組み立てる力などが身につくだろう。
Posted by
「自分の視点」に凝り固まらず、色々な角度から物事を見ることを教えてくれた一冊です。 大学に入ってすぐに出会うことが出来てよかったと思っています。
Posted by
[関連リンク] 「頭の良くなる本を教えて下さい!」「ごめんなさい」 読書猿Classic: between / beyond readers: http://readingmonkey.blog45.fc2.com/blog-entry-294.html
Posted by
「なぜ」と考える必要性。常識の破り方が書いてある。要因、関係性を見つけるスキルが学べる。禁止語のすすめは実践していきたい。
Posted by
【自分の視点を持つとは、自分がどのような立場から問題をとらえているのか、その立場を自覚することでもあるのです。】 だいたい認識していた。 ただし、このことをちゃんと言葉として表現できることはすばらしい。
Posted by
何度も読むことが勧められる。 目次 第一章 創造的読書で思考力を鍛える 1著者の立場、読者の立場 2知識の受容から知識の創造へ -批判的読書とは ・疑問を持つこと ・著者のねらいはなにか ・論理性、根拠のチェック ・著者の前提を把握し、疑う 第...
何度も読むことが勧められる。 目次 第一章 創造的読書で思考力を鍛える 1著者の立場、読者の立場 2知識の受容から知識の創造へ -批判的読書とは ・疑問を持つこと ・著者のねらいはなにか ・論理性、根拠のチェック ・著者の前提を把握し、疑う 第二章 考えるための作文技法 1論理的に文章を書く 2批判的に書く -一人ディベートのすすめ ある問題に対して仮想の立場を複数設定し、それぞれから批判、反論 その際、複数の前提を把握する 最後は文章にして客観的に論理性チェック 第三章 問いの立てかたと展開のしかた 1問いを立てる 2<なぜ>という問いからの展開 3概念レベルで考える 第四章 複眼思考を身につける 1関係論的なものの見かた -これから行おうとしていることの ・副産物 ・抜け道 ・全体の影響 ・計画の表明自体が計画にどう跳ね返ってくるか 2パラドクスの発見 3<問題を問うこと>を問う ・ある問題を取り出すことで隠れる問題はないか ・ある問題を立てることで誰が得/損をするか ・問題が解けたらどうなるか <レビュー> 単純的な思考に陥ってしまわないため、 物事を多面的な視点から見るように訓練する方法論。 インプット、アウトプット、考え方からかえてゆく。 特に批判的読書法は、素直な私にとって有効ではないか。 具体例がすべてわかりやすく、納得させられるものばかりであった。 少しでも複眼思考ができるように気をつけよう。
Posted by
僕に「疑う」という行為を教えてくれた本。 新聞、テレビ、ネットで発する情報を鵜呑みにせず、どのように自分で考えるかをわかりやすく教えてくれる。 学生のうちに読めば、その後の学生生活を大きく変えるだろう本。 この表紙はいかがと思うが。
Posted by