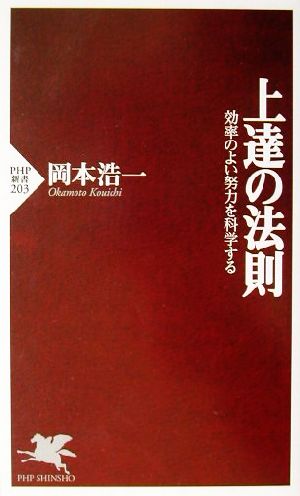上達の法則 の商品レビュー
初級者かた中級者そして上級者になるまでの、上達に係る普遍的なプロセス、法則を示したものです。上級者を目指すなら、その指針を得るための格好の材料になる本であります。
Posted by
上級者と呼ばれる人の共通点などが書いてある。 そして、何かに上達するという経験を経たものは、人格に余裕ができる、何か必要なときには、またマスターできると本人が思えるし、他の人もまかせられる、そういう人格が備わるという。 私も、自分なりの弱点克服の練習方法を生みだす、自我関与の度...
上級者と呼ばれる人の共通点などが書いてある。 そして、何かに上達するという経験を経たものは、人格に余裕ができる、何か必要なときには、またマスターできると本人が思えるし、他の人もまかせられる、そういう人格が備わるという。 私も、自分なりの弱点克服の練習方法を生みだす、自我関与の度合いを高めるなどのこの本で紹介されていたことを、実行に移してみたい。
Posted by
将棋と茶道について興味が少しでもないと全くイメージがわかない懸念がある一方で、言ってることは全くもって的を得ている。上達するにはまず手をつけて、手触りをもってからあーだこーだ考えればいいのだ。そしてブレイクダウンをするにはメモを取る習慣が必須。そんだけガムシャラにやらんと上達って...
将棋と茶道について興味が少しでもないと全くイメージがわかない懸念がある一方で、言ってることは全くもって的を得ている。上達するにはまず手をつけて、手触りをもってからあーだこーだ考えればいいのだ。そしてブレイクダウンをするにはメモを取る習慣が必須。そんだけガムシャラにやらんと上達ってのはないんだと。至極ご尤もな話。スキルとして人の忘却は1日、3日、1週間だから上達したい程度に合わせてトレーニングを週1、週2、週5にして、それ以上はやらないと腹を括るというのが今回得られた知見。あれ?じゃあ仕事ってものすごく上達するはずなのでは?そんなー。
Posted by
上達する為の方法をリスク心理学の先生が教えてくれる。初級者から中級車へのステップ、そして、さらに上級者へのステップにはそれぞれ重要になる要素がある。まねることや得意分野を持つこと、好きになることは一般的に物事が上手になる為に必要なことである。上級者であるほど、観察範囲が広く、そし...
上達する為の方法をリスク心理学の先生が教えてくれる。初級者から中級車へのステップ、そして、さらに上級者へのステップにはそれぞれ重要になる要素がある。まねることや得意分野を持つこと、好きになることは一般的に物事が上手になる為に必要なことである。上級者であるほど、観察範囲が広く、そして、深い傾向にあるとの解説に納得。 いろいろと例を出して紹介してくれるが、音楽と将棋の例が多く、著者の趣味に偏りすぎている感あり。
Posted by
努力の頻度は週2回から始めるのが良い、ノートを取る、などのような具体的な提案とその理由がきちんと述べられている点に好感が持てます。
Posted by
→廃棄 わかっちゃいるけどどうすればいいの、的な指南内容で隔靴掻痒感あり。頭の良い人にはわからないことがわからないのかも。
Posted by
スキーマやコード化が上達の道。一つのものをとことん追求すれば、他のものにも応用が利くなど、なんとなくそうなのかなぁと日常思っていることが、例をあげて解説されていて納得できる。
Posted by
どんなに努力しても、努力の仕方が間違ってたら 効果的にステップアップできないじゃん? というわけで手に取ってみました。 目次をさらっと見たときは「スキーマ」とか 「コードシステム」とか専門的な言葉が並んいて 割と学術的な専門書なのかなと思ったけど、 読んでみたら結構分かりやすい...
どんなに努力しても、努力の仕方が間違ってたら 効果的にステップアップできないじゃん? というわけで手に取ってみました。 目次をさらっと見たときは「スキーマ」とか 「コードシステム」とか専門的な言葉が並んいて 割と学術的な専門書なのかなと思ったけど、 読んでみたら結構分かりやすい内容で読みやすかった。 勉強でもスポーツでも趣味でも 何かこれといったものを効率的に上達するためのルール、 みたいなものが論理的に説明されているんだけど、 「ああ、これ分かる!」って納得できるものが多かったです。 感覚的に意識していたものが言語化される爽快さがありました。 上級者は自分なりの独自の言葉で説明する力を持っているとか、 細かな手がかりから他者評価ができるとか。 もっとあったような気がしたけど忘れた。 スランプの構造とかも分かりやすかった。
Posted by
新しく何かを習いたいと思うならば、脳科学・心理学的側面から上達までのプロセスについては、知っておいたほうがよいだろう。自動車運転、楽器、将棋、英会話、茶道等幅広いテーマを例にどのように覚え、どのように習得し、どのように熟達するのかがわかる。
Posted by
本当にオススメの本です。 どういうことに意識して、どういう風に練習すればいいかを教えてくれるので、 英会話、ギター、野球、サッカーなど何でも、挑戦しようと思っていることがあれば、 その前にぜひ、この本を読んでみてください。 この本では、上達のために記憶のメカニズムを上手に...
本当にオススメの本です。 どういうことに意識して、どういう風に練習すればいいかを教えてくれるので、 英会話、ギター、野球、サッカーなど何でも、挑戦しようと思っていることがあれば、 その前にぜひ、この本を読んでみてください。 この本では、上達のために記憶のメカニズムを上手に利用しています。 人は、一瞬の記憶から、短期の記憶(数秒)へコード化しているが、 この短期の記憶は同時に7つ(7チャンク)が限界なのです。 実際に、できる人はチャンクの数が多いのではなく、その前のコード化が優れているそうです。 一見すると何の関係もないような大量の流れをコード化して 一つのチャンクにすることで、より多くのことを使えるようになり それが上達につながっているのです。 このコード化の磨き方がいろいろ書かれていますので、 自分に合うものを見つけて、ぜひ参考にしてみてください。
Posted by