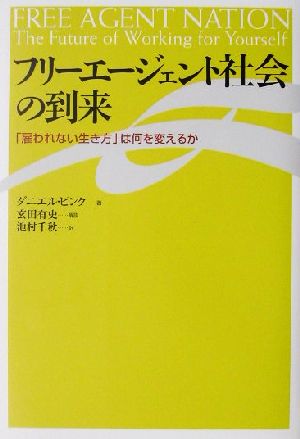フリーエージェント社会の到来 の商品レビュー
バランスではなくブレンド。 ハイリスクではないとリターンは得られない。教育、税制まで書かれていて面白い。 日本版のこう言った本はないのですかね。知りたいです。
Posted by
本書の目的は、フリーエージェントの「真実にかなり近い」姿を語ることです。 2002年時点のアメリカで、すでに労働人口の4分の1は、フリーエージェントとして働いていた。 気になったことは以下 ・フリーエージェントになったのは、嫌な上司非効率な職場、期待外れの給料に嫌気がさしてや...
本書の目的は、フリーエージェントの「真実にかなり近い」姿を語ることです。 2002年時点のアメリカで、すでに労働人口の4分の1は、フリーエージェントとして働いていた。 気になったことは以下 ・フリーエージェントになったのは、嫌な上司非効率な職場、期待外れの給料に嫌気がさしてやめた人、レイオフ合併倒産で会社を離れざるを得なかった人がいる。 ・忠誠心は死んだ。タテの忠誠心にかわってヨコの忠誠心がうまれている。 ・フリーエージェントは、3つのタイプ。 ①フリーランス:特定の組織に雇われずに様々なプロジェクトを渡り歩く ②臨時社員:恒久的な職につきたいが、経済の階段の最下層に甘んじている ③ミニ起業家、コンサルタント:5名未満の会社を興して起業する ・かって家族的温情主義をとっていた企業もそれを放棄した。企業の寿命が短くなっているのに、人の寿命は長くなっている。 ・企業はリスクをとれなくなっている。⇒個人にリスクを転嫁している。 ・フリーエージェントは、労働のジャストインタイムといえる。必要なだけの労働力を必要な時に確保する。 ・誰よりもアメリカ人は働いている。忙しいのが嫌なのではなく、自分でスケジュールができないのが嫌だ、意味のある仕事ができないのが嫌だ。 ・組織の押し付けでなく、意味ある仕事がしたい。自由、自分らしさ、責任、自分なりの成功を求める。 ・ピーターの法則:人は自分の能力を超えて、無能となる地位まで昇進する ・どんな仕事をするときも、お金をもらって勉強させてもらっていると考える ・学校、教育の現場はあいかわらず変化していない。新しい教育のあり方が台頭してくる。 ・フリーエージェンドは、緩やかなパートナーシップに属している ・公式の組織図とは別に実際の人のつながりの組織図がある ・フリーエージェントとのつながりは、「信頼」。汝の欲するところを他人になせ。 ・フリーランスを阻む制度、医療制度、税制度 等々。旧来の制度は雇用を前提に作られている。 ・臨時社員が正社員になるのは難しい。なぜなら、年収の30%を派遣会社に払わなければならないから。マイクロソフトは訴えられて臨時社員と正社員にした。 ・大半の管理職はこれから生き残れない。生き残れるのは、立ち上げから、完了までを監督するプロジェクトマネージャー 結論は、「これから多くの人が独立を宣言し、仕事でも私生活でも自分の運命を切り開くようになる」、それが一つの進歩であることは間違いない。 目次は以下の通り プロローグ 第Ⅰ部 フリーエージェント時代の幕開け 第1章 組織人間の時代の終わり 第2章 3300万人のフリーエージェントたち 第3章 デジタルマルクス主義の登場 第Ⅱ部 働き方の新たな常識 第4章 新しい労働倫理 第5章 仕事のポートフォリオと分散投資 第6章 仕事と時間の曖昧な関係 第Ⅲ部 組織に縛られない生き方 第7章 人と人の新しい結びつき 第8章 互恵的な利他主義 第9章 オフィスに変わる「第三の場所」 第10章 仲介業者、エージェント、コーチ 第11章 「自分サイズ」のライフスタイル 第Ⅳ部 フリーエージェントを妨げるもの 第12章 古い制度と現実のギャップ 第13章 万年臨時社員と新しい労働運動 第Ⅴ部 未来の社会はこう変わる 第14章 リタイアからeリタイア 第15章 テーラーメード主義の教育 第16章 生活空間と仕事場の穏やかな融合 第17章 個人が株式を発行する 第18章 ジャストインタイム政治 第19章 ビジネス、キャリア、コミュニティーの未来像 エピローグ
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
いろいろと楽観的過ぎるので、特に人に対して誇れるスキルや実績の無い人が転職を考えている時期に読む本としては適切では無い気がしました^^;。ただ、人に対して誇れるスキルや実績のある人が、この先、管理職を目指すという行為に対して違和感を感じてしまっている人にはオススメの本だと思います☆ ちなみに僕は、この本全体に感じられる、「働き者の社員が怠け者の社員に補助金を与えているに等しい」と言った論調の考え方が余り僕は好きでは無いです^^;。確かに、同じ組織内に限定して言えば正直そう思ったりする時もあったりしますが、怠け者には怠け者に見合ったつまらない仕事しか回ってきません。逆に働き者には、その能力に見合ったワクワクするような楽しい仕事が回ってくると思います。 また、組織全体に視野を広げて考えてみると、何を持って「働き者」「怠け者」と定義するかにも疑問を感じてしまいます。例えば、成果が直接数値として現れる営業職の人から見れば研究開発職の人なんてただの怠け者に見えてしまうと思いますし、またその営業職の中でも既存顧客向けの営業をしている人から見れば新規顧客向けの営業をしている人なんてただの怠け者に見えてしまうと思います。 という訳で、基本的に僕はこの本に書いてある内容に対して総論反対です^^;。みんながみんな目先の事しか考えなくなってしまう事は危険だと思いますし、また、みんながみんな「自分さえ良ければ良い」「能力の無い奴が給与が低いのは当然だ」みたいな感じの社会が必ずしも素晴らしいとは思いません。ただ、職種によってはこういった働き方もアリだなあとは思いますし、また、95ページに書いてあった「遠い将来のご褒美のために一生懸命働くのは、基本的には立派な事である。けれど、仕事そのものもご褒美であって良いはずだ。」と言った意見には強く共感を覚えました☆ ひとまず僕のような凡人が勘違いしてフリーエージェントになるなどと言ったりする気はサラサラありません^^;。ただ、逆に僕自身が会社の方からリストラされてしまう可能性もありますし、受身で仕事をするのでは無く、常に起業者意識を持って業務に励んでいきたいと思います!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
何が貴重なのか? 古典的資本は今も変わらず貴重なままなのか? 原始人は生き延びることが大変だった。 だから健康状態を保つ栄養が貴重だった。 生活を便利で楽しくしてくれる物が貴重だった。 今、食料や物はあふれている。 必要だし重要だけれど貴重ではない。 物も溢れている。 今は何が貴重なのか? 今後は何が貴重になっていくのか? 貴重なのは...自分を特別化するストーリーであり、それを後押しする枠組みだ。 現代人は生き延びられて当たり前。 そう著しく不本意に死ぬことはない。 いわゆるマズローの5段階欲求がある。 1. 自己実現の欲求 2. 承認 (尊重) の欲求 3. 社会的/所属と愛の欲求 4. 安全の欲求 5. 生理的欲求 これらは、下から順にではなく、 全てが十分かつバランスよく満たされる必要性がある。 先人の努力により、現代では4〜5は満たされた。 しかし、1〜3あたりの上位レイヤの充足が足りていない。 とくに上位レイヤほど満たされていない。 大事なのはこれを満たす枠組みだ。 標準化、均一化された枠組みへの適合は1〜3を満たさない。 需給で考えると、例えば ピラミッド型の組織に属して上意下達では供給者の欲求が満たされることはない。 また、そのような枠組みで提供される製品やサービスも、顧客の欲求を満たさない。 それじゃあ、自己実現はおろか、尊いものとして重んじられていないではないか。 標準化、均一化された枠組みはスケールメリットが大きい。 だから、規模の経済が効くし、物が重要であればとくに物的、金銭的資本がものを言う。 でも、でも、それはもう貴重じゃない。 すでにレッドオーシャン化したレイヤへのアプローチをいくら改善しても、 いわゆるマズローの欲求の上位レイヤという需要を満たせない。 貴重なのは「人」の注目 (attention) だ。 注目という資源は、人の命と同様、全員に同じだけある。 これをどう振り向けるかで、自分や他人を特別化できる。 人の「特別化」に (そう感じられるストーリーに) 価値が生じる。 今のピラミッド型組織は義務労働みたいなもの。 先人の努力により、それを卒業できるほど社会が洗練されてきた。 社会システムはまだ追従できていないが、あたらしい形態として フリーエージェントが台頭してきた. 貴重な資本とは「人」。 価値とは自分や誰かを「特別化」すること。 圧倒的個人の時代である。 この本は20年前 (2000年そこそこ) に書かれたものだが、 その時点でも、控えめにいってアメリカ人の4人に1人はフリーエージェント。 そして、不本意な期間労働などではなく、自ら意図したフリーエージェントが増加中。 インターネットが、このようなライフスタイルを後押しするということであった。 今日では、どのくらいのフリーエージェントがいるのか? オーガニゼーション・マンより幸福、自由、収入などを総合的に勘案して より望ましいライフスタイルとして定着を深めたのか? 社会システムの整備も進んだのか? あるいは、フリーエージェントに変わる新たなスタイルは発生していないか? 現状報告も見てみたいところである。
Posted by
なんとなく手にとってみた本。 400ページ近い分量なのと、プロローグを見て、目次を見て、解説、訳者あとがきを見る。各章の最後にTHE BOXというまとめがあるのでそこを読む。 この本は2002年発刊なので、昔を思い出しながら、自分の周りにも独立してフリーになる人たちを何人か見てき...
なんとなく手にとってみた本。 400ページ近い分量なのと、プロローグを見て、目次を見て、解説、訳者あとがきを見る。各章の最後にTHE BOXというまとめがあるのでそこを読む。 この本は2002年発刊なので、昔を思い出しながら、自分の周りにも独立してフリーになる人たちを何人か見てきたし、万年派遣なんて言う世界と、派遣を採用する側の意見なんてのも実生活では聞けたりして、興味深いものはあるにせよ、いま2020年のコロナの世界で、更に進化したであろうフリーエージェントって言うものと在宅勤務がメインになった会社員の自分との間で、何がメリットで何がデメリットなのかと言う点については思考停止だ。フリーになった事がない上に、なった時の各種のオーバーヘッドを考えると、フリーという選択肢はなかなか無いかなと再認識…
Posted by
筆者であるダニエル・ピンク自らが全米各地を取材し、アメリカで働く人の4人に1人は組織に雇われない「フリーエージェント」だとして話題となった書。 将来が不確定な日本においても、今後確実に増加すると予想されるフリーエージェントの生き方指南書。 今後独立や組織に雇われずに働いて生きてい...
筆者であるダニエル・ピンク自らが全米各地を取材し、アメリカで働く人の4人に1人は組織に雇われない「フリーエージェント」だとして話題となった書。 将来が不確定な日本においても、今後確実に増加すると予想されるフリーエージェントの生き方指南書。 今後独立や組織に雇われずに働いて生きていきたいと考えている人には是非読んでいただきたい一冊。 400ページというボリュームであるが、平易な文章で書かれているため、非常に読みやすい。
Posted by
アメリカはとっくの昔にフリーエージェント社会になっていると思っていたのだが、意外にそうなったのは遅いことをこの本で知った。戦後は組織人の社会が長く、20世紀末にようやくフリーエージェント社会になったというのだ。 この本は、そんなアメリカのフリーエージェント社会の実情を良く描いてい...
アメリカはとっくの昔にフリーエージェント社会になっていると思っていたのだが、意外にそうなったのは遅いことをこの本で知った。戦後は組織人の社会が長く、20世紀末にようやくフリーエージェント社会になったというのだ。 この本は、そんなアメリカのフリーエージェント社会の実情を良く描いている本である。日本も遅ればせながら、フリーエージェント社会に近づきつつあると思う。最近はやりのノマドライフも、すでにこの本に十分に記述されていんた。ある意味パクリでは?と思ってしまうぐらいに。
Posted by
・従業員管理の最善の方法は、フリーエージェントのように扱うこと。 ・学校は、オーガニゼーションマン養成に理想的なシステム。
Posted by
過去の読書会の人気課題本ということで読んでみた。確かに日本でもこの本で紹介されているような生き方を選んだ人はいる。しかし、この本で紹介されているような生き方は、誰にでもできるものではなく、社会的に高く評価してもらえる技術や人脈などが必須であることは留意するべきだと思う。もちろん、...
過去の読書会の人気課題本ということで読んでみた。確かに日本でもこの本で紹介されているような生き方を選んだ人はいる。しかし、この本で紹介されているような生き方は、誰にでもできるものではなく、社会的に高く評価してもらえる技術や人脈などが必須であることは留意するべきだと思う。もちろん、著者自身が、「高級官僚の天下り」ということも、ある程度差し引いて考えるべきである。また、著者がやたらに楽観的で、いわゆる「派遣切り」の問題を”一部の例外”として矮小化している態度に、とても違和感を覚えた。
Posted by
2002年に出版され、話題になった1冊とのこと。企業から離れ、独立して個人事業を営むフリーエージェントが米国では事業者全体の25%も占めていたそうで、これはかなり驚きの数字である。大企業に勤める暮らしに比べ、安定性には欠けるし、社会保障も不十分で、仕事とプライベートの区別もなくな...
2002年に出版され、話題になった1冊とのこと。企業から離れ、独立して個人事業を営むフリーエージェントが米国では事業者全体の25%も占めていたそうで、これはかなり驚きの数字である。大企業に勤める暮らしに比べ、安定性には欠けるし、社会保障も不十分で、仕事とプライベートの区別もなくなるというフリーエージェント的な働き方だが、職住隣接、家族との時間も増え、何より自分で思うように好きな仕事ができるという魅力には代えがたいのだろうことは容易に想像がつく。 翻って、日本はどうなのだろう。この2002年からの15年間、一時は米国同様に、フリーエージェント的な働き方がもてはやされた時期があった。しかし、リーマンショックやグローバル化についていけず企業の業績が落ち込む中で、そのような生き方は派遣労働者の厳しい実態を通じて問題視され、勢いを失い、今また安定的な生き方に回帰してきたのではなかったか。 しかし、この日本と米国の環境の差は、新規産業を生み出すダイナミズムの差として現れているのではないか。滅私奉公的な働き方はなくなってきたとはいえ、彼我の差はまだまだ大きい。2002年当時に読んでいれば、新たな視点ももらえた1冊だと思うが、現時点で読むとそんな読後感になってしまうところ。
Posted by