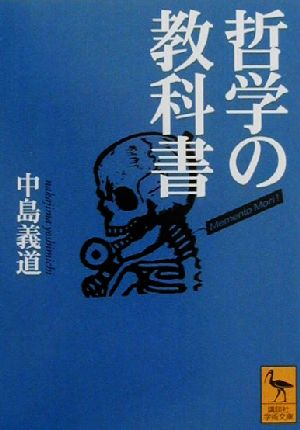哲学の教科書 の商品レビュー
この「私」を通じてしか、哲学できないことの絶望を感じさせてくれる本。 哲学とは何ではないか、哲学者になるにはどうすればいいか、という項目はなかなか目新しく、新鮮に読めた。
Posted by
哲学に対する姿勢について考えさせられる.哲学者と哲学思想家との違いは言われてみればその通りである. 哲学的中身の取り扱いについては単純に賛同できないところもあるものの,この本の最も重要なところは「読者に哲学的思索を想起させようとしている」ところかと思う.
Posted by
初めての「哲学」の本だったが、予想以上にのめりこめた。哲学は、おもしろい反面「深入りは危険」という狂気を孕んだ領域だということが少しながら感じた。 本書では、死とは、存在とは、言語とは、心とは・・・etcという哲学の命題を著者の経験を踏まえながら伝えているし、多くの示唆を与えては...
初めての「哲学」の本だったが、予想以上にのめりこめた。哲学は、おもしろい反面「深入りは危険」という狂気を孕んだ領域だということが少しながら感じた。 本書では、死とは、存在とは、言語とは、心とは・・・etcという哲学の命題を著者の経験を踏まえながら伝えているし、多くの示唆を与えてはくれるが、いかんせん難しい。内容はもちろんだが、哲学独特の表現は慣れないと読んでいくのはしんどい(自分だけかもしれないが)。 しかしながら、教科書と銘打っているだけあって、思想と哲学の違いや哲学研究者と哲学の違いなど興味深いテーマでひきつけてくれた。 巻末には引用文献やオススメ本なども載っており入門書としては十分だと思う。
Posted by
本屋に行って、見つけるとニヤニヤしながら買ってしまう中島義道の本。 感想を書くのも結構骨が折れる内容です。 「あの人には哲学がない」 なんて人物評をしたことがある方は是非ご一読のほどよろしくお願いいたします。
Posted by
講談社現代新書にしては、文面が硬くなく柔らかいために、読みやすいと思う。 今回は自分の目的にあわずに読書を避けたが、哲学全体を再構成するには良い本でないかと思う。いつか、読んでみたい。
Posted by
第三章がおもしろく、ためになった。 ・「今があるのみ」であり、自責の念は不要。 ・「思うこと」と「意志」の違い。 形や行動となって表れるものでしか、他人からみて、その人の「意志」は推察できない。 腑に落ちる本でした。
Posted by
初めての中島義道。講談社学術文庫は学生には高いので我慢してた。先日ようやくamazonで購入。 当然ですが、哲学に教科書なんて存在しません。 この本もそういう内容をくどくど書いた本です。 初めて哲学の本を読む人や哲学に教科書があると思っている人にはおススメ。 (推薦者:篠崎...
初めての中島義道。講談社学術文庫は学生には高いので我慢してた。先日ようやくamazonで購入。 当然ですが、哲学に教科書なんて存在しません。 この本もそういう内容をくどくど書いた本です。 初めて哲学の本を読む人や哲学に教科書があると思っている人にはおススメ。 (推薦者:篠崎)
Posted by
――哲学の教科書、なんてものはない、ということを透徹した著者によってつづられた哲学の教科書は自己矛盾と自己批判を経てつづられていく。そのあたりにツァラトゥストラの匂いを嗅ぎとった。哲学者は総じて胡散臭いが(学者であろうとも)、俺が認める哲学者は、「自ら苦悩しその実感を基に哲学して...
――哲学の教科書、なんてものはない、ということを透徹した著者によってつづられた哲学の教科書は自己矛盾と自己批判を経てつづられていく。そのあたりにツァラトゥストラの匂いを嗅ぎとった。哲学者は総じて胡散臭いが(学者であろうとも)、俺が認める哲学者は、「自ら苦悩しその実感を基に哲学している人間」である。「実感」のない哲学などは所詮、教養でしかない。そこに知の好奇心はあっても圧倒的な生々しさは見出せない。だが、そこにはある種病的なところがある。著者は、哲学をして、「病気に近しくて、凶暴性・危険性・反社会性的な思考に絡めとられた悪趣味」と評している。だが、個人的にはそこに一票を投じたい。哲学も、思想も、文学もなければなくていい。しかし、思考に絡めとられぬけ出せなくなった人間にとっては、絶対的に必要な分野なのである。そして、その人間は絶えず一定数存在しているのだ。それゆえに、ソクラテスやプラトンから始まり、ニーチェやハイデガーなどの著書は未だに読まれ続けるのである。 ちなみに、ヴィトゲンシュタインは論理的哲学考において、哲学的な命題に解を出し切ったと考えたらしい。そこで一度哲学そのものに終止を打ち、だが、その後、別の尺度から哲学を再考した。ここに哲学の抱える一つの矛盾があるのかもしれない。哲学の目的とは答えを導き出すことなのか?しかし、違う。なぜならば、答えを出したところで思考はやまないからである。思考は巡り続ける。ヴィトゲンシュタインがもし、本当にそこで哲学を終わらせたかったならば、論理的哲学考を仕上げた時点で自殺しなければならなかった。しかし、彼は自殺しなかった。結果として、思考は巡り続ける。思考はとある一つの地点にとどまってはいられない。少なくとも、哲学という迷路に迷いこんだ時点でそいつは思考から不可分の存在となりうる。これは才能であると同時に、荷物なのであろう。では、哲学とはなんなのかと言うと、それはつまり考え続けるということに他ならない。考え続けるために考え続けているのではないか?無論、答えが出ることもある。しかし、だからといってほかの分野がある。その答えへの反証もある。思考はやまない。思考することこそが哲学の意義であるとするならば、哲学に終焉はない。いや、終焉を迎えさせてはいけないのである。だが、仮に答えが出尽くしたところで思考はやみはしないだろうから、そういう意味において哲学には終わりはない。それを知らしめてくれる一冊であったと言えるかもしれない。 また、本著の特徴としては、哲学史概説となっていないところがあげられる。著者独特の哲学観みたいなのが所々提示され、しかし、深く追及する前にぱっと手を離され、後は自由にやってみてくれとだけ冷たく(温かく?)述べて次へと進んでいく。著者自身としては自らこう思うと断じているものの、批判はどんとこい、という鷹揚な姿勢をとっているあたりに哲学者としての評価が高まるように思う。権威に背を向けているのである。また、所々上げられている例などを見ている限り、地味に文学性を持っている方だと思われる。
Posted by
平易な言葉で<哲学>を語る。違和感や問題意識がなければ、ただ知識としての哲学を学んでも意味がない、という指摘は頷ける。これは哲学以外の学問にも通じる部分だが、人が生きるにあたって、哲学以上に真摯な姿勢が求められるものはないということでもある。 以下、気になった記述。 ・理想社会...
平易な言葉で<哲学>を語る。違和感や問題意識がなければ、ただ知識としての哲学を学んでも意味がない、という指摘は頷ける。これは哲学以外の学問にも通じる部分だが、人が生きるにあたって、哲学以上に真摯な姿勢が求められるものはないということでもある。 以下、気になった記述。 ・理想社会が現実化にあたって、現実化される前、現実化された後の人の死は問題にならないだろうか。 ・哲学と思想の違い=主観的と客観的の違い ・宗教の中心部にはこうした排他性があると思っており、救済そののの語りにくさ以上にこうした言語的コミュニケーションを最終的には拒否するところ、言語的コミュニケーションを最終的には信頼していないところに哲学との大きな差異を嗅ぎつけます。 ・哲学は科学ではない(科学は個物の個物性に正面から向き合わないから) ・哲学とはあくまでも自分固有の人生に対する実感に忠実に、しかもあたかもそこに普遍性が成り立ちうるかのように、精確な言語によるコミュニケーションを求め続ける営み、と言えましょう。 ・原因とは結果が何であるかに依存し、その結果との「関係」においてはじめて意味づけられるような概念だからです。 ・因果関係の「原型」は意志行為のうちにある ・他者問題とは、他人に乗り移ることではなく、他人と一体になることでもなく、自分であり続けながら異質な他人を理解することです。 ・哲学の議論は他人に同調することを抑制するところ、自分と他人との差異を精確に測定するところに、はじめて開かれてくるように思います。 ・真の哲学とはまさにソクラテスやニーチェがそうであったように、同時代人から処刑されるか狂気に陥るか、そのように危ういもの、安穏と権威の上にあぐらをかいているものではない。 ・西洋哲学における言語の不平等構造 ・西洋哲学から学ぶこと--それは「言葉」に対する信頼、個人と個人が向き合って「弁論」によって真理に至るというソクラテス以来西洋哲学の硬い基層をなしている信念です。 ・ソクラテスと利休の死に際の違い
Posted by
批判的に読むことはまだ自分には難しいが、 少なくとも自分がいかにものを考えていなかったかを気づかせられた。 読者の人生体験によっていくらでも得るものが変わると思う。
Posted by