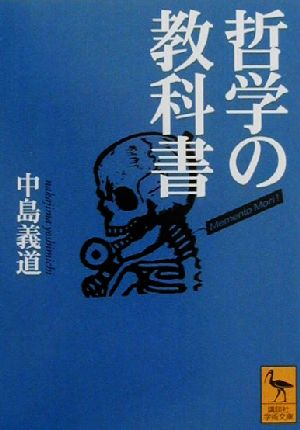哲学の教科書 の商品レビュー
哲学の入門というと哲学史から勧めることは多いが、この本はそういう慣習と離れて哲学が私たちの身の回りとどう繋がるかから踏み込んでいて大変わかりやすかった。 私たち存在の根源にもつながる、死だったり時間をそれに答えを出すのでなくて考えることに哲学がある。 それは小難しいことでなくとも...
哲学の入門というと哲学史から勧めることは多いが、この本はそういう慣習と離れて哲学が私たちの身の回りとどう繋がるかから踏み込んでいて大変わかりやすかった。 私たち存在の根源にもつながる、死だったり時間をそれに答えを出すのでなくて考えることに哲学がある。 それは小難しいことでなくとも考え続けること。 明日が次がどうなるかわからないだとか、それこそ思考実験のようで普段は想起しないことー明日、世界が破滅するかもしれない…目覚めないかも知れないーそういったことについて思いを巡らすきっかけにもなった。 かといって難しいことはなく、また形式的だったり権威的な文章で語られていないため読みやすい。 時たま抽出される実例…死刑囚の手紙だったり著者の体験談も瑞々しく効果的なものを心象に加えていた。 考えること疑問に思うこと、そこに哲学的な何かがある。 ある程度学んだ末に読んでも初心を思い出させ新たな発見もさせうる書物だった
Posted by
哲学の読書会の課題本で読みました。 わたしは、哲学ができる環境ってことがすごく恵まれていて特権階級的だって意見があって面白かったです。 中島義道さんがなぜこのような本を書いたか。ほとんどの入門書に書かれていないこと、お行儀のいいことではありません。迷走している人にはおすすめかも...
哲学の読書会の課題本で読みました。 わたしは、哲学ができる環境ってことがすごく恵まれていて特権階級的だって意見があって面白かったです。 中島義道さんがなぜこのような本を書いたか。ほとんどの入門書に書かれていないこと、お行儀のいいことではありません。迷走している人にはおすすめかも。 あ、していないようにみえる人かそかな。 第四章 哲学は何の役にたつのか。 哲学は何の役にもたたない で、無用の用という荘子の教えがとても良かった。散木となりたい。 哲学とはなんぞや。迷い続けてもわかるもんでないなとかんじました。
Posted by
なぜ読んだ?: 同じ高校の友人がこの著者の本を好んでおり、高校時代に読むよう勧められもしたが、読むには至らなかった。 時は過ぎ、小坂井敏晶『社会心理学講義』にてこの本が引用されており、哲学や哲学者に対する態度に感銘を受けたため、この本を読むことにした。 感想総論: まえがきから...
なぜ読んだ?: 同じ高校の友人がこの著者の本を好んでおり、高校時代に読むよう勧められもしたが、読むには至らなかった。 時は過ぎ、小坂井敏晶『社会心理学講義』にてこの本が引用されており、哲学や哲学者に対する態度に感銘を受けたため、この本を読むことにした。 感想総論: まえがきから、「哲学に教科書などないことをこれでもかと語った」と断言するあたりが痛快である。 こういうやつは哲学者ではないとか、西洋哲学コンプレックスの話とか、大学時代の哲学病の話とか、実に熱の入った記述が印象に残った。 いわゆる普通の"哲学の教科書"というのは、大抵が哲学史を概説したものであろう。対してこの本では、哲学とは何ではないのか、哲学固有の問いとはなんなのか、哲学者とはどんな種族かといった内容が語られている。誰がどう考えていたかを翻訳して横流しするのではなく、自分の頭で考えた思索を表現しているのが良いと思った。
Posted by
哲学に対してテレビ的な誤ったイメージを持っている人、哲学に興味のない人、哲学にインテリなイメージを持っている人、とにかく読んでみたほうがいい。 哲学は何の役にも立たない、が、哲学の問いを心の片隅に置いて生きるのとそうでないのとでは、何かが違う、かも?
Posted by
これは哲学の歴史を教えるのでも、さまざまな哲学の案内書でもない。哲学でないものは何かから、哲学とはどういったものかを感じ取らせる。哲学は子供の問いに似たもので、生きるとは、死とは、存在とは、私とは、心とはと問う。自分の存在をかけて問い詰めるものが哲学者であるとか。七面倒くさいこと...
これは哲学の歴史を教えるのでも、さまざまな哲学の案内書でもない。哲学でないものは何かから、哲学とはどういったものかを感じ取らせる。哲学は子供の問いに似たもので、生きるとは、死とは、存在とは、私とは、心とはと問う。自分の存在をかけて問い詰めるものが哲学者であるとか。七面倒くさいことにを悩みながら言葉を操って精緻に語ることが哲学者か。自分にはなれなことだけは分かった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
哲学の大きな特徴は、時間や自我、物体、因果律などについて徹底的な懐疑を遂行することであり、この点で、これらに拘泥せずに前提とした上で論じられる思想や文学、芸術、人生論、宗教とは異なっているのである(なお、哲学でないことがこれらの価値を下げることはない)。また、物理学、社会学、心理学などの諸科学では、私固有の意味付けや印象は排除され、客観性が求められるが、哲学は、自分固有の人生に対する実感を忠実に、しかもあたかもそこに普遍性が成り立ちうるかのように言語化する営みである点で異なっている。ゆえに、科学には客観的な答えはあるが、哲学は、人類の歴史が終わるまで終わりはなく、問い続ける運命にあるのである(哲学の一番の敵は、「分かったつもり」になることである)。 ところで、「死」を全くの「無」と仮定することは、我々の実感に合わない。すなわち、我々は死を不幸でかわいそうな状態というマイナスの了解事項として捉えているである。そしてこのことが、我々が日常的「死」を直視しないようにして生きている原因の一つなのかもしれない。しかし、われわれが死ぬことよりも確実なことはない以上、「死」について恐れず考えるべきであり、自分が一滴もいない世界について思いを寄せることほど欺瞞的なことはないのである。 この他にも、哲学が取り組んでいる固有の問いには、時間、因果関係、意志、存在、他者、善などがあるが、これらの問いに答えようとする哲学は、医学や法学のように技術や道具として役立つものではない。ただ、哲学は徹底的に疑うところから出発するため、前提とされている了解事項や、我々に押し寄せる不幸(様々あるが、究極的には「死」)をごまかさずに直視する目を養うことにつながる。つまり、哲学とは、「死」を宇宙論的な背景によって見つめることであり、それによって、小さな地球上のそのまた小さな人間社会のみみっちい価値観の外に出る道を教えてくれるものなのである。 おそらく本書は、様々な例を挙げることで、哲学の感触を読者に届けようとして書かれたものであると思われる。そのため、哲学に関する本にしては、特に中島義道にしては、分かりやすい本になっていると考えられる。 哲学的な問いとはどういうものか理解でき、勉強になった(例えば、「近代とは何であったのか」は哲学的な問いではなく、「過去はいかに存在するのか」は哲学的な問いである)。また、日頃から哲学的視点を持ち合わせていることは、言葉の意味に敏感になったり、因果について深く検討したりすることにつながり、自分の視野や思考が広がると感じた。
Posted by
今まで多くの哲学書を読んでさっぱり理解できなかったが、この本を読んで理解できなかったのも仕方がないということが理解できた。所詮、哲学は言葉遊びであり、しかしながらその言葉遊びをしなくては人間は生きていけないということだろう。途中の哲学的考察はそれでもやっぱり難解。
Posted by
みずからの死について恐怖を抱えながら少年時代をすごした著者が、「哲学とは何か」という問いに答えています。 著者は、「最大の哲学問題は「死」である」といい、「死」や「私」、「他者」、「存在」といった問題についてとことん理性的に考察をおこなっていく態度が、哲学と哲学でない思想や文学...
みずからの死について恐怖を抱えながら少年時代をすごした著者が、「哲学とは何か」という問いに答えています。 著者は、「最大の哲学問題は「死」である」といい、「死」や「私」、「他者」、「存在」といった問題についてとことん理性的に考察をおこなっていく態度が、哲学と哲学でない思想や文学、芸術との違いをなしていると主張します。 「哲学の教科書」というタイトルで、しかも巻末には読書案内まで付されており、やさしい哲学案内のような装いですが、みずからの「死」にこだわり抜く著者一流のセンスが基調に流れています。
Posted by
哲学は何ではないか 「わかったつもり」はひどく危ないが、 其れさえ認識してないことのほうがもっと危ない p86 ピカソ 人生論はPの部分であって全体もしくは上位ではない よい 青年とは常に抽象的な問いを発し悩み続ける存在 ドスト 銃口 議論 全体によって部分がわかる
Posted by
10年前に読んで腑に落ちなかったものが、10年経った今、腑に落ちない。。。 その間に、色々な哲学書を読んだが、結局、解答なんてないのだろう。そういう意味では、いつも「出発点」に戻らされる良書。 それとは反して、哲学に「教科書」がないということ。 更には、一般的な「解答」などない...
10年前に読んで腑に落ちなかったものが、10年経った今、腑に落ちない。。。 その間に、色々な哲学書を読んだが、結局、解答なんてないのだろう。そういう意味では、いつも「出発点」に戻らされる良書。 それとは反して、哲学に「教科書」がないということ。 更には、一般的な「解答」などないということ。 哲学はセンスであり、病である。 ある意味、この本で扱われている諸問題が気になり続けるのでないのならば、それは、「捨てられるべき梯子」であり、「快癒」である。。。
Posted by