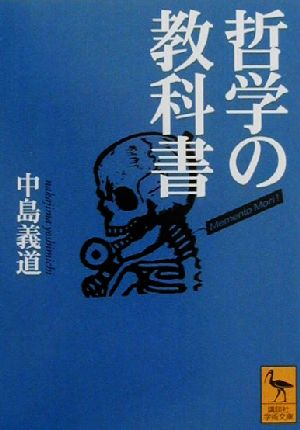哲学の教科書 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
原因や結果とは、「こうしたことは二度と起こってほしくない」とか「この現象は回避したいものだ」とかの原始的なわれわれの欲求にしたがって、自然現象をさらにとらえなおすことです。P163 因果関係とは、「起こってほしくない」という思いを込めて、ある現象を見るところに発生する概念です。原因とは、ある現象が、われわれが期待している通常のあり方から逸脱したとき、はじめて問うようなものなのです。P165 過去の出来事に興味を抱く態度全体が、じつはもはや取り返しのつかない意思行為をいかにとらえるかという態度に支えられています。過去の出来事の原因を問うのは、第一に、過去の出来事がもはや取り返しのつかないことを知っているからであり、第二に、それにもかかわらず「腹の虫がおさまらないか」からです。われわれは過去のとりかえしのつかない出来事に、現在何らかの「決着」をつけたいと願うのです。われわれがこうしたこと一切を今から遡って「なかったこと」にすることができるような存在者なら、人をいささかも恨まないような存在なら、そもそもいかなる原因を問うこともないということです。P169
Posted by
ねっとりとした語り口だ。哲学への愛憎なんだろうな。哲学というのは本質的な問、生と死とか、を取り扱ってもそこにいつまでの手続き論がぐるぐる回っているということなんだろうか。
Posted by
僕はこの本の著者、中島氏が好きである。氏は世間一般からみれば「社会人不適合者」なのだが、こういう人でないと哲学者にはなれないのかもしれない(氏の著作の一覧をAmazon等で参照されたい。とんでもないタイトルがずらりと並んでいます)。僕は小さいころから「死ぬ」ということがズッと気...
僕はこの本の著者、中島氏が好きである。氏は世間一般からみれば「社会人不適合者」なのだが、こういう人でないと哲学者にはなれないのかもしれない(氏の著作の一覧をAmazon等で参照されたい。とんでもないタイトルがずらりと並んでいます)。僕は小さいころから「死ぬ」ということがズッと気になって、25~28歳頃にこの「死」に対する恐怖心が異様に増して、それ以来不眠症気味で、睡眠薬なしでは眠れなくなってしまいました。 その当時、「死」を分析している『存在と時間』という本の存在を知り、同書に関する解説本等やらをたくさん読んで、その当時は「本来的な生を自覚している俺って、人とは違うんだな」なんて、若気の至りで思いあがっていたのですが、それでも「死」に対する恐怖心は拭えない。ハイデガーの「死の現存在分析」も「確かになぁそうだよな」と感心するんだけど、でも「死」に対する恐怖を上手く説明してくれなかった。そういう時に、中島氏の書いた「死」に対する恐怖心に関する記述を読み、僕が持っていた「死」に抱いていた漠然たる恐怖心をとても的確に表現してくれていたことに、とても感動した。「僕だけが怖いんじゃないんだ。死をこんなにも恐れている人が他にもいるんだ」と思うとそれだけでも安心できた。 「死」に対する恐怖に対する記述は、この本にも至るところに書いてあるし、氏の著作のほとんどにも書いてあるので参照してもらいたい。とにもかくにも「死」を契機にいわゆる哲学に興味を持ち、哲学関連本をいろいろと読んできたけど、哲学が究極の文系学問である以上、言葉遣いが難解であるのは必然的帰着だとは思う。それは解るんだけど、それでも一般の人が興味をもてる程度に解りやすく説明してもらいたい、という一定の読者層が向けの本の少なさたるや…。 そういう「哲学とは何か」「哲学書の読み方」「哲学者の生活」が、哲学者でない我々一般読者にも解るように説明してくれるのは、この中島氏の他に、竹田青嗣氏、西研氏、(ちょっと敷居は高いが)木田元氏が挙げられる。僕はこうした、解りやすく説明してくれる哲学者が好きで、著作が出版されれば無条件で購入する数少ない著者である。 哲学に興味がある、普通の生活に飽きた等の方々が、哲学入門書として読むには最適かもしれない。惜しむらくは、中島氏の著作を多く読んでいる(僕のような)人にとっては既知な部分が多いので、敢えて読むまでもないということです。もしこの本を読んで、「哲学って面白いな」と思えば、そこから先は多くの哲学者が書いた本を読む楽しみが増えるし、「よくわかんねぇな」と思えば、哲学に興味がなかったことがわかったという意味で有用だと思います。
Posted by
哲学とはどういった学問なのかを、思想や宗教、文学など誤解されやすいものとの対比の中で規定することを試みている。この著作だけでは哲学を知るにはもちろん不十分ですが、哲学の入門者は哲学史のテキストと併せて読むと理解が進むと思われます。
Posted by
「哲学は思想史ではない」っていう安心感を与えてくれた本。 中島義道はこれで知った。 すごく好きになった。
Posted by
オススメの理由 自分が直面していた死の概念ついての参考になったから 推薦者のページ ⇒http://booklog.jp/users/yasushirei
Posted by
中島義道さんの本は 基本的には好きなんだけど 今回はあまり はまれなかったなあ 一語一語が 頭の中で上滑りしていく感じ でも もしかしたら あたしの頭の中に 哲学用の回路が できあがっていないから かもしれない とりあえずは 簡単そうな 哲学ものを あんまり選ばずに さくさ...
中島義道さんの本は 基本的には好きなんだけど 今回はあまり はまれなかったなあ 一語一語が 頭の中で上滑りしていく感じ でも もしかしたら あたしの頭の中に 哲学用の回路が できあがっていないから かもしれない とりあえずは 簡単そうな 哲学ものを あんまり選ばずに さくさく読んで 回路を作ろうかなあ
Posted by
どのような哲学があるかを論じるものではない。哲学とはどういうものか、どういうものではないかを論じるものではない。特に混同されがちな思想と哲学の違いについて説明している。
Posted by
「哲学の教科書」というタイトルだけれど、哲学の入門書かと思ったら大間違い。ものすごくシニカルな哲学的思考の指南書。 哲学という特別なようで当たり前の「フィルター」を通して物事を捉え直した時、目の前にどんな世界が広がるか、そしてその世界のなんと豊かなことか! 活字を読むというより、...
「哲学の教科書」というタイトルだけれど、哲学の入門書かと思ったら大間違い。ものすごくシニカルな哲学的思考の指南書。 哲学という特別なようで当たり前の「フィルター」を通して物事を捉え直した時、目の前にどんな世界が広がるか、そしてその世界のなんと豊かなことか! 活字を読むというより、活字に引っ張られるようにして読み進めたこの本。世の中のあらゆることを全て当たり前に受け入れ、それらを前提として喜怒哀楽と共に生きる多くの人にぜひ読んでもらいたい。 あなたが自分だと思っているその「自分」を、何故にあなたは自分だといいきれるのですか?
Posted by
タイトルのまんま、『哲学』とは?と云う問いから、あらゆる『哲学的』な事柄が書かれている作品。 筆者の中島義道氏は、かなり虚無的なタイプの人間だと随所に感じられる。 個人的に、大好きな作品。 哲学が哲学たらしめるひとつのコタエを示してると思います。 また、読み返す時が来そう。
Posted by