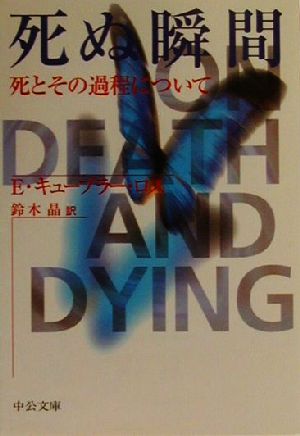死ぬ瞬間 の商品レビュー
勉強にはなったけど、やっぱり実際に現場に行ったり自分が死に直面しないとわからないことだらけだと思った。本だけでは。
Posted by
課題の本で今一生懸命読んでる本。 難しい。でも自分にとっても身近な死についての本だからもっとちゃんと読まなきゃ
Posted by
うーん。 何か微妙でした。 確かにこういうのも大事だと思うし、ターミナルケアはこんな感じなのかなぁ。 でも私が知りたいこととはちょこっと違う感じ。 何でだろ。 ほんとにこんな風に進むのかっていうのもあるし、このプロセスを経る十分な時間がない場合はどうなるのかってのもあ...
うーん。 何か微妙でした。 確かにこういうのも大事だと思うし、ターミナルケアはこんな感じなのかなぁ。 でも私が知りたいこととはちょこっと違う感じ。 何でだろ。 ほんとにこんな風に進むのかっていうのもあるし、このプロセスを経る十分な時間がない場合はどうなるのかってのもあるのかな。 あとは、もっと一般的な健康な人の死生観の方が興味あるからかも知れません。これは本当に死期が目に見えている人にフォーカスしてるからかな。 またこういうことについてじっくり考えたくなったら読み返してみたいと思います。 読みやすいことは読みやすかった
Posted by
末期患者との直接インタビューで得た、人間の死に至るまでの心の動きを5段階に分けて研究していった著書。 全体的に分かりやすい説明。会話(対談)の書き方がリアルで良い。けどシンプル(会話部分だけ)な為、抑揚のない風に聞こえる。そこが少し怖くて、ジョークもジョークに取れんかった。 次の...
末期患者との直接インタビューで得た、人間の死に至るまでの心の動きを5段階に分けて研究していった著書。 全体的に分かりやすい説明。会話(対談)の書き方がリアルで良い。けどシンプル(会話部分だけ)な為、抑揚のない風に聞こえる。そこが少し怖くて、ジョークもジョークに取れんかった。 次の段階に入ると、これまでについて軽く触れてくるから、忘れっぽい杏でも思い出せるとこが嬉しい。 医者−E・K・ロス(著者)は女性の為か、牧師よりも感受性豊かに見えたのが印象深い。良く言うと、1人の人間として患者と接している。まあ良いことなんだけど。 以前私は「”死”は分からないから恐ろしく感じるのだ」と言った。それもあるが、しかしもう一つ大切なのは「今、この状態から去る」という事実、だ。『今から去れば、愛していたものと別れることになるし、好きなことも出来ない。これは”死”を知らないから余計に不安になる』(P279) 『〜という仕方でもって、わたしたちは生きているうちから”死”と付き合っている。その意味で、わたしたちはやはり”死”を経験しているのだ。同じように、神に祈ったり神の存在を疑ったりという仕方で、わたしたちは”神”をも経験している』(P?) なぜか(やはり?)杏的には「うーん」だなあ。”死”の捉え方が違うんだろう。しかし14行目『経験している=なんとなく分かっている』なら、まあそうなのか、と思う。なあ。 『主観的、客観的という〜<わたしは黒で、向こう側に真理がある>』(P?) ?!どういう意味だろう?!もっと見方を変えた読み方をしなきゃ…。
Posted by
死に直面した時、人は何を考えるか。コミュニケーションに飢え切った臨死患者のケアをする為には、まず、自らの死の恐怖を取り去らなければならないと説く。著者が臨死患者のインタビューから学び取った、死の受容までの5段階、他。
Posted by
誰にも必ず訪れる死。未知の世界ゆえに恐怖感が先にたつ。人は死を前にした時、どういう過程をたどっていき、それを受け入れていくのか。人々の心理の移り変わりがとても興味深い。
Posted by
人の命の瀬戸際に臨む者として、死の受容までの五段階を何度も何度も読んで、深く考えた。この心理的段階は、死に限らずいろいろな局面で、同じような心理過程を示すものだと言うことを臨床経験から学んだ。医療従事者はもちろんのこと、現代を生きる全ての人に読んで欲しい本。精神科医であり、末期医...
人の命の瀬戸際に臨む者として、死の受容までの五段階を何度も何度も読んで、深く考えた。この心理的段階は、死に限らずいろいろな局面で、同じような心理過程を示すものだと言うことを臨床経験から学んだ。医療従事者はもちろんのこと、現代を生きる全ての人に読んで欲しい本。精神科医であり、末期医療を確立したエリザベス・キューブラー・ロス博士の世界的名著。
Posted by