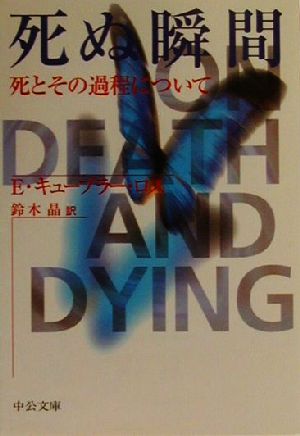死ぬ瞬間 の商品レビュー
有名なキューブラー・ロスの本。 受容までの5段階について患者へのインタビューも含めて掲載されている。 予想以上に厚い本だったが、感動的な場面も多く読んでいて涙ぐむことも。 他人の死や他人事としてでなく、自分のこととして死を考えるきっかけになった。
Posted by
著者は死に瀕した患者が至る過程には以下の5段階が存在すると述べている。 1否認と孤立 2怒り 3取引 4抑鬱 5受容 現代の日本社会では死について語ることはいまだタブー視されている。一方、超高齢社会の到来を迎え死は誰にも必ず訪れる身近なものとなり、私たちはその在り方...
著者は死に瀕した患者が至る過程には以下の5段階が存在すると述べている。 1否認と孤立 2怒り 3取引 4抑鬱 5受容 現代の日本社会では死について語ることはいまだタブー視されている。一方、超高齢社会の到来を迎え死は誰にも必ず訪れる身近なものとなり、私たちはその在り方について考える時が来ている。 患者の個別性を無視して死の受容過程のすべてを5段階にカテゴライズはできない。しかし、生と死の狭間で揺れ動く末期患者の心を受け止めより良いターミナルケアにつなげていくことは、同情や憐憫ではないこのような概念から始まるだろう。 死を目前に、人はどのような過程をたどっていきそれを受け入れていくのか。葛藤を繰り返しながら残された時間を生きる患者を支えるために医療者は必読すべき本だと思う。
Posted by
ターミナルケアの聖書。 人はいつか死ぬ。それを受容するまで、否認→怒り→取引→抑うつ→そして受容という過程を経る。やはり死ぬのは怖い。存在の否定。消失。いなくなる。さようなら。
Posted by
7年ぶりに読んだ。 久しぶりに読んでみて、学生時代にはなかった、あの患者、この患者という姿が思い出される。いるなーっていう、昔の自分と今の自分の考えの違いも感じられた。)1960年代にかかれたとは思えない秀逸な内容であり、どこにも古さを感じない。 マジで勉強になりました!! また...
7年ぶりに読んだ。 久しぶりに読んでみて、学生時代にはなかった、あの患者、この患者という姿が思い出される。いるなーっていう、昔の自分と今の自分の考えの違いも感じられた。)1960年代にかかれたとは思えない秀逸な内容であり、どこにも古さを感じない。 マジで勉強になりました!! また5年後、10年後くらいに読みたいです。
Posted by
私にとっては、感情を揺さぶられるというよりも、 落ち着いてじっくりとひとつひとつを「知る」ことができた本。 翻訳した本だから言い回しや使われてる単語が、本から受け取るこの感覚に影響してるのかなーどうだろ、分かんないけど。笑 「死は死にいたる過程が終わる瞬間に過ぎない」っていう...
私にとっては、感情を揺さぶられるというよりも、 落ち着いてじっくりとひとつひとつを「知る」ことができた本。 翻訳した本だから言い回しや使われてる単語が、本から受け取るこの感覚に影響してるのかなーどうだろ、分かんないけど。笑 「死は死にいたる過程が終わる瞬間に過ぎない」っていうフレーズがとても印象的だった。
Posted by
病者はどのように死を迎えるのか? いわゆる「障害受容」の5段階で有名なキュブラー・ロスの著書。 否認・怒り・取引・抑鬱・受容、というやつですな。 察するに画期的だったのは、DeathとDyingを分けた点にある。 死は単にポイントとして設定されている地点なのではなく、 ...
病者はどのように死を迎えるのか? いわゆる「障害受容」の5段階で有名なキュブラー・ロスの著書。 否認・怒り・取引・抑鬱・受容、というやつですな。 察するに画期的だったのは、DeathとDyingを分けた点にある。 死は単にポイントとして設定されている地点なのではなく、 死に至るまでの過程で見なくてはならない。 徐々に自由が利かなくなっていく身体や、痛み、 自分亡き後の家族への心配事、 医療従事者への不満などなど、 実際に「死」に到達するまでには、自分自身も変容するし、他者との関係も変わる。 「治す」ものとして病いを捉えるのではなく、いかにして(幸福に)この地点を迎えるか、 というのが著者の観点であり、この本のユニークなところだったのだろう、と思う。 ただし、疑問も多い。たとえば、この話の転用可能性がちょっと判らない。 本書に通底する、かつ看過できない点として「キリスト教」の影響がある。 死を迎えるにあたって、「信仰」は一つのキーワードになっている。 「患者 ええ、私は叔父が大好きでした。でも、私たちはだれかが死んでも泣くことはないんです。だって死んだら天国に行くんですもの。楽園に行くのなら、死んだ人にとっても幸せでしょう?」(p.338) という患者の語りは象徴的で、キリスト教における幸福な「死」という像が浮かぶ。 ここのところ、どうなのだろうなと思う。 「幸福なものとしての死」が一方にあって、 「身体的な苦痛、不安、しんどさ色々」が他方にある。 本編で引かれている患者の語りにおいても、 「死は怖くない(何故なら神様の下に行けるから)」けれど、 「医療の進歩や新薬の開発がギリギリで間に合って治ったらいいな」という 相反するような心境が多く示されていたのが興味深い。 こういう矛盾めいた部分が、人間の在り方としてとても面白いのだと思うし、 この本がかつて評価を受けた理由でもあるのだろうと思う。 しかしながら、結局のところ「幸福なものとしての死」が前提となっているのだとしたら、 宗教的背景の異なる人びとへの転用はおよそ適わないし、 そもそも「受容」という段階自体が宗教的な枠組みに基づいて、 トップダウン的に設定されたものに過ぎないのではないかという疑いが出てくる。 (著者は信仰の影響については留保しているけれど) 「死は幸福なのでどうぞ死んでください」という言説はなかなか怪しいものがある。 実は病者が死んで幸福なのは、いま生きている人びとなのではないかな。 少なくとも、有形無形の圧力の結果として生まれたであろう「受容」なる段階が、 病者本人の幸福なる過程を経て生じているのか、 そもそもそれくらいしか病者の行き場がないのか、我々には弁別ができないのだ。 というわけでこの本で言っていることは、「いかに生きるか」ではなく「いかに死ぬか」に 重点が置かれている。 これってどうなのよ?という思いを禁じえない一方で、 こういう枠組みを提示したからこそ、ここを土俵にして色々と議論がスタートしうる。 生をもっと肯定的に見るための方法論や、概念が蓄積されることもあるだろうし、 逆に死を推奨するような言説が生まれることもあるだろう。 全てはこうした先人の議論があってこその話で、少なくとも古典的な教養としては、 本書の価値が揺るぐことはないのではないかということを考える。 でもまぁ、そんなに誉める気にはならないというのが本音。
Posted by
医師である著者は、二百人あまりの重篤患者のインタビューを通じ、致命疾患の自覚から死への過程を「衝撃」→「否認」→「怒り」→「取引」→「抑鬱」→「受容」→「虚脱」としている。 これらの段階は重なることもあるし、また、同時に「希望」を持っている。 各段階での患者との対話内容を記載し、...
医師である著者は、二百人あまりの重篤患者のインタビューを通じ、致命疾患の自覚から死への過程を「衝撃」→「否認」→「怒り」→「取引」→「抑鬱」→「受容」→「虚脱」としている。 これらの段階は重なることもあるし、また、同時に「希望」を持っている。 各段階での患者との対話内容を記載し、患者の生活環境や歴史、宗教観を踏まえ、著者が解説している。 病院牧師がいるアメリカらしく、死への恐怖や疾患への運命を受け入れる姿勢は、信仰心と絡めて患者・医師ともに語る場面も多い。 患者のみならず、家族や医療スタッフにもスポットをあて、死に対するそれぞれの立場の心理的段階を教えてくれる。
Posted by
ともすればタブーと捉えられそうな内容ですが、衝撃的な題名に劣らぬ踏み込んだ内容の名著です。対話を通して真摯に患者と死に向き合った著者だからこそ書けた内容と感銘を受けます。死にあたって患者が通り抜ける過程は、死に関わらずとも人間が何かを受け入れるに応用できるものかと感じました。
Posted by
11.03.04読了。臨死体験/立花隆から。末期患者のインタビューを基調とした本。「臨死体験」と合わせてレビューを書くべき本。
Posted by
病院で死を間近に控えた人々へのインタビュー集。 それがどんな形でやってくるかには差があるが、 死というものの前では誰もが平等であり、 いつかはそれを迎えることになる。 死の宣告をされた当人や周りの人々は、 避けられない運命を誰かのせいにしたがり、 新しい治療法が発見されるとい...
病院で死を間近に控えた人々へのインタビュー集。 それがどんな形でやってくるかには差があるが、 死というものの前では誰もが平等であり、 いつかはそれを迎えることになる。 死の宣告をされた当人や周りの人々は、 避けられない運命を誰かのせいにしたがり、 新しい治療法が発見されるという藁にすがり、 文章では恐怖はありませんと言っていた人も、 顔が青ざめて明らかに恐怖を感じていたらしい。 繰り返すが誰もがいつかは死ぬことになるので、 自分や周りの人間がそうなった時のために、 心構えとして読んでおいて損は無い本である。
Posted by