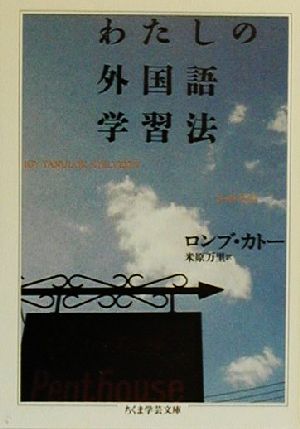わたしの外国語学習法 の商品レビュー
16カ国後を身に付け…
16カ国後を身に付けた著者が、タイトル通りその学習法を惜しみなく教えてくれる本。会話偏重の時代にあって、「読むことが大切」というアドバイス、どう受け取るかは読む人次第ですが、重要な示唆をいっぱいくれる本です。
文庫OFF
著者が25年間に16…
著者が25年間に16ヵ国語を身につけていく過程と秘訣を紹介。ただし、結構当たり前のことが多く、これで学習法を学び取るのは無理。
文庫OFF
良かった。学習法なのでメソッド本と思いきや1980年代に発行されてた本なだっけあって勉強法だけでなく学習に対する姿勢、なぜ外国語を学ぶのかという問いかけもあり、単なる外国語学習本にとどまらない含蓄があった。 また、文章がとても綺麗で読みやすい。何ヶ国語も学んできた著書だから言語隔...
良かった。学習法なのでメソッド本と思いきや1980年代に発行されてた本なだっけあって勉強法だけでなく学習に対する姿勢、なぜ外国語を学ぶのかという問いかけもあり、単なる外国語学習本にとどまらない含蓄があった。 また、文章がとても綺麗で読みやすい。何ヶ国語も学んできた著書だから言語隔たりなく平易かつ綺麗な文章が書けるのか、訳者のハンガリー語訳のレベルが高いのか分からないが、訳文だとしてもとても真似したい文章だった。
Posted by
文法とは、体系です。全身全霊を打ち込んである言語の文法を身につけた者、文法事項の暗記という難行を通過した者は、体系化され得る知識のあらゆる分野において体系化する能力を身につけたことになります。
Posted by
割と飛ばし読みだったがまあまあ面白かった。古いからか表現が遠回しな感じでわかりにくいところが多かった。 以下印象に残った点 ・外国語学習にはある程度の密度が必要。具体的には最低限週10〜12時間→1日1時間でも足りない! ・読書おすすめ。興味のある本を読もう。最初は精読しすぎて...
割と飛ばし読みだったがまあまあ面白かった。古いからか表現が遠回しな感じでわかりにくいところが多かった。 以下印象に残った点 ・外国語学習にはある程度の密度が必要。具体的には最低限週10〜12時間→1日1時間でも足りない! ・読書おすすめ。興味のある本を読もう。最初は精読しすぎて挫折せぬよう辞書に頼らず読み進む。 ・単語帳を自分の手で作ることをお勧めする。なんらかの行為と結びついているし、個性が出るから。 ・辞書を一時たりとも手放すな、そして常に手放せるようで無くてはダメ。
Posted by
おすすめ資料 第510回 「専攻(兼修)語学だけで良いですか?」 (2021.12.03) 実はロシア語と同じスラブ語派に属するブルガリア語。 専攻(兼修)語学だけでなく、同じ語派の言語も学ぶチャンスです! 16ヵ国語を習得したロンブ・カトーいわく、 「(略)人間による活動...
おすすめ資料 第510回 「専攻(兼修)語学だけで良いですか?」 (2021.12.03) 実はロシア語と同じスラブ語派に属するブルガリア語。 専攻(兼修)語学だけでなく、同じ語派の言語も学ぶチャンスです! 16ヵ国語を習得したロンブ・カトーいわく、 「(略)人間による活動の成果とか効力というものは、関心の度合と(略) 費やされたエネルギーの量いかんにかかっている」。 【神戸市外国語大学 図書館蔵書検索システム(所蔵詳細)へ】 https://library.kobe-cufs.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BK00132842 【神戸市外国語大学 図書館Twitterページへ】 https://twitter.com/KCUFS_lib/status/1468027478752956423
Posted by
母国ハンガリーにいながら16ヶ国語(日本語も含む)を習得した通訳者による外国語を学ぶ際の心得と、笑えて心励まされる体験記。 一読して連想したのは、この本の翻訳者である米原万里の『貞淑な醜女か不実な美女か』だった。訳者あとがきによると、若き米原さんは本書を訳したのがきっかけで通...
母国ハンガリーにいながら16ヶ国語(日本語も含む)を習得した通訳者による外国語を学ぶ際の心得と、笑えて心励まされる体験記。 一読して連想したのは、この本の翻訳者である米原万里の『貞淑な醜女か不実な美女か』だった。訳者あとがきによると、若き米原さんは本書を訳したのがきっかけで通訳を職業にすることにしたのだという。ユーモアのセンスなど本当によく似ているから、深く共感して入れ込んだのがわかる。 実践的な学習法として「本を読むこと」を挙げているのがこの本の特色。学習目標として「本を読めるようになろう」と掲げることはあっても、最初にまず本を、というのは少し珍しいと思う。カトーさんは、語彙は文脈のなかで覚えていくべきだし、文法は自力で発見していくことで身につくから本を読むのが一番だと言う。 カトーさんがこうした独学法を編みだしたのは1930年代の就職難のせいだった。独学で英語教師となり(!)、終戦後は連合国軍統制委員会の事務局という他言語を学ぶにうってつけの仕事に就き、のちに通訳者となった。だが「外国語こそが、下手に身につけても無駄に終わらない唯一のもの」という信念を読むだに、仕事を求める以上に新しい文化をその国の言葉で楽しむことが大好きだったのだろう。 終わりのほうでは通訳という仕事、特に同時通訳の楽しさと過酷さに触れるが、米原さんが魅力を感じた気持ちがわかるくらい、ここで披露される経験談が面白い。仕事中は重量挙げの選手がバーベルを持ち上げる瞬間を超える脈拍数にもなるという同時通訳を楽しめるバイタリティには圧倒されるが、それをユーモア交じりにカラッと語る彼女のスタンスに、たしかに憧れる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
外国語習得には近道や魔法はないということが書かれている。 母国語はハンガリー(洪)語、露英仏独洪はどの組み合わせでも自由に通訳作業ができる、イタリア語、スペイン語、日本語、中国語、ポーランド語は半日準備が必要、残る6か国語は翻訳できる、という著者の学習法が書かれている。 著者は特に語学の才能はなく、関心の度合い、関心の対象を実現するために費やされたエネルギー量にかかっていると断言。 「勤勉に、週二~三回、あるいはそれ以上の周期を守って外国語を学習し続けることによって、四~五年後には、自分の要求水準を満たすほどまでに到達することは可能です。」(P43) 著者の言うところの語学力は 1、高等発言の理解力 2、文章の理解力 3、口頭発言能力 4、文章力 である。 著者が勧めるのは 読書…好きな本を読む、あらすじ→念入りにの順番で読む、 発音…架空の語(nonsense syllables)で訓練する、ラジオなどを聞き入り、単語や文章の旋律を何度も聞く、単語は単独ではなく反語のペアや動詞と名詞の組み合わせなどで覚える、 単語…すでに知っている表現や概念と連結させる、個性を発揮した単語帳を作る 自分と独国の人による教科書を用いる、辞書と参考書を用意する、外国語で独り言を言う すでにやったことがある勉強法が多く、それでも私の英語が抜けていくのは日々の鍛錬が足りないからでしょう…。
Posted by
カバーに、「14のヨーロッパ系言語と中国語、日本語を、ほとんど自国を出ることなく、純粋に学習という形で身につけてしまった女性の外国語習得術」とあれば、どのようにしてそんなことを可能にしたのだろうか?という興味が湧くのは自然な成り行きであろう。 でも、いわゆる外国語を習得するための...
カバーに、「14のヨーロッパ系言語と中国語、日本語を、ほとんど自国を出ることなく、純粋に学習という形で身につけてしまった女性の外国語習得術」とあれば、どのようにしてそんなことを可能にしたのだろうか?という興味が湧くのは自然な成り行きであろう。 でも、いわゆる外国語を習得するためのノウハウ本の類ではない。書かれているのは、筆者がほとんど独学によってどのように外国語を習得していったのか、その学習を支えていたものは何だったのか、という外国語学習の遍歴である。 読後、自分でもぜひ挑戦してみたいという気持ちにさせられた方法がいくつかあった。おそらく、これから外国語の学習に取り組もうと思っているひとならば、必ずいくつかの試みたい方法を発見することであろう。
Posted by
著者は、海外暮らしなどの人生上の偶然のめぐり合わせのおかげで複数言語ができるようになった多言語所有者ではなく、ほとんど自国を出ることなく言語を身につけた外国語習得者である。 「芸術を除くあらゆる人間による活動の成果とか効力とかというものは、関心の度合いと、この関心の対象を実現す...
著者は、海外暮らしなどの人生上の偶然のめぐり合わせのおかげで複数言語ができるようになった多言語所有者ではなく、ほとんど自国を出ることなく言語を身につけた外国語習得者である。 「芸術を除くあらゆる人間による活動の成果とか効力とかというものは、関心の度合いと、この関心の対象を実現するために費やしたエネルギーの量いかんにかかっているのです。」 語学であれ、何であれ、そこに費やすエネルギーの量があれば、実現可能であるのだと。 著者は、私たちを勇気づけ、外国語学習に前向きな楽観主義に感染させてくれる。 語学学習に挫折した人は、この本を読めば学習熱が再燃してくるはず!
Posted by