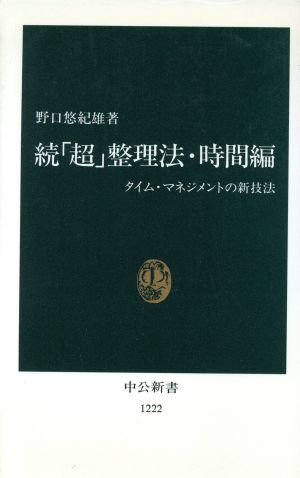続「超」整理法・時間編 の商品レビュー
この後めちゃくちゃfaxした 95年の本だけあって、生かせることも古いこともあった。 ただ、学ぶところは多く単体でも生かせそう。 もう少し未来になれば、逆にこの本のアナログで行っていた事がインタフェイスそのままデジタルで出来る様になるかも。
Posted by
序章 時間との戦い 第1章 時間を見る技術 第2章 スケジューリングの技術 第3章 連絡時間の無駄をなくす技術 第4章 組織内コミュニケーション革命 第5章 押し出しファイリングと時間管理 第6章 時間を増やす技術 第7章 人間の認知・記憶能力とタイム・マネジメント 終章 他人の...
序章 時間との戦い 第1章 時間を見る技術 第2章 スケジューリングの技術 第3章 連絡時間の無駄をなくす技術 第4章 組織内コミュニケーション革命 第5章 押し出しファイリングと時間管理 第6章 時間を増やす技術 第7章 人間の認知・記憶能力とタイム・マネジメント 終章 他人の時間を大切にしよう
Posted by
もう10年も前の本なので、内容的には古くなっている部分もありますが、基本的には今でも通用するハウツウ書です。見方によっては、携帯電話の氾濫やスパムメールの問題を、予言している書とも言えるかなあ。 P.224 これを大胆かつ大雑把に一般化すれば、スペシャリストよりジェネラリス...
もう10年も前の本なので、内容的には古くなっている部分もありますが、基本的には今でも通用するハウツウ書です。見方によっては、携帯電話の氾濫やスパムメールの問題を、予言している書とも言えるかなあ。 P.224 これを大胆かつ大雑把に一般化すれば、スペシャリストよりジェネラリストのほうがよいということである。
Posted by
この領域の本をよむとき、自らを制するために書かれたか、他との競争を制するためのものかを考え、せいぜい前者にかぎると考えている. 時間の使い方.多くの人が課題にしている.いろいろあるが、「終章 他人の時間を大事にしよう」がおすすめ. ほぼ、ここを読むと、著者の主張点を解する...
この領域の本をよむとき、自らを制するために書かれたか、他との競争を制するためのものかを考え、せいぜい前者にかぎると考えている. 時間の使い方.多くの人が課題にしている.いろいろあるが、「終章 他人の時間を大事にしよう」がおすすめ. ほぼ、ここを読むと、著者の主張点を解するような気がする. 「手帳に折りたたみ式スケジュール表」「中断シンドローム」「会議から文書へ」「マジカルナムバー・オブ・セブン」. 新用語がならぶ.電話がくると思考停止、もとに戻すまでに時間を要する.それが『中断シンドローム」. 人間、七項目しか覚えられない.かくて七曜日の習慣. なるほど、なるほど.著書を通じた提案のうち、いくつ取り組んでいる、か.そこの検証が読んでいて、楽しい. 中心街をあるき、立ち寄った古書店で3冊100円のうちの一書.著者にはまことに気の毒なことをするが、悪くない買い物.
Posted by
著者の思いの一つ。「現実世界で使えるノウハウが欲しい」 確か一作目でも書いてましたが「ぐうたらな自分に実践出来てこそ、本当に優れた整理法だ」みたいなことも。賛成です。労少なくして効果多し。それ理想。
Posted by
仕事を効率的に進めるためにと思い、再読。タイムマネジメントの極意は、不確実性をいかに減らすかということのようだ。個人的には、仕事が中断しない時間をいかに作るかということと、8割原則で次の仕事に向かうということが重要なんだということに気づかされた。典型的なハウツー本だが、経済学的な...
仕事を効率的に進めるためにと思い、再読。タイムマネジメントの極意は、不確実性をいかに減らすかということのようだ。個人的には、仕事が中断しない時間をいかに作るかということと、8割原則で次の仕事に向かうということが重要なんだということに気づかされた。典型的なハウツー本だが、経済学的な考え方に根ざしている点がミソ。1995年の本なので内容が古く感じられる箇所もある(例えばFAXの活用方法を説明しているところなど)が、「合理的なマネジメント」なるものを考える上では役に立つ。 ★比較優位説と不確実性に関する以下の記述は、示唆に富む。 「分業による専門家が望ましいというのは、不確実性がさほど大きくない場合の結論である。不確実性が十分大きい場合には、ミラーが指摘したように、「変化する状況への適応」という目的が優先する。国際貿易理論における「比較生産費の理論」(各国は、あらゆる生産物を自国で生産するのではなく、最も得意とする産業に特化し、国際貿易を行なうべきである)が現実に影響力を持たないのは、このためだ。」(p.225) ※ジョージ・A・ミラーは、1956年に"The Magical Number of Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information," The Psychological Review, 63(2), pp.81-97. を発表した心理学者。
Posted by
超整理手帳が自分が求める手帳に最も近いので、その人の時間管理術を知りたくて読んだ。が、内容がやや古くそのまま活用できるノウハウが思ったより少なかった。全体的な考え方としては時間管理に非常に役立つ。
Posted by
超整理法の作者による、時間術の本。 本の前半は時間どう把握するかということについてよく書かれている。朝4時起きするなどの方法は著者は否定する。 なぜなら、人間の怠惰さを無視しているからだと。 ただ、中盤からは実践的な内容となるけと、1995年に書かれた今から20年ほど前の本...
超整理法の作者による、時間術の本。 本の前半は時間どう把握するかということについてよく書かれている。朝4時起きするなどの方法は著者は否定する。 なぜなら、人間の怠惰さを無視しているからだと。 ただ、中盤からは実践的な内容となるけと、1995年に書かれた今から20年ほど前の本だから、この本に書かれた解決法や作者の苦闘はパソコンやスマホによって解決されてしまっている部分が多くて参考にならない。 仕事の進め方の進歩の歴史として読むなら、または、FAXで連絡していたよねー的なあるあるネタとして読むならおもしろくよめるとおもう。 でも、どれだけ技術が進んでも、ダブルブッキングや重要なことを後回しにしてしまうなどの、時間の悩みについては20年前もいまも変わらないのだあなぁ、と思った。 「将来の時間を見通すには、すぎて行った時間を、日にちを考えればいい。一週間先の予定があるとまだ時間があると思いがちだが、一週間前にあった予定を思い出すと、もうこんなに時間が経っていると思ってしまう。その時間感覚を将来にも当てはめれば、うまくいく」というようなことが書いてあって、なるほどなぁ、と思った。 時間がたてども、人の悩みは変わらず、かな。
Posted by
最近読んでいる本は、雑誌類が多く、 まともに読むものが少ない。 なにか、物足りないものを感じているが、 現在は、頭の中が、パソコンを基本としているために このような事態となっている。 新しい時代がやってきていることは確かである。 阪神大震災の中で、生まれた、 人間としてのいろい...
最近読んでいる本は、雑誌類が多く、 まともに読むものが少ない。 なにか、物足りないものを感じているが、 現在は、頭の中が、パソコンを基本としているために このような事態となっている。 新しい時代がやってきていることは確かである。 阪神大震災の中で、生まれた、 人間としてのいろいろな価値観は、 今後日本の精神史に大きな役割を果たすであろう。 築き上げてきたものが、 自然の力にあっけなく、破壊されてしまう。 その中で、けなげに立ち上がっていく日本人の姿は、 なににもかえがたい重要なものになると思われる。 その中で、やはり、情報がいかに 重要なものであるかということは、 いうものではないが、しかし、 今後大きな発展を遂げていくことは確かである。 このことに対する取り組みと、 ビジネスに変えていく力が要求されている。 農業の分野でおこっていることは、 確実にこのような変化であろう。 超整理法の時間編を読むことによって、 やはり新しい刺激をうけた。 時間に対する使い方というよりも、 生活スタイルそのものに対する取り組み みたいなものを表示している。 時代が、変化していることが背景にある。 ①仕事の多様化と複雑化。 ②たくさんの人との共同の仕事が多くなり、不確実性の増大 ③仕事のサイクルが長くなり、同時並行的に進めるようになった。 提案されている要点は、実に簡単なものであり、シンプルである。 ダイエーの文書に simple is best. one page is the best. とかかれていたが、たしかにそのような状況が生まれている。 タイムマネジメントの基本として、 (1)スケジュール表を一覧性のあるものにすること。 デジタルから、アナログ化にすすめていく。 一目でわかるようにする。 スケジュール管理をする。 「まぎわシンドローム」 (2)連絡は、文書で行うこと。口頭から、メモに。 「中断シンドローム」から、 解放されるためには、FAXを使用する。 (3)問題を、どのような現象であり、その解決を急ぐかにある。 それの「表示」について考え提案する。 (4)時間を、節約する。 待ち時間を活用する。時間をとられない。 国富論 「分業は市場の大きさによって規定される。」 The division of labor is limited by the extent of the market. この意見は、きわめて重要である。 このことをきちんと理解しないと、 前に進まないことは、確実である。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本書は、「超」整理法の続編としてタイムマネジメントに焦点をあてて、スケジューリングの方法、時間節約・時間増大のノウハウを他の文献や著者自身の経験を通して紹介している。 スケジューリング表は時間を直感的にわかるように数週間、数か月間先までを一覧表にして把握することにより手帳を受動的な備忘録からスケジュール管理の道具へと進化させ、仕事の重要度に応じた時間配分、不確実性への対処などを適切に行うこと、また、連絡の手段として文書を活用し、FAXやEメールに切り替えることによって、連絡にかかわる無駄な時間を節約できると主張している。
Posted by