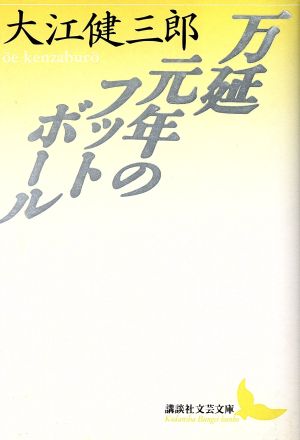万延元年のフットボール の商品レビュー
すごい作品です。短編…
すごい作品です。短編以外では、個人的にはこれがベストです。
文庫OFF
純文学だから、と敬遠…
純文学だから、と敬遠している人もぜひ読んで欲しい。理屈ぬきに面白い!クセのある文章ですが、慣れてくるとハマリます。
文庫OFF
なんといっても、使わ…
なんといっても、使われている言葉が難しい!理解しながら読むのに時間がかかりました。哀しい兄弟愛がうまく描かれています。
文庫OFF
文学史に残る名作!!…
文学史に残る名作!!時代をうまく捉えた一作!!
文庫OFF
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
Jリーグ観るのが好きなのでタイトルが気になって読んだ。この作品においてフットボールとは念仏踊りであり、念仏踊りは歴史の再現なのね。Jリーグは差別に対して毅然と対応してくれるから、こうした懸念を払ってくれる。ありがたい。それはさておき、読むのに体力が要るけど次々と怪人が出てくるから何とか読めた。めちゃめちゃ面白かったのでみんな読んでここに感想を流してほしい。 アンニュイな語り手である蜜が、弟が恥辱に塗れて死ぬまで正論で殴り続けるところが好きだった。英雄になりたい欲を潰すことにかけては自分で「悪意の迫撃砲」とか言うレベルで容赦がない。で、終盤に100年前の一揆について重要な思い違いが判明して、一揆の首謀者だった曾祖父の弟諸共弟のこともまるごと再評価して敗北感を感じたりしちゃうんだけど、そこはもう大江健三郎あるあるの森で生まれ変わるターンに入っているからそうなっちゃっただけで読んだ限り弟が「幼稚なげす」であることは揺るがないよな…となるあたりも良い。冒険が必要→アフリカ行く、って雑さも良かった。 半世紀前の作品だけれど、ヒロイックに語り直された歴史に煽動される閉塞感を抱えた人々、というのはなかなか現代社会でも心当たりがあるようにも思える。とはいえそういう難しいことを気にせずみんな読んでほしい。
Posted by
ノーベル賞作家・大江健三郎の骨太な長編。安保闘争に敗北し「政治の時代」が終わりを迎えた鬱屈した時代感の中で、性や障害、記憶、歴史といった実存主義的なモチーフが次々に繰り出され、グロテスクで仄暗い小説世界が形成される。 全編を通じて飽きさせないが、中でも第1章が出色。一文が極端に...
ノーベル賞作家・大江健三郎の骨太な長編。安保闘争に敗北し「政治の時代」が終わりを迎えた鬱屈した時代感の中で、性や障害、記憶、歴史といった実存主義的なモチーフが次々に繰り出され、グロテスクで仄暗い小説世界が形成される。 全編を通じて飽きさせないが、中でも第1章が出色。一文が極端に長く、比喩も多用されており到底スラスラと読める代物ではない。「僕は、自分の内部の夜の森を見張る斥候をひとり傭ったのであり、そのようにして僕は、僕自身の内側を観察する訓練を、みずからに課したのである。」(P.9)といった具合に(これは主人公の失明した片目について触れた箇所である)、難解でありつつセンチメンタルな格調高さを湛えた文章に、話の筋の面白さとは全く異なる次元の、小説を読むという体験の素晴らしさを教えられた。 物語の結末は率直に言って、ぼくの想像力を超えた難解なものだった。主人公の選択が輝かしい人間性の恢復へと続くのか、それとも惨たらしい悔恨と逃避を意味するのかはまだ若く未熟なぼくには判断がつかない。 大江自身は後書きで、この作品が彼自身にとっても、彼と同時代の読者にとっても一つの「乗越え点」、すなわち作風の転換点であり、同時に今までの読者をある種ふるいにかけた作品であったと語っている。 ぼく自身がこの作品を自分なりに咀嚼してその意味の一つでも掬い上げることができたのか、あるいはその難解さにただ翻弄されつつ、ファッションとして消費してしまったに過ぎないのかは定かでないが、少なくとも大江文学という一つの「乗越え点」を見つけることはできた。今はそれだけで十分だろう。
Posted by
一種通俗的な物語 ショッキングと希望がなひまぜになって、冒頭からおよそ言葉の洪水の暴力がなだれこんでくる。自殺した友人のイメージがショッキングで、同時に惹きつけられる。 四国の山奥を卑下して大丈夫なのかと思ったほどだが、ある種普遍的な話だ。神話とからめて語る人が多いが、むしろ...
一種通俗的な物語 ショッキングと希望がなひまぜになって、冒頭からおよそ言葉の洪水の暴力がなだれこんでくる。自殺した友人のイメージがショッキングで、同時に惹きつけられる。 四国の山奥を卑下して大丈夫なのかと思ったほどだが、ある種普遍的な話だ。神話とからめて語る人が多いが、むしろ昔の一揆との連続性を蘇らせる現代の騒動を描いたもの。鷹四のやうな人間も、いくぶん誇張されてゐるとはいへ、ゐないわけではない。蓮實重彦や小川榮太郎が書いてゐたが、部分的には通俗的でもある。 やはり一種難儀なのはながながしい主人公の独白で、興味の持続を断念するひとも多いはず。動物や自然を用ゐた比喩や、川流れのエピソードから、大江の子供の頃の実体験が混じってゐるとわかる。 しかし、個人的にはこのやうなフィクションめいたものよりも、中期後期以降の大江の、個人的な話題のほうが個人的な私は惹かれる。「静かな生活」や「河馬に噛まれる」などである。大量の独白は実在感を得ない。
Posted by
万延元年つながりで読む。 独特のグロテスクな暗さの中に、著者の経験、苦悩とそこからの希望が見える。 しかし疲れる。
Posted by
再読。文体が合うかどうかでだいぶ印象が変わる小説だと思います。長く、やりすぎなほど長く続くセンテンスと、美しい比喩表現、そして登場人物の「翻訳口調」。どこを切り取っても常人では成し得ない高い技巧が凝らされており、読んでいて目眩がするほどです。特に1章にあたる部分ではその独特の文体...
再読。文体が合うかどうかでだいぶ印象が変わる小説だと思います。長く、やりすぎなほど長く続くセンテンスと、美しい比喩表現、そして登場人物の「翻訳口調」。どこを切り取っても常人では成し得ない高い技巧が凝らされており、読んでいて目眩がするほどです。特に1章にあたる部分ではその独特の文体が濃厚に発揮されていて、とぐろを巻くような言葉の連なりに酩酊感を覚えててしまう。2章以降はある一定のテンポが生まれ、上記した「翻訳口調」という部分が強調されてくるのですが、私この翻訳口調すごくすきなんですよねー。話の内容はまさしく”文学”って感じなのに、この口調のせいで妙な軽さ、そして奇妙さが備わっているのです。まるで邦画を観ながら翻訳された字幕を読んでいるとでもいうか、なんというか。中上健次のどろくさい文体とも、村上春樹の詩的(すぎる)な文体とも違う、この人にしか出せない「音」が文体から聞こえてくる気がします。 舞台となるのは1960年代の四国。谷間の村に妻と弟とともに訪れた”密三郎”を語り手として、この村で起きた一揆について綴られていく。学生運動に対する内省、戦後からの復興、朝鮮人、天皇、地方に浸透していくスーパーマーケット……。時代の転換点を見極め、作者自身が何事かに”ケリ”を付けるために書かれた本作は、熱量、完成度、文章の美しさ、読み物としての純粋な面白さ、すべてが高水準であり、そりゃノーベル賞だって取っちゃうよなあと感じます。 むかし読んだときはひどく暴力的で凄惨な展開が目に付いたのだけど、再読してみるとむしろ”密三郎”の思考の流れとか、”鷹四”との会話とか、文体の面白さとか、そういう内面的な方に魅力を感じたな。解像度があがるというのはこういうことなのだろうか。作者の真剣さが小説そのものに、言葉そのものに宿っており、読む側が真剣に読めば、それだけ多くのものが返ってくる。そんな豊潤さ。じっくり時間をかけて読み、頭がくたくたになりながらも、読み終わったときはしあわせな気持ちになっていた。これは神話ですね。現代を舞台とした神話。土俗的で政治的でありながら崇高さも持ち合わせているすごいやつ。こういうのを世界文学というのでしょう。 ちなみに私、大江健三郎の本はこれ一冊しか読んだことがなかったのですが、本書を再読してこれから他の本も読んでいきたいなーと思いました。一生かけて付き合っていってもいいと思える作者な気がするので。
Posted by
難しくて断念。500ページくらいあります。読むの時間かかると思うので、図書館で借りるより、買った方がいいかもです。
Posted by