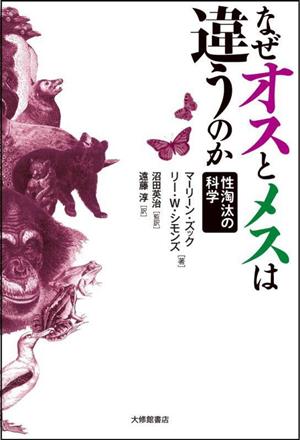- 書籍
- 書籍
なぜオスとメスは違うのか
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
なぜオスとメスは違うのか
¥1,980
在庫あり
商品レビュー
3.7
3件のお客様レビュー
性的対立に興味をもって読み始めた。オスとメスが、自分自身の子孫をより多く残すために互いと対立するという話だ。メスに尽くすことが得策だと考える種もあれば、オスに尽くすことが良いと考える種もある。一方で、メスを弱らせてでも自分以外の遺伝子を受け入れさせない、あるいは、オスを騙して他の...
性的対立に興味をもって読み始めた。オスとメスが、自分自身の子孫をより多く残すために互いと対立するという話だ。メスに尽くすことが得策だと考える種もあれば、オスに尽くすことが良いと考える種もある。一方で、メスを弱らせてでも自分以外の遺伝子を受け入れさせない、あるいは、オスを騙して他のオスとの子供を育てさせる。このように種によって戦略は多様なのだが、人間単体で考えても、戦略の多様性があるような気がする。 異性と出会いにくい種の場合、転換して単為生殖ができるようにしておく事が有効であり、普段はメスだが、オスの機能も果たせる種がいる。この方が、遺伝子を維持していけるのだが、本来は有性生殖が望ましいという考えが根底にある。つまり、何が望ましいかというベストな方式、理想はあるが、種のサイズ感や環境によってそれが果たせないという状況がある。そう考えると、全くの主観だが、恐らくは、<単為生殖 → 有性生殖 → 性転換種 → ハーレム → 一夫一妻>というように、性的対立が平等化されるのが最終的な理想形という気がする。なぜなら、環境による学習が可能な高度な知能を得る個体の場合、その子孫に対して安定した環境を提供するには、一夫一妻が最も効率が良いからだ(時に、非効率になる個体もいるが)。 以下、これにも関連して面白いと思った内容。 ― 一般には選り好みをする性はメスだが、雌雄両方による配偶者選択も珍しくはない。たとえば、ジュリアン・ハクスリーが研究したカンムリカイツブリでは、雌雄とも頭部に同じような極端に発達した装飾を持っており、互いに相手の動きをそっくり写すようにして複雑な求愛ダンスを踊る(図2)。同じことは、アホウドリやペンギン、ウミスズメの仲間など多数の鳥類にあてはまる。雌雄両方による配偶者選択は、他に魚類やカエル、昆虫にさえある。雌雄両方による配偶者選択が起こるのは、パートナーの双方が配偶者を選好することで利益を得られる場合と予想される。 ― 多くのキリギリス類では、オスが交尾の際、メスの餌になる栄養豊富な物質を分泌して精子とともにメスに与える、婚姻贈呈と呼ばれる行動が見られる(図2)。メスは交尾中か交尾後にオスの贈り物を食べ、中に含まれるタンパク質などの栄養素により、卵生産や寿命が増加する恩恵を得ている。オスが贈呈する分泌物は、オスの体重の3分の1あるいはそれを超える重さがあり、生産に非常に多くのエネルギーを費する。ヒトの男性が性行為のたびに、15キロを超える何かを生産しなくてはならないと想像すると、これがどれだけのことかわかるはずだ。贈り物に高いコストがかかるということは、オスは何度も連続して交尾することができないことになる。再び贈り物の準備をするのに、時間とエネルギーを要するためだ。このような状況でオスにとって利益になるのは、通常のようにメスの獲得をめぐって競争をすることではなく、交尾するメスを選り好みすることである。そして実際に、多くの種のキリギリスでは、オスが交尾の相手として最も太ったメス、つまり、多くの卵を持ち、オスに多くの子をもたらしそうなメスを選ぶ。 ― オスがメスの産む子に占める自分の子の割合を高めるには、メスがライバルオスと交尾する機会を減らす方法や、自分の精子を受精場所の近くに送り込んで受精プロセスに介入する方法、または、送り込む精子の量を増やして、受精の確率を自分に有利にする方法がある。一方でメスは、オスの受精競争の場として受動的な立場に甘んじているかと言うと、そうではないとパーカーは考えていた。メスはより魅力的なオスの精子と自分の卵を受精させるため、精子の受け入れや貯蔵、使用に差をつけることが考えられる。つまり、交尾の後もメスの選り好みは継続する可能性がある。
Posted by 
雌雄で外見が異なる種である性的二型について、特に議論している。 端的に言えば男女の騙しあいについて例を挙げて説明しているが、メスがオスを選考する場合に限らず逆のパターンも挙げているし、特に後半に行くほど過激な例も挙げている。 また交尾後性淘汰として、交尾後の精子による競争による淘...
雌雄で外見が異なる種である性的二型について、特に議論している。 端的に言えば男女の騙しあいについて例を挙げて説明しているが、メスがオスを選考する場合に限らず逆のパターンも挙げているし、特に後半に行くほど過激な例も挙げている。 また交尾後性淘汰として、交尾後の精子による競争による淘汰があり、そのために性器や精子についても特性が出ていること、ただ具体的な研究は進んでいないことを記載している。 また種の分化における性淘汰の役割も議論している、そもそもなぜ性的な選考があるかという議論については、集団内の遺伝子の異常を排除する機能があるとしている。 意図的に設けた環境下での比較研究により結果を得られていること、また偏った種だけ見て全体を理解した気にならない方が良いことを述べていて、客観的な研究としてよく記載できているように思える。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
一夫一妻と考えられている鳥でも、巣の中に違う父親のヒナがいる。鳥類の90%。他のオスと交尾しておけば繁殖の保険になる。 一夫多妻の種では、オスの争いでメスと極端な違いがみられる。メスの繁殖成功度は低くなる。 一妻多夫は珍しい配偶システム。メスはオスに子供を預ける。手がかからない早成性の鳥が多い。近年、意外に多いことがわかり、一妻多夫革命と言われている。 同じつがいが続くほど繁殖成功度が上がる。子育てにオスの協力が必要なほど、一夫一妻制になる。哺乳類では少ない。 狩猟者は、大型のオスを標的にするが、一夫一妻だとオスがいなくなると子育てができなくなる。オスの消失は家族の消失につながる。オスだけを殺すほうが、オスメスを殺すより個体数の衰退につながる。野生動物の保護につながる。 メスを引き付けるための進化は、行き過ぎると捕食の危険性を高めて有害になる。 ヒトの配偶者選択は男女双方による淘汰圧があった。先行性は幼少期から現れる。文化によって作られたものではない。 鳥類のメスは、オスの精子を体内に貯蔵していて、複数回交尾のあと、精子間競争が起きることで淘汰が進む。 精子の数が多いのは、精子競争の結果。 ボノボは、複数のオスと交尾するので激しい精子競争が起こり、その結果精巣サイズは大きい。 交尾後の性淘汰が起きる場合には、オスは精子生産に投資するよう進化する。 トンボ類は、前のオスの精子を掻き出してから交尾する。自分の精子を守るため、受精までメスのそばにとどまる。配偶者防衛と呼ばれる行動。 性的対立=オスとメスの繁殖上の要望が違う場合にそれが対立すること。 動物の性行動は多様なもの。動物を例にとりヒトが本来どおう行動するべきかを語ることはできない。 キリギリスのオスは自分の体重の1/3にあたる栄養価が高い贈り物をして交尾する。限られたオスしか交尾できない。 性淘汰は多数の生き物を観察しないと理解できない。性淘汰は交尾後も終わらない。
Posted by