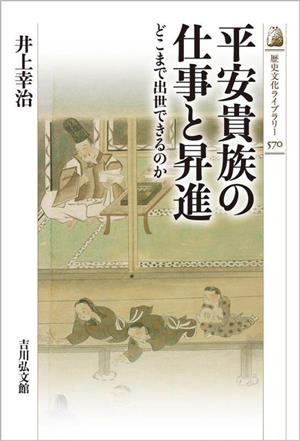- 書籍
- 書籍
平安貴族の仕事と昇進
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
平安貴族の仕事と昇進
¥1,870
在庫あり
商品レビュー
4
6件のお客様レビュー
1. 平安時代の公卿社会の構造 - 平安時代の公卿(貴族)は、複雑な社会制度の中で特定の役割を持ち、年中行事や政務を通じて政治に関与していた。 - 公卿は、国会議員や中央省庁の幹部職員に類似した役割を果たし、政治的な影響力を保持していた。 2. 年中行事とその重要性 - 年中行...
1. 平安時代の公卿社会の構造 - 平安時代の公卿(貴族)は、複雑な社会制度の中で特定の役割を持ち、年中行事や政務を通じて政治に関与していた。 - 公卿は、国会議員や中央省庁の幹部職員に類似した役割を果たし、政治的な影響力を保持していた。 2. 年中行事とその重要性 - 年中行事は公卿にとって最も重要な職務であり、政治そのものと見なされていた。 - これらの行事は、形式的なものであったが、実際には政治的な決定や権力の象徴として機能していた。 3. 平安貴族の昇進と職務 - 昇進の過程は複雑であり、平安貴族たちは多様な官職を経て昇進していった。 - 官職には、六位外記や六位史などがあり、これらのポストを経て受領任官に至る流れが存在した。 4. 政務(申文)の実施 - 政務は、外記庁で行われ、上卿が中心となって申請文類に対する判断を下していた。 - 各公卿や大夫は、政務における役割を持ち、業務を円滑に進めるために協力していた。 5. 除目の意義 - 除目は、平安貴族にとって重要な行事であり、官職の任命や昇進が行われた。 - 参加者は、役職や地位に応じた期待を持って行事に臨んでいた。 6. 平安貴族の日常生活 - 公卿たちは、日々の生活の中で多くの業務をこなし、忙しい日常を送っていた。 - 彼らは、内裏や寺社行事に参加することで、社会的な役割を果たしていた。 7. 社会的・文化的背景 - 平安時代の貴族は、学問や芸能に秀でた者が多く、社会的地位を高める手段としてこれらを重視していた。 - 特に、和歌や音楽などの芸能は、貴族社会において重要な役割を果たしていた。 8. 平安貴族の変遷 - 承久の乱以降、平安貴族の地位や役割に変化が見られ、徐々に武士の影響が強まっていった。 - これにより、貴族たちの生活や職務も変化し、歴史的な転換点となった。 9. 結論 - 本書は、平安時代の公卿社会の複雑さと、彼らがどのようにして社会に影響を与えたかを詳細に解説している。 - 年中行事や政務を通じて、平安貴族たちの生活や昇進の過程を示すことで、当時の社会構造を理解する手助けとなる。
Posted by 
公卿、諸太夫、侍に分けて、平安貴族の仕事の仕方と昇進ルートを記述。 ①申文が出される。②先例を調べ対応案を作成する。③関白等関係者に根回しする。③続文(つぎぶみ)ー案と先例を整理した文書ーを作成する。④結政(かたなし)事務方で文書の確認をする。⑤陣の(定めでの)申文等(閣議)で上...
公卿、諸太夫、侍に分けて、平安貴族の仕事の仕方と昇進ルートを記述。 ①申文が出される。②先例を調べ対応案を作成する。③関白等関係者に根回しする。③続文(つぎぶみ)ー案と先例を整理した文書ーを作成する。④結政(かたなし)事務方で文書の確認をする。⑤陣の(定めでの)申文等(閣議)で上卿の審議を受ける。⑥天皇による決済。⓻文書を施行する。という現代と行政文書の処理の仕方である。陣の申文には公卿は小人数しか出ず、あらかじめ内諾している公卿は出ないことが多い。決裁権者である天皇・関白は出席せず。 諸太夫の昇進について、特に詳述。外記、史が出世コース。学生や史生から昇進を重ね六位外記になると順番で従五位に叙爵する。叙爵すると待機ポストで除目による任用を待つことになる。その間国司の下で私に働くことも。11世紀終わりには、この昇進ルートが途切れ家格による固定的なものに。 最後に従五位で終わった者にとっては、身につまされるところ。
Posted by 
イメージする優雅な平安貴族の日々。 しかし、その実態は、年中行事に追われる毎日。 祭礼の準備、書類を認め、挨拶回りに、それが終わったらまた次の仕事。 いったいいつ休んでいるのかという感じ。 中には未明近く、あるいは、夜が明けてから帰宅する貴族も。 平安時代から「前例があるから...
イメージする優雅な平安貴族の日々。 しかし、その実態は、年中行事に追われる毎日。 祭礼の準備、書類を認め、挨拶回りに、それが終わったらまた次の仕事。 いったいいつ休んでいるのかという感じ。 中には未明近く、あるいは、夜が明けてから帰宅する貴族も。 平安時代から「前例があるから」「前例がないから」という理由で、官僚の仕事が進んでいたのも面白かった。
Posted by