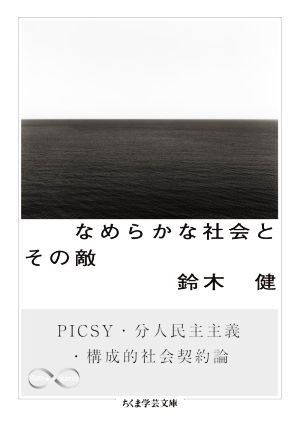- 書籍
- 文庫
なめらかな社会とその敵
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
なめらかな社会とその敵
¥1,540
在庫あり
商品レビュー
3.9
9件のお客様レビュー
300年後の社会を構想した本。 「この複雑な世界を,複雑なまま生きることはできないのだろうか」という冒頭の文章に心動かされ手に取った。 数式的な部分の理解は飛ばしてしまったが、要旨は以外2点だと受け取った。 1.インターネットとコンピュータの発達により、複雑なものを複雑なまま受...
300年後の社会を構想した本。 「この複雑な世界を,複雑なまま生きることはできないのだろうか」という冒頭の文章に心動かされ手に取った。 数式的な部分の理解は飛ばしてしまったが、要旨は以外2点だと受け取った。 1.インターネットとコンピュータの発達により、複雑なものを複雑なまま受け取ることが可能になる(物理世界と認知の間の万能のミドルウェアとして情報技術) 2.フラットでもステップでもない、内と外が連続的につながっている状態(=なめらか)を志向する 現在のインターネットの状態と比べると理想を描きすぎていると感じる点は否めないものの、想定問答に対する反論や現状考慮できていない点に対する真摯さは、本論に取り組む決意を感じた。 その上で考慮から漏れていると感じた点は、インターネットという仮想空間を維持するための物理的制約(ハードの維持管理)とソフトのメンテナンス体制の2点だ。 前者は2025年現在話題となっているAIを成立させるためのデータセンターの増加及び電力消費の増大という形で表出している。テクノロジーの進歩で解決できる側面もあるのだろうが、本書を読んだ限り膨大な計算を誰がするのかの視点が抜けているように感じた。
Posted by 
> 本書が挑戦するのは、膜と核という2つの社会現象がインターネットによって打ち破られるのか、もし可能だとして一体どのような方法で可能なのかという問題である。(1.2. 膜と核) 科学的なメタファーで社会を分析するやり方自体はおもしろかったものの、シグモイド関数などはモデル...
> 本書が挑戦するのは、膜と核という2つの社会現象がインターネットによって打ち破られるのか、もし可能だとして一体どのような方法で可能なのかという問題である。(1.2. 膜と核) 科学的なメタファーで社会を分析するやり方自体はおもしろかったものの、シグモイド関数などはモデルではなくメタファーとして紹介されており、再現性を持った問題の解決方法には達していないという印象を受けた。 数式や行列計算も多く出てくるが、現象よりも数式が先立っているように読めてしまい、理解が難しかった。
Posted by 
2024.03.08 長らく読みたかったが文庫化されてから、また長い時間が経ってしまったが、とうとう本屋で購入した。横書きという体裁への驚きはすぐになくなり、難しい算式に戸惑いながらも、すべて読了(算式は読み飛ばしても問題なく読める構成に感謝)。 著者は、人間の認知限界により、...
2024.03.08 長らく読みたかったが文庫化されてから、また長い時間が経ってしまったが、とうとう本屋で購入した。横書きという体裁への驚きはすぐになくなり、難しい算式に戸惑いながらも、すべて読了(算式は読み飛ばしても問題なく読める構成に感謝)。 著者は、人間の認知限界により、世界を単純化せざるを得ないことを指摘するところから議論はスタートする。罪を犯した人の背景を考えるブレストで、僕たちの世界はもっともっと複雑であったことを思い出させられた。そんな事実を忘れていた自分へ一番驚いた。複雑な世界を複雑なまま受け入れる事はあまりにも難しい。これは人間の脳の認知機能の問題であり、インターネットなどの技術の発達により、世界の見方を変えられるのではないかということがこの本の大きなストーリーである。 資源を囲い込み内部と外部を分離する膜と、膜を操る権力となる核。この2つの構造は、資本においても政治権力においても見られ、本来手段であるものが自己目的化して凝り固まる。資本は資本家に集められ、権力は一手に集中する。本書はそこに変容を与えることに挑戦する、提案していく。 核や膜の形成は生命史に深くプログラミングされたことであることから議論はスタートする。が、一見核や膜で説明しやすい事象は、それらを成立させる複雑な相互作用のネットワークである網があり、それこそが本質なのである。 生命史に刻まれた核と膜の重要性に対して、環境である網=ネットワークに技術を適用することで本質的にものごとをとらえる(世界を複雑なまま捉えることができる)。 読了後に、世界の見え方がまた少し変わった。 ・自由意志は存在しない。運動が先に始まり、その後意志が動く。自由意志はいわば拒否権。適切さが一貫性を意味するときに、人は運動を後付けで合理化する。 ・ものごとを2分化する。そのための制度が視野を固定化する(婚姻という制度が、婚姻届や婚姻者用住居の整備などにより、強固になる)。 ・自由とは、与えられた選択肢の中から選択することが可能であることでは決してなく、複雑なまま生きることが可能であることを言う。 ・そもそも官僚機構とは、法律と言うある種のプログラムによって書かれた内容を実行する存在である。直接民主制においても、実際にその意思決定が実行されるかどうかは官僚制の実行に委ねられるのが現実だ。だから、その効率性や性格性や法律の自動実行によって飛躍的に向上する。
Posted by