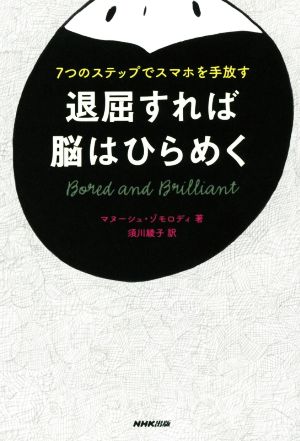
- 新品
- 書籍
- 書籍
- 1215-03-00
退屈すれば脳はひらめく 7つのステップでスマホを手放す
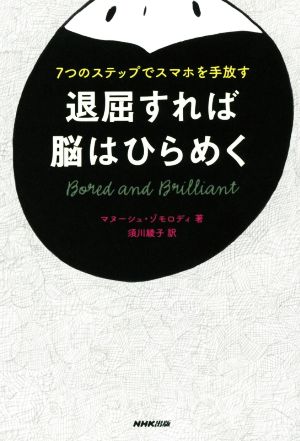
1,760円
獲得ポイント16P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | NHK出版 |
| 発売年月日 | 2017/10/01 |
| JAN | 9784140817261 |
- 書籍
- 書籍
退屈すれば脳はひらめく
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
退屈すれば脳はひらめく
¥1,760
在庫なし
商品レビュー
3.3
17件のお客様レビュー
スマホ、しまっとこう。見すぎるなら、アプリ削除して、何ならアカウントも削除。それくらいしないとダメなんだろうなあ。やれない時点ですでに依存症か。うーん。
Posted by 
本書で引用されているキルケゴールの言葉が印象的だ。 「何もしない状態は人間の存在の中心的状態であり、 それが欠けているものは人間のレベルに達していない」 日々、俯きながらマスクを付けて虚な目でスマホを眺め続けている人々を見て「家畜みたいだな」と感じていた私にとっては、やっぱり...
本書で引用されているキルケゴールの言葉が印象的だ。 「何もしない状態は人間の存在の中心的状態であり、 それが欠けているものは人間のレベルに達していない」 日々、俯きながらマスクを付けて虚な目でスマホを眺め続けている人々を見て「家畜みたいだな」と感じていた私にとっては、やっぱりそうだよねという感覚だ。 プラットフォーマーに搾取される人生で良いのだろうか。 アルゴリズムのように生きて、後悔しないのだろうか。 そもそもそんな疑問すら抱けないような「人間」を量産する現代社会が狂っているのだろうか。 とにかくスマホはインプットではなく、アウトプットに使う。 これを徹底していく。 私はこれからも人間でいたい。
Posted by 
タイトルにはスマホを手放すとあるが、スマホを手放すことが目的なのではなくて、”退屈“にあてられるはずの時間をスマホに割きすぎてしまっているから減らしてこうね!ということかなと思った マインドフルネスとマインドワンダリングについての違いが興味深かった たしかに、ヨガとかの音声ガ...
タイトルにはスマホを手放すとあるが、スマホを手放すことが目的なのではなくて、”退屈“にあてられるはずの時間をスマホに割きすぎてしまっているから減らしてこうね!ということかなと思った マインドフルネスとマインドワンダリングについての違いが興味深かった たしかに、ヨガとかの音声ガイドでもひたすら「キャンドルの炎をイメージして!呼吸に集中!」というやつと「浮かんできたイメージ、感情をただそこにあるものとして受け入れます」というのがあるな〜と思い、マインドフルネスもみんな同じわけじゃないんだなという気づき
Posted by 

