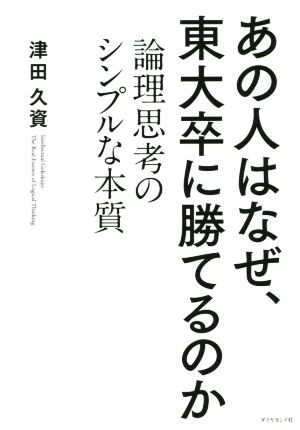
- 新品
- 書籍
- 書籍
- 1209-02-28
あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか 論理思考のシンプルな本質
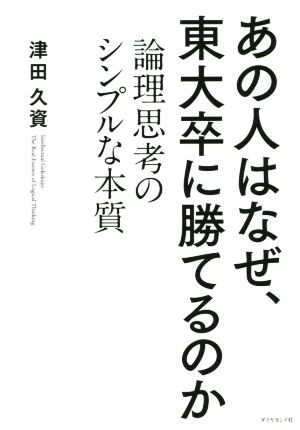
1,540円
獲得ポイント14P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ダイヤモンド社 |
| 発売年月日 | 2015/09/19 |
| JAN | 9784478065174 |
- 書籍
- 書籍
あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか
¥1,540
在庫なし
商品レビュー
3.7
55件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか』との対話を通じて得られた気づきは、単なる思考法の理解を超え、自身の経験の再解釈と体系化の可能性を開くものでした。本書の核心である「バカの壁」の概念は、無意識の思考制限を可視化し、論理思考の本質を「発想の速度と多様性」に置く点にあります。長年実践してきた「仮説検証型アプローチ」が、実はMECE(モレなくダブりなく)の原則と直感の統合によって成り立っていたことに気付かされました。 具体的な気づきは三つあります。第一に、情報収集の目的が「仮説の裏付け」から「発想の素材集め」へと転換した点です。過去のプロジェクトで無意識に行っていた業界トレンドの横断的比較が、実は本書の提唱する「情報量×加工率」の最適化そのものだったと理解できました。第二に、パワーポイント作成前のワードでの構想作業が、思考の構造化だけでなく「言葉の境界線の明確化」という機能を果たしていたことに気付きました。第三に、会議での「しまった」という後悔が、発想率の低さではなく情報加工の甘さに起因していたという分析視点の獲得です。 特に興味深かったのは、ロジックツリーとゴールデン・サークルの相似性に気がつけたこと。WHY(目的)を起点にHOW(方法)とWHAT(具体策)を展開するプロセスが、新規事業開発でも既存業務改善でも共通の基盤を持つことを再認識しました。これは、過去に成功したプロジェクトの裏側に常に存在していた「無意識の型」を言語化したもので、経験知をチームに継承する際の指針となり得ます。 実務家としての気づきは、次の三点に集約されます。第一に、直感とフレームワークの統合が「再現性あるイノベーション」を生むという事実。第二に、言葉の定義が現実認識を規定するという逆説的真理。第三に、競争優位の本質が「戦場の選択」と「思考速度」の組み合わせにあるという戦略的洞察です。 今後実践すべきことは、日常業務での「小さな気付き」をMECEで分解する習慣化です。例えば、取引先との会議で感じた違和感を「情報量不足/加工ミス/発想の偏り」の三軸で分析し、改善策を導く。これにより、本書が提唱する「発想の質」の向上を継続的に図れます。経験と理論の往還が、真の意味で「バカの壁」を超える力となることを学びました。思考の可視化と体系化は、単なる手法ではなく、組織的な競争優位を築くための基盤だという結論に至ったのです。
Posted by 
あーコンサルが書いてるなーって感じの内容。言ってることそのものは悪くないが、言い方が悪い。独自性を出したいがために、不自然な用語を作り出し無駄に話を複雑にしているような印象。その上で、かつての社会人時代の思い出として「マッキンゼーは難しいコンサル用語を使わないことが凄かった」とし...
あーコンサルが書いてるなーって感じの内容。言ってることそのものは悪くないが、言い方が悪い。独自性を出したいがために、不自然な用語を作り出し無駄に話を複雑にしているような印象。その上で、かつての社会人時代の思い出として「マッキンゼーは難しいコンサル用語を使わないことが凄かった」としているのだからタチが悪い。 何よりも著者がそもそも東大卒であり、本書の中で負けたと評しているのはハーバードの学生やマッキンゼーの人間であって、事実として学歴による差だと言えるのでは。 1章、考えることの定義を提起。考えている時間イコール書いている時間とは随分雑な結論を出しているが、わからんではないというライン。 2章、発想を広げるためにバカの壁を越える必要があり、まずはバカの壁があることを自覚する必要がある。そのためにツールを使い、あらゆる視点で考え尽くす、網羅することを推奨する。この辺りは結局地頭が必要な点を隠している狡さを感じた。時間が有限でありビジネスにおいてスピードは価値であると示しているのに、この考える作業を実践できる人が多いとは思えない。またここで、自分自身が本書では天才と呼ばれるタイプに比較的近いかもしれないと感じ始める。 3章、言葉により境界を作るのだから論理性は語彙力に基づくと言った展開。実際にざっくりとした優秀さと語彙量に相関があるとはよく聞く研究なので、想像はしやすい。 4章、発想力を高めるためにツールを用いて漏れをなくそう。ただ完璧なツールはなく、ある一定のライン以上は論理的なプロセスでは辿り着けない。なんだそれ、そこをどうにかしないとビジネスで競合を出し抜けないって話じゃないのかよ。MECEの解説も割と雑。 3章から知識量で負けている分を発想力と加工力を高めて競争に勝つをテーマに進んできたが、第5章では一転し、発想の材料となる「知識の幅」が重要であると述べる。特定分野の専門知識を深めることよりも、幅広い知識を身につけることで発想の視野が広がるとし、「情報流入」という概念を用いて説明している。知識の幅を広くすること自体は共感するが、ここまでの説明からこの流れは悪い意味でずるい。 第6章では、発想の質を高める手法としてロジックツリーを紹介する。しかし、内容の多くは結果論的であり、ビジネスにおけるスピード重視の姿勢と、MECEを使ってツリーの完成度を求める論調にやや無理、矛盾を感じる。 第7章では、個人の発想からチームや上司としての「考える力」へと視点を広げる。情報収集においては、効率化のため「仮の結論」を持ちそれを補強する情報を探すという手法を紹介。 第8章は、本書の中で最も価値があると感じられた部分。現代ビジネスにおける「学ぶこと」の意義を再確認しつつ、先進国では学ぶべき項目が減少し、「考えること」が差を生む時代になっていると指摘する。一方、中国や過去の日本では「学ぶ・真似る」ことが成長の鍵だったとし、ゼロからの思考よりも効率的な成長方法があったことを示唆している。
Posted by 
目的:ファーストクラブ達成に必要なマーケティング、経営者から用いられる魅力開発、ロジックを学ぶ ▼定義 学ぶ:既存のフレームワークに当てはめて答えを導く 考える:自分で作ったフレームワークから答えを導く 発想の質=情報量×加工率×発想率 考える=書く事 言葉は境界線である ロジ...
目的:ファーストクラブ達成に必要なマーケティング、経営者から用いられる魅力開発、ロジックを学ぶ ▼定義 学ぶ:既存のフレームワークに当てはめて答えを導く 考える:自分で作ったフレームワークから答えを導く 発想の質=情報量×加工率×発想率 考える=書く事 言葉は境界線である ロジックツリーの本質:論理の筋道×直感の飛躍 ●ツリー3種 1. why 問題の分解、原因探求 2. how 課題分解、解決策探求 3. what その他 ●mece3ステップ 直感→上流→下流 ▼気づき ・発送のスピードupが発想の質を高める事に直結する。 ・ボツアイデアが多い人ほどクリエイティブ ・人は枠内を考えている事に気づかず、枠外がある事を知らないものだ ・あるあるネタ=潜在的なアイデアの顕在化 ・受け身であれば情報流入が増える(学校教育)↔︎キュレーション ・知恵は背景の理解、whyで深まる ▼実行すること ・20アイデアの習慣 ・制限時間決めてアイデア出し ・前提を疑う ・アイデアは2つの組み合わせで作る(カードを引いて合わせるなど) ・メモはノート化する ・徹底的に思考→仮説構築→情報収集 ・どこで戦うか?考える
Posted by 



