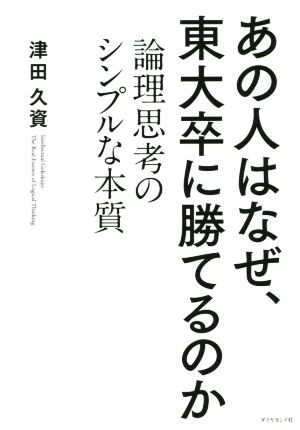あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか の商品レビュー
目的:ファーストクラブ達成に必要なマーケティング、経営者から用いられる魅力開発、ロジックを学ぶ ▼定義 学ぶ:既存のフレームワークに当てはめて答えを導く 考える:自分で作ったフレームワークから答えを導く 発想の質=情報量×加工率×発想率 考える=書く事 言葉は境界線である ロジ...
目的:ファーストクラブ達成に必要なマーケティング、経営者から用いられる魅力開発、ロジックを学ぶ ▼定義 学ぶ:既存のフレームワークに当てはめて答えを導く 考える:自分で作ったフレームワークから答えを導く 発想の質=情報量×加工率×発想率 考える=書く事 言葉は境界線である ロジックツリーの本質:論理の筋道×直感の飛躍 ●ツリー3種 1. why 問題の分解、原因探求 2. how 課題分解、解決策探求 3. what その他 ●mece3ステップ 直感→上流→下流 ▼気づき ・発送のスピードupが発想の質を高める事に直結する。 ・ボツアイデアが多い人ほどクリエイティブ ・人は枠内を考えている事に気づかず、枠外がある事を知らないものだ ・あるあるネタ=潜在的なアイデアの顕在化 ・受け身であれば情報流入が増える(学校教育)↔︎キュレーション ・知恵は背景の理解、whyで深まる ▼実行すること ・20アイデアの習慣 ・制限時間決めてアイデア出し ・前提を疑う ・アイデアは2つの組み合わせで作る(カードを引いて合わせるなど) ・メモはノート化する ・徹底的に思考→仮説構築→情報収集 ・どこで戦うか?考える
Posted by
MECEやロジックツリー関連の本を読んでも腹落ちして出来てなかった部分が腹落ちした。 ロジカルシンキング、論理的思考をその言葉を使わずに説明されており、難しい古文の話を現代語で翻訳されているようでよく理解できた。 学んだこと 考える時のアイデアだしフロー 1.まずは直感でだ...
MECEやロジックツリー関連の本を読んでも腹落ちして出来てなかった部分が腹落ちした。 ロジカルシンキング、論理的思考をその言葉を使わずに説明されており、難しい古文の話を現代語で翻訳されているようでよく理解できた。 学んだこと 考える時のアイデアだしフロー 1.まずは直感でだしつくす 2.大きなグループから分解していく 3.下流から登っていく それでもでないときは直感で出したものと下流のものから上に登っていく うっかり忘れ、発想のモレを無くすためのものをチェックリストと呼ぼう。優れたチェックリストに共通するのは、「項目に漏れがない」「項目が出来るだけ具体的である」 いきなりチェックリストは作れないので段階的に作っていく。(公園の鳩の数が減った話 あならや
Posted by
■ 考える=❶言葉を構造化(上位概念・下位概念・グルーピング)して❷その関係を明確にすること/❶=発想←今考えている言葉とその言葉「以外」を対にすることを忘れない❷=筋道 ■ 書くこと=考える
Posted by
論理的思考を身につけることで、東大卒レベルの頭の良い人たちに勝つための本。 バカの壁を視覚化できるようになることで、思考の見落としを防ぐようにする方法をまとめている。 バカの壁を意識化するとは、自分が考えてる範囲を明確にすること。今、自分がどこにフォーカスしているのかを意識しな...
論理的思考を身につけることで、東大卒レベルの頭の良い人たちに勝つための本。 バカの壁を視覚化できるようになることで、思考の見落としを防ぐようにする方法をまとめている。 バカの壁を意識化するとは、自分が考えてる範囲を明確にすること。今、自分がどこにフォーカスしているのかを意識しながら考える。 言葉によって、現実に境界線を入れる → この部分は以前に自分で考えていた内容と同じ。語彙力を身につけることで現実の境界を明確にしやすくなる。 メモしたものは、接続詞をつけて文章としてまとめるようにする。
Posted by
フレームワークは何のためにあるのかとか、考えることの本質とかに、他の本よりも一歩踏み込んで教えてくれた。 優れたアイディアは論理思考から生まれる、これがベースにある本。 考えることは公式に当てはめることではなく(これは学びの成果を生かした高級なルーティンに過ぎない)、公式を考えだ...
フレームワークは何のためにあるのかとか、考えることの本質とかに、他の本よりも一歩踏み込んで教えてくれた。 優れたアイディアは論理思考から生まれる、これがベースにある本。 考えることは公式に当てはめることではなく(これは学びの成果を生かした高級なルーティンに過ぎない)、公式を考えだすこと。今までと違い、見本がない中では学ぶことより考えることのほうが重要になってきた。 天才は多作。名作の陰に大量の駄作がある。我々凡人もそれだけの発想をするために必要なこと。思考の幅を広げるためにバカの壁を意識化すること。発想の質≒発想の広さ=情報量×加工率×発想率。考えることは書くこと。言葉は境界線、語彙力を磨くことの重要性。知識は絶対量より幅を広げるべき、知識は知恵へと深めるべき。結論仮説→情報による検証のサイクルを高速で回すことの重要性。
Posted by
ロジックツリーを作っても発想が広がってなかったら意味がない。作ったあと、アイデアが広がったか検証しよう。
Posted by
凡人にはバカの壁が存在すること、発想の広さは情報量×加工率×発想率で決まる、という二点が特に印象的だった。
Posted by
副題がしっくりくる内容。論理的に考えるとは書きながら、整理することでより狭く深く考えられることを教えてくれる書
Posted by
言葉をはっきりさせることの難しさ: Meet Up 大阪 @ blog http://www.meetuposaka.com/article/459085768.html
Posted by
■本を読んで学んだメッセージ 「考える」とは自分が作ったフレームワークで答えを導くこと 論理的思考を用いてアイデアの数を増やすことで、発想の質を高めることができる ■本を読む前の自分が考えていたこと 優れたアイデアを発想できる人との違いは「才能」によるものと考えていた ■本を...
■本を読んで学んだメッセージ 「考える」とは自分が作ったフレームワークで答えを導くこと 論理的思考を用いてアイデアの数を増やすことで、発想の質を高めることができる ■本を読む前の自分が考えていたこと 優れたアイデアを発想できる人との違いは「才能」によるものと考えていた ■本を読んで ・気づいたこと 論理的思考力を用いることによって優れたアイデアを発想することができる ・これからやってみようと思ったこと ロジックツリーを用いて思考の幅を広げる 「言葉」にこだわる ■本を読んで学んだこと ①僕たちはいつも「考えた」と誤解する ②「バカの壁」を意識化して思考の幅を広げる ③言葉の「境界線」を意識して論理的に考える ④MECEに考え発想率を高める ⑤「幅(多様性)」を広げ発想の材料を増やす ⑥ロジックツリーを用いて発想の質を高める ⑦4つの習慣で言葉の力を高める ⑧まず「結論仮説」を立案し、その上で情報収集する
Posted by