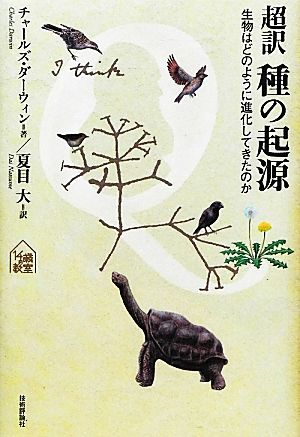- 書籍
- 書籍
超訳 種の起源
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
超訳 種の起源
¥1,628
在庫あり
商品レビュー
4.3
18件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
19世紀、科学者は一人前の職業ではなく、趣味や興味で研究するものだった。 ビーグル号の航海中、ライエンの『地質学原理』の斉一説に触発された。 ガラパゴス諸島は、進化論が生まれた場所として知られている。 ターウィンの祖父エラズマスダーウィンも進化論者だった。 マルサスの人口論にヒントを得て、食料が不足すれば絶滅するという自然選択を考えた。 種の起源は、それまでに書き溜めたものを本にしたもの。最初は、進化ではなく変化、とした。 進化論は差別の正当化に使われやすい。また資本主義の正当性を主張するのにも誤用されやすい。 種の起源は、自然選択だけで説明できること、人類の相対化、に勝ちがある。 掛け合わせても雑種が生まれない。仮に生まれても生殖能力がない、場合は別種。 変化が蓄積して起きる。目の途中の段階でも、有用であれば生き残って更に変化する。 交雑が有利なのは、劣性遺伝子が重なることが少ないから病気の遺伝子も引き継がないことから。 中間段階の生物が見つからないのは、化石として残っているのはほんの一部だから。化石の記録には空白が多い。もしすべての化石が見つかったら、種の区別はできない。 ミツバチは針を刺すと死んでしまう。欠陥のように見えるが、この状態でも生存競争に勝てたからこそ、この機能のままにいる。これが種の保存に不利ならば自然選択が起きて、死なないミツバチが生まれただろう。 人間にも盲点がある。なくても困っていないから改良されない。 本能も自然選択。本能は一見利他的にみえても、利己的なもの。 カッコウの托卵は、2~3日おきに産卵するからではないか。 奴隷狩りをするアマゾンアリ。 働きアリはメスだが不妊。このほうが都合がいいのだろう。 地層は断絶しやすい。すべての時代の地層があるわけではない。 アメリカ大陸のウマは、化石は見つかるが、最近持ち込まれたもの。 オーストラリアの有袋類は、隔絶されたために生き残った。
Posted by 
昔の本の場合、当時考えられてた間違った理論などもそのまま記載されてることが心配だった。しかし、この本は注釈に現代の定説も書いてあったのでよかった。 噛み砕いた文章だったので、初心者のわたしでも、問題なく読めた。 この時代に、ダーウィンがここまでの推測をたててたのは改めてすごい...
昔の本の場合、当時考えられてた間違った理論などもそのまま記載されてることが心配だった。しかし、この本は注釈に現代の定説も書いてあったのでよかった。 噛み砕いた文章だったので、初心者のわたしでも、問題なく読めた。 この時代に、ダーウィンがここまでの推測をたててたのは改めてすごいと思った。
Posted by 
誰しもダーウィン、 進化論、 自然選択というワードを聞いたことがあると思いますが、 その本文を読んだことがある よという人はかなり少ないのではないかと思います。 本書 は、ダーウィンの有名な 『種の起源』 を中学生でも理解で きるような平易な言葉使いで書いたものです。 さて、...
誰しもダーウィン、 進化論、 自然選択というワードを聞いたことがあると思いますが、 その本文を読んだことがある よという人はかなり少ないのではないかと思います。 本書 は、ダーウィンの有名な 『種の起源』 を中学生でも理解で きるような平易な言葉使いで書いたものです。 さて、 過去の書評でも書きましたが、 昔の科学の名著を今 読むというのは相当難しいことだと思います。 第一に、単純 に専門的な内容で難しいということ、 第二に、 当時何が知られていて何が知られていないのかという歴史的文脈を知ら ないと見当外れな読み方をしてしまう可能性があるということです。 本書はそういう意味で2つの難題に気を配ってい ると言えます。 1つ目は既に説明した通りですが、2つ目の 懸念も、念入りな時代背景の説明がなされ、「なぜ今ダー ウィンを読むのか」を明らかにしてから読めるようになっ ています。 もし読みが不安なら、 シッダールタムカジーの 『遺伝子』、アイザック・アシモフの 『生物学の歴史』、 佐々木閑 『犀の角たち』 を読むといいと思います。 さて、ダーウィンは (イメージと違って??) どうやら気の弱いタイプのようでしたが、その分膨大な博物学の知見を読者にこれでもかと提示して、 想定される反論に対応しています。 この姿勢は科学者だけではなくビジネスマンにも有用 なのではないか、と思えます。 行間からは、 「自分にはどう してもこう思えて仕方ないのだけどこれでいいのか?」と問 い続けた結果白らの内側でたくさん議論したことをしっかりと書いています。 大事なことは、全てのデータを(特定のものを無視しないで)説明するような理論を考えているということで、その姿勢が、仮に後世にいくらかの間違いがわかったとしても、そんなものは些細なことでしかなく、ダーウィンの偉大さが語り継がれている所以なのだなぁと思います。
Posted by