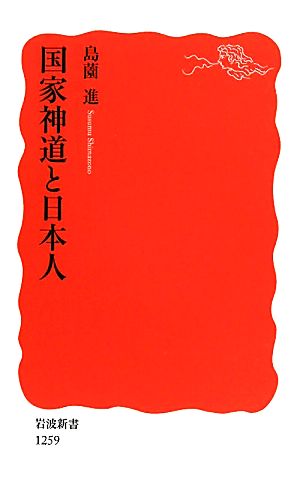
- 新品
- 書籍
- 新書
- 1226-29-00
国家神道と日本人 岩波新書
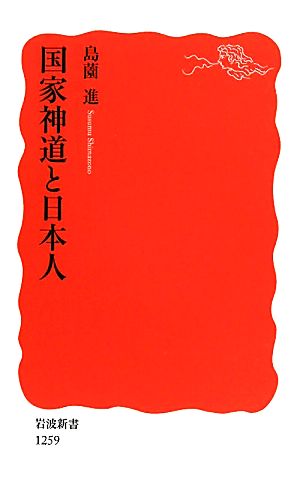
1,056円
獲得ポイント9P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2010/07/21 |
| JAN | 9784004312598 |
- 書籍
- 新書
国家神道と日本人
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
国家神道と日本人
¥1,056
在庫なし
商品レビュー
3.8
18件のお客様レビュー
はじめに - 国家神道の解明が重要である理由 - 自由や思想・良心の自由の保持に関連し、政教関係の政治的・法的問題も考慮されるべきである。 - 国家神道の理解を通じて、近代日本の宗教構造や信教の自由、政教分離の在り方を考察することを目的としている。 第一章: 国家神道の...
はじめに - 国家神道の解明が重要である理由 - 自由や思想・良心の自由の保持に関連し、政教関係の政治的・法的問題も考慮されるべきである。 - 国家神道の理解を通じて、近代日本の宗教構造や信教の自由、政教分離の在り方を考察することを目的としている。 第一章: 国家神道の位置づけ - 国家神道の歴史的経過 - 明治時代の神道国教化政策の変遷とその意義。 - 神道が国教的地位を保持しつつ、政教分離への道を歩んでいく過程を解説。 - 皇室祭祀と神社の結びつき、特定の神道のあり方が国民に強制される歴史的背景について言及。 第二章: 国家神道の把握 - 国家神道に対する捉え方の多様性 - 皇室祭祀や天皇崇敬と切り離して神社神道だけを国家神道とする見方の問題点。 - 国家神道は神社神道と皇室祭祀を結びつけて成り立っていることを強調。 - 国家神道の教えとその影響の広がりについての考察。 第三章: 国家神道の形成 - 国家神道の生み出された歴史的背景 - 幕末から明治維新期の国学と神道の関係。 - 教部省の設置や教育勅語の制定による国家神道の教化政策の進展。 - 祭政一致の理念がいかにして国家の根幹を支えたかについての考察。 第四章: 国家神道の普及 - 国家神道の広まりとその影響 - 教育制度や神社組織の整備を通じて国民への普及が進んだ。 - 「下からの国家神道」としての運動の重要性とその影響。 - 地域神職や民衆の参与が国家神道の発展に寄与した事例の紹介。 第五章: 国家神道の解体とその後 - 第二次世界大戦後の国家神道の変遷 - 神道指令による国家神道の廃止と皇室祭祀の維持。 - 教育勅語の廃止に関する議論とその影響。 - 現代における国家神道の影響と神社本庁の役割についての考察。 結論 - 国家神道の理解は、近代日本の宗教史や思想史を考える上で不可欠であり、特にその影響力の変遷を追うことが重要である。 - 国家神道の様々な側面を理解することで、現代における信教の自由や政教分離の問題をより深く考察する手がかりを得られる。
Posted by 
神道というと、本書でもとりわけ5章で述べられているように、祈願の成就のために向かう各種神社の管理をし、日本の神への祈祷祭祀を行っている人たち、またその関連信仰体系という印象を持っていた。 それだけに、神道には政治として神道を利用した国家神道、庶民における土着の自然崇拝・祖先崇拝、...
神道というと、本書でもとりわけ5章で述べられているように、祈願の成就のために向かう各種神社の管理をし、日本の神への祈祷祭祀を行っている人たち、またその関連信仰体系という印象を持っていた。 それだけに、神道には政治として神道を利用した国家神道、庶民における土着の自然崇拝・祖先崇拝、そしてそれらの間に位置するともいえる神社神道があり複雑な世界を構成していることは目から鱗で興味深い内容だった。 これまで理屈を知らず認識が不明瞭になっていた皇室、神社の立ち位置であったり、教育勅語での洗脳の如き教育などの点の知識が具体的な流れを持って繋がり、腑に落ちる部分が多くあった。 帝国主義の時代において、なぜ日本が戦争に突き進んでいったのか、その精神性を理解する上で本書の知識は欠かせないものと思う。 列強の圧力から開国を迫られ、大政奉還、明治維新へと進んで行った中で、日本の中枢や知識人は欧米の強さの理由と近代化への道筋を見つけて早急に進化する必要があった。 そんな歴史背景と、武士に根付いていた儒教の考え方、とりわけ考や仁を元に生み出された一つの方法が、神道と皇室崇敬を元にして国家を団結するというアイデア。 しかし結果的に民衆を抑えきれなくなって軍国主義へと進んでしまう大きな失敗は、政治としての皇室や神道という捉え方をエリートが生み出し、以て国民を操作するのに対して、国民には神話的な神聖性を植え付け、日常に信仰を沁みつけたこと、即ち本音と建て前のような二重性、言い換えれば支配・被支配関係を知識・思想の面で明確に分けてしまったことにあると思う。 民衆が政治や国家関係に口を出すのは非効率であることは確かである。それぞれがそれぞれの目の前の持ち分に集中して働くことには意義がある。 一方で、ベースとしての知見、考える力は国民全体で持っておくべきだろう。現代の義務教育の意義は大きい。 戦前までの支配層・被支配層という二重性を繋げていたのは、儒教的な、強引な上下関係だった。「君主には従う、目上の者には従う」というもの。理由などないに等しい。 これでは信頼は生まれない。全体がある程度の知的水準を持ち、情報の透明性を持つことこそ、信頼に足る関係性を形作るものだと私は信じている。物事を理解できる度合は人によって異なるが、正しい情報にアクセスできる平等性であったり政治の透明性であったり言論の自由といったものは、国家として一体性を持つには、神話を用いるよりよっぽど有効に思う。 まだ私は日本史の知識が弱いので、肉付けを厚くして理解を深めていきたい。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
国家神道の成りたちや、その成立によって明治期の新興宗教や江戸からの土着信仰に止まらず仏教キリスト教までもが国家の管理に納まらなければ事実上の弾圧を受けていた事実は改めて近代日本の闇の始まり、と印象をもった。戦後のGHQにより国家神道の解体が行われたが、明治期から行われていた天皇による皇室祭祀はそのまま現在まで残っている。 明治から取り入れられた皇室祭祀やのちに廃止された神社庁による全国神社の管理によって天皇が全国の神社を訪問する、ということがあり、今も神社に行くと天皇陛下が来た旨の張り紙や旗が立っている理由がわかって興味深い。 伊勢神宮については国家神道の頂点としたり、神社合祀や廃仏毀釈など近代国家の関与で残念な結果になってしまったことなども詳細に書かれている。 戦後の神社本庁についても今の神社本庁の在り方を納得させる記述が面白いのだけれど、事実を知って うわ… と暗い気持ちになる一冊。天理教や大本教にも触れている。岩波の本は文体が固く、疲れる。
Posted by 



