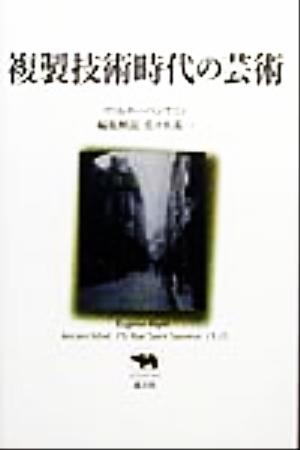

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 晶文社 |
| 発売年月日 | 1999/11/05 |
| JAN | 9784794912664 |
- 書籍
- 書籍
複製技術時代の芸術
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
複製技術時代の芸術
¥2,090
在庫あり
商品レビュー
4
16件のお客様レビュー
2026.1.19 視点がおもしろい 「ゲーテの『親和力』」とかと合わせて読むともっとおもしろくなる アドルノの手紙も良かった
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
正直私にはかなり難解である。写真(愛好)家は必読と思え読み始めて一旦中断、今後再開する。 アウラの喪失=複製により1回性が喪失する事、デジタル化の今日に対して予言的である事をプロの写真家から直接伺っていたので本書を購入。 一部読んだだけで、読破せずに勝手な知ったかぶりの解釈をするのは避けるべきだが、それを恐れずに言うと、私の好きな人形も造形作家や玩具メーカー内の名も無きデザインチームに作られた最初の1個(の3Dデータ)から複製して量産される無数の人形が総て等しく本物であり、それが多くの鑑賞者の手に渡る・・・と考えると本書は興味津々である。 生成AIの自動生成画像を試しに使って見ての感想として、21世紀の現代は「自動摸倣技術の時代の似非芸術」の時代と言えるのかも知れない。 ネットに常時接続された生成AIシステムが無数の写真、絵画、イラスト、文章を無断でサンプリングし、数値化し、それに対する開発者の勝手なバイアスの掛かった「統計処理」の元に出力されると言うのが所謂生成AIの正体では無いのかと、私個人は疑っている。 生成AIは只で使えると言われて使えば使う程、それに知見を与え、クリエーターは自らの首が締まる結果になると思われる。 生成AIの無い時代から、「創造とは経験の再構成」どころでは全くない「恥を知れ」と言える程の「単なるパクリ」が映画、漫画、小説に散見されるので、このままでは「全自動無人『創作(摸倣)』システム」が稼働し、小説家も漫画家も失職し、読者は今より更にツマラナイ本を読まされ、書評は有名な、存在しなかった映画評論家、「ジョン・マニング氏」より幾らかは巧妙なAI自動評論家がそうした自動生成された漫画や小説を高評価する事になるのではないか。挙句選挙もスマホによる「電子投票」更には「AIによる自動投票」となり「あなたに最適な政党、候補者はコレ」とAIが勝手に決め付け、与党は何時でも大勝利www 冗談?はさて置き、これから本書を読み進め、読破した時点で本レビューの改定を行いたい。
Posted by 
●2025年6月12日、グラビティの読書の星で紹介してる男性?がいた。 「ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』を読みました 複製技術とは写真や映画のことである。絵画における芸術には歴史の一回性という「アウラ」があり、礼拝的価値が存在する。しかし、このカメラによってそれら...
●2025年6月12日、グラビティの読書の星で紹介してる男性?がいた。 「ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』を読みました 複製技術とは写真や映画のことである。絵画における芸術には歴史の一回性という「アウラ」があり、礼拝的価値が存在する。しかし、このカメラによってそれらは喪失する。ただし、これは陳腐化ではなく、芸術の大衆化と絵画以上の情報の多さに新たな芸術を生み出す。 写真芸術の良さはあまり納得していないが、意味は理解した。」 贋作とか興味ある。
Posted by 

