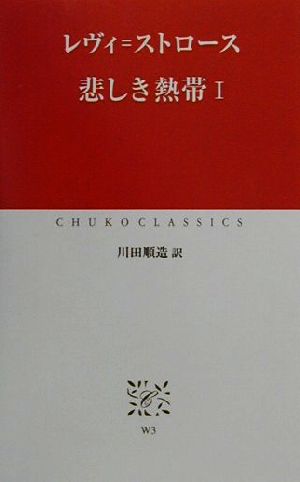- 書籍
- 新書
悲しき熱帯(1)
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
悲しき熱帯(1)
¥1,595
在庫あり
商品レビュー
3.8
53件のお客様レビュー
フランス人の作者レヴィ=ストロースは、英語読みするとリーバイ•ストラウス、あのジーンズメーカーの名前と同じだ。 あまり旅行好きでなかったレヴィ=ストロースが、若い頃、ブラジルの大学から招聘を受け、ブラジルの未開民族の調査に赴いた時の手記。 西洋人の目に映る未開民族の姿がビビッドに...
フランス人の作者レヴィ=ストロースは、英語読みするとリーバイ•ストラウス、あのジーンズメーカーの名前と同じだ。 あまり旅行好きでなかったレヴィ=ストロースが、若い頃、ブラジルの大学から招聘を受け、ブラジルの未開民族の調査に赴いた時の手記。 西洋人の目に映る未開民族の姿がビビッドに描かれて、読む者を引きずり込む。 彼の辿り着いた結論は、ヨーロッパの物の考え方に激震を与え、構造主義という、思想潮流というより、新しい思考枠組み(=方法論)を生み出した。 我々は今もこのレヴィ=ストロースの作り出した思考枠組み=方法論)の中で思考している。 「未開民族は取り残されてなんかいない 彼らの思考は西洋人の思考よりも理性的だ」と主張して、ヨーロッパ中心思想を解体した。 個人的なことを言えば、突然、脳の病で病院のICUに運び込まれた。 その時、こっそりとICUのベッドに持ち込んだのが、本書だった。 頭痛と闘いながら、眠れない日々、本書を読み進むのが、慰めだった。 ICUに本を持ち込んだ患者はあなただけだ、と医師に飽きられながらも、レヴィ=ストロースの筆に引き込まれていった。 「人生最後の本」となるかもしれなかった、忘れ難き書。
Posted by 
通勤電車の中で読もうとしたが、なかなか進まず。お盆休みで漸く読了。旅の話でない部分を噛みしめて読み進めていく書籍。
Posted by 
50年近く前に読んだ本。正確には、室淳介訳の「悲しき南回帰線」を読んだ。 最近、なぜかレヴィ=ストロースがマイ・ブームなので、読み直したわけだが、驚くほど、内容を覚えていない。 以前に読んだのは、訳が分かりにくいと言われる「悲しき南回帰線」というヴァージョンで、旅行記感覚でわ...
50年近く前に読んだ本。正確には、室淳介訳の「悲しき南回帰線」を読んだ。 最近、なぜかレヴィ=ストロースがマイ・ブームなので、読み直したわけだが、驚くほど、内容を覚えていない。 以前に読んだのは、訳が分かりにくいと言われる「悲しき南回帰線」というヴァージョンで、旅行記感覚でわりとスラスラと読めた記憶があったのだが、今読むとわりと難しい。 かと言って、人類学についてそれなりに本を読んできたり、南アメリカのインディオの大量虐殺、そしてユダヤ系知識人のアメリカへの亡命など、背景情報はだいぶ詳しくなっているので、今の方がわかるはずなんだけど、どうしてだろう。。。。 多分、昔はブラジルでのフィールドワークの部分を中心に読んで、それ以外のところは流し読みしていたんだろうな。 この第1巻は、ブラジルでの調査は1つの部族のもので、それに続くものは第2巻となっている。第1巻は、レヴィ=ストロースが人類学者になる過程とか、ブラジルへの船旅、ブラジルの都市(サン・パウロ)の印象、そして、アメリカに亡命する旅行などが主な内容。 が、これらは時系列になっておらず、アメリカへの亡命の船旅は第二時世界大戦中の話しで、ブラジルの大学への赴任や現地調査は30年代と時系列が入れ替わっている。また、ブラジルの話しがいつの間にか南アジアの話しになったりして頭が混乱してくる。 表現はわりと文学的な香りがあるが、だからといって読みやすいわけではない。 帯には「思想界に衝撃を与えた構造主義の原点」と書いてある。以前、読んだときの印象としては、構造主義というより、人類学的な旅行記というものであった。 しかしながら、今、読むと確かに構造主義的な発想で描かれているところも見えてきて、あながち帯のキャッチは嘘ではないことが分った。 だが、やはりそれ以上に、ブラジルで少数部族のフィールドワークをやっている時以外も、自分自身のストーリーも含めて、物事を人類学的に観察している冷めた視点が感じられた。 思ったより難しいけど、今、読み直してよかったと思う。 第2巻は、ブラジルでのフィールドワークの記述が中心なので、多分、もう少し読みやすくなっていることを期待したい。
Posted by