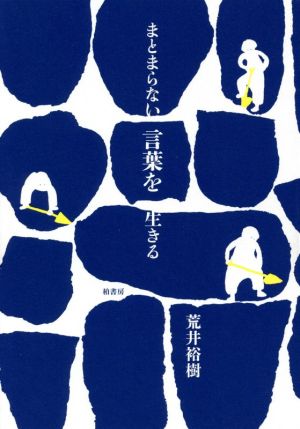
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1220-05-01
まとまらない言葉を生きる
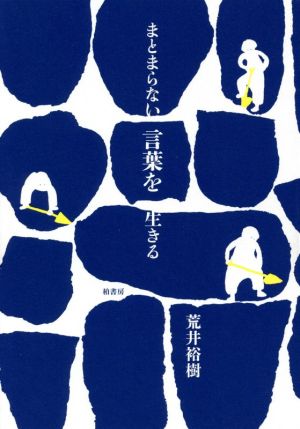
定価 ¥1,980
1,375円 定価より605円(30%)おトク
獲得ポイント12P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 柏書房 |
| 発売年月日 | 2021/05/03 |
| JAN | 9784760153497 |
- 書籍
- 書籍
まとまらない言葉を生きる
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
まとまらない言葉を生きる
¥1,375
在庫なし
商品レビュー
4.2
59件のお客様レビュー
率直にいえば、簡単に読んでいいような本ではないと感じた。そして、感想を書くのがとても難しかった。 私は、本書は『短い言葉や伝わりやすい言葉が重視されがちな現代において、短くできない言葉が存在しないものとされることや、本来の意味が理解されず言葉が軽く扱われていることに対して警鐘を...
率直にいえば、簡単に読んでいいような本ではないと感じた。そして、感想を書くのがとても難しかった。 私は、本書は『短い言葉や伝わりやすい言葉が重視されがちな現代において、短くできない言葉が存在しないものとされることや、本来の意味が理解されず言葉が軽く扱われていることに対して警鐘を鳴らすもの』だと理解した。 著者は「被抑圧者の自己表現」を専門としていることもあり、各エピソードは障がい者に関する内容も多くなっている。 特に第七話『「お国の役」に立たなかった人』を読んでいて、現在も同様の状況になっているのではと恐怖を感じた。 この章では、戦時中、”お国の役に立た”ず迫害の対象となった障がい者たちがさらなる迫害を受けないためにどういった言動をとればよいか考えた末、自発的に戦争を賛美するという行動をとった(そう表明することでその瞬間だけは世間からいじめられなかった)とある。 誰だって迫害されたくない。そういう心理を利用して、自発的に考え方を変えさせるようになっていくと、それはもう強権的な社会となってしまう。 同調圧力が強い日本では、特に誰か同じ立場の人が主張している内容に賛同してしまう人も少なくない。私も100パーセント他人の意見に左右されないとは言い切れない。それってとても危険なことで、自分の意見を持つこと、そしてそれを恐れずに発信していくことの重要性を改めて痛感した。とはいえ、言葉にするのは簡単で、痛感した内容をどう行動にしていけばいいのかはまだわからない…。 そして終話『言葉に救われる、ということ』にある『ものすごく言葉にしにくいことだが、相模原事件に関して、事件を起こした人物が行ったことに理解も共感も納得もできないとした一方で、自分と「地続き」のところを生きているという実感がある(できる限り内容を崩さないように記載)』と記載した著者は自分の深いところまで見つめている。それはとても難しいことで、(簡単な言葉で申し訳ないが)それができる著者はすごい人だと改めて感じた。そして自身が障がい者と関わり、自分の凝り固まったイメージをほぐしている、ということは自分の弱い部分を見つめなおすことで、相当苦しい思いをされたのでは、と勝手に想像した。 会議内容や本を要約するなど、”タイパ”を重視する人が多い世の中になってきたと思う。スピード感が重視され、回答は”早いこと=いいこと”になりつつあることにも危機感を感じる。もちろん恩恵は私も受けている。しかし、それは本当に正しい回答なのか、乱暴に言葉をつぎはぎしただけではないか。常に考えながら過ごしていきたい。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
以前から印象的な表紙を何度も見かけて気になっていた中、友人がおすすめしてくれたので読んだ。タイトルどおり、言葉をめぐるエッセイで、著者がコミットしてきた障害者運動を軸に現在の日本語を考察している一冊で興味深かった。 日々暮らす中で気になった言葉を巡るムードに関する考察がなされ、そこに障害者運動から見えた景色が付加される構成となっている。著者の言葉に対する着眼点は鋭く、普段使っている言葉の中に感じる違和感を余すことなく言語化しようと試みていた。著者の特徴として言語の両義性に注目している点が挙げられる。一点ポジティブに見えるような言葉でも、ひっくり返すとネガティブに捉えられる。それは自分の都合だけを考えるのではなく、他者の眼差しを考える、とりわけ社会のマイノリティである障害者の活動に従事してきたからこそ養われた言語に対する感性なのだろう。 介護施設で提供されるおでんが刻まれていた話が一番興味深かった。施設サイドとしては、事故を防ぐこと、また個別対応による労力を避けるため、効率を目的として、おでんを刻んで提供したが、著者の知り合いは「刻まれたおでんは、おでんじゃないよな」といって不満を述べる。日本の社会は「仕方ない」と諦め、和を乱さないことが美徳になる場面が多いが、このように小さいと思われることもあきらめてしまえば、その諦めてしまう心は際限なくどこまでも追いかけてくる。自分の考えを主張する必要性と妥協点のバランスについて「おでんを刻む」という想像もしないシーンから引き出されるだなんて斜め上の発想すぎる。 また、繰り返し登場する「降り積もる」という動詞は、今の言論空間のアナロジーとしてこれほど納得感があるものはない。それはSNSのUIの影響が大きいと考えられる。次から次へと上から言葉が降ってきて、下へと流れていく。フォローしている人の言葉に絞ることもできるが、今や「おすすめ」というランダムな言葉の集積がデフォルトになり、それはまるで雨や雪のように質と量をコントロールできない。そうして降り積もった言葉は時代の価値観の形成に寄与する大きな存在として眼前に立ちはだかるのであった。 言葉を軽く見る現状は、社会を軽く見ることと同義だという主張は本著の核心部分である。生産性、生きる意味、権利といった言葉を絡めて、我々の人生が軽視される可能性について思いを巡らせており、ここ数年は同じようなことを感じていた。他人の権利が侵害される様を指くわえて見ていると、いつのまにか自分の大切なものも奪われてしまうかもしれない。そんな想像力を強く喚起する一冊だった。
Posted by 
病気や障害を持つ人たちとのエピソード・言葉が読んでいるとなんだかグサグサと刺さってくる、言葉と社会を哲学している感覚。 「生きる意味」や「生きた心地を削る言葉」、「誰かや国のために役に立つこと」、「理不尽に抗う方法」、「自己責任」などなど印象の残る言葉がとても多かった。 当たり前...
病気や障害を持つ人たちとのエピソード・言葉が読んでいるとなんだかグサグサと刺さってくる、言葉と社会を哲学している感覚。 「生きる意味」や「生きた心地を削る言葉」、「誰かや国のために役に立つこと」、「理不尽に抗う方法」、「自己責任」などなど印象の残る言葉がとても多かった。 当たり前の日常が当たり前じゃなくなったときに、自分が社会を見る目がどう変わるのか、考えるきっかけにもなる。
Posted by 



