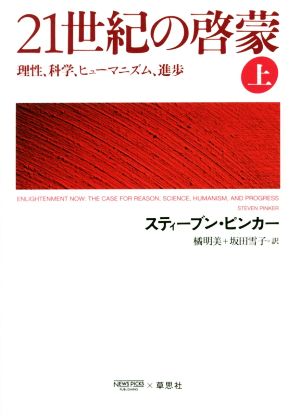
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1206-07-00
21世紀の啓蒙(上) 理性、科学、ヒューマニズム、進歩
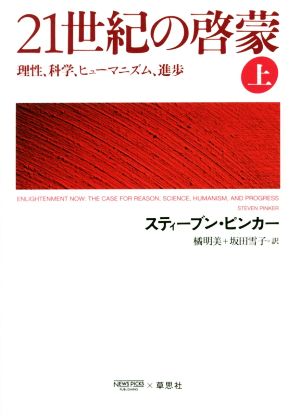
定価 ¥2,750
550円 定価より2,200円(80%)おトク
獲得ポイント5P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:1/4(日)~1/9(金)
店舗到着予定:1/4(日)~1/9(金)
店舗受取目安:1/4(日)~1/9(金)
店舗到着予定
1/4(日)~1/9

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
1/4(日)~1/9(金)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 草思社 |
| 発売年月日 | 2019/12/18 |
| JAN | 9784794224217 |
- 書籍
- 書籍
21世紀の啓蒙(上)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
21世紀の啓蒙(上)
¥550
在庫あり
商品レビュー
4.2
27件のお客様レビュー
ハンス・ロスリングのFACTFULNESSの方が親しみやすい文体でしたが、こちらも読み応えあり。 目次を読むだけでさらっと内容が頭に入ってくるところも素晴らしい。
Posted by 
人間の社会活動や経済活動などの全般を「エントロピーを減少させる活動」と扱っている第二章がおもしろい。 人間社会は放っておけばエントロピーが増大して散らかってしまう危ういバランスで成り立っており、法、科学技術、経済活動などは、すべて秩序を形成または維持するものとも考えられる。 その...
人間の社会活動や経済活動などの全般を「エントロピーを減少させる活動」と扱っている第二章がおもしろい。 人間社会は放っておけばエントロピーが増大して散らかってしまう危ういバランスで成り立っており、法、科学技術、経済活動などは、すべて秩序を形成または維持するものとも考えられる。 そのベースにあるのは進化と情報。
Posted by 
まじおもろ ニュースなどの利用可能性バイアス、ネガティビティバイアスに惑わされずに、データで現状の認識を改めることが大事 科学の進歩が世界にどれだけ利益をもたらしているのか少し理解できた。(マイナスも多少はあるだろうけど)
Posted by 



