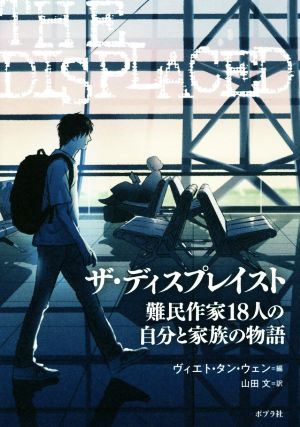
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
ザ・ディスプレイスト 難民作家18人の自分と家族の物語
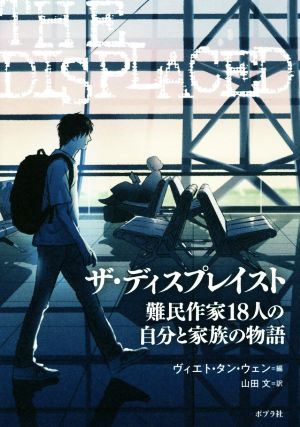
定価 ¥1,870
550円 定価より1,320円(70%)おトク
獲得ポイント5P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
11/30(土)~12/5(木)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ポプラ社 |
| 発売年月日 | 2019/02/07 |
| JAN | 9784591162125 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
11/30(土)~12/5(木)
- 書籍
- 書籍
ザ・ディスプレイスト
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ザ・ディスプレイスト
¥550
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
5件のお客様レビュー
アニメ的な表紙に反して、重い、辛い話が続く。生きるために命がけで愛する故郷をあとにして、新たな国を目指して流浪の旅を続け、絶え間ない飢えや命の危険を超えてたどり着いた先での、さらなる差別や苦難には心が痛む。排外主義や不寛容が広がるこの世界で、難民の置かれた状況がさらに悪化している...
アニメ的な表紙に反して、重い、辛い話が続く。生きるために命がけで愛する故郷をあとにして、新たな国を目指して流浪の旅を続け、絶え間ない飢えや命の危険を超えてたどり着いた先での、さらなる差別や苦難には心が痛む。排外主義や不寛容が広がるこの世界で、難民の置かれた状況がさらに悪化しているであろうことは、想像に難くない。一人称で語られたこのようなルポを読むことで、少しは難民理解に繋がるか、いや、そもそもこのような本を手に取る人は少数派か。やりきれない思いを募らせるばかりである。
Posted by 
displaysed -故郷、故国を失った、はずされた、追放された、難民、流民 難民としての経験をした筆者たちが出自について回想し、アイデンティティを問うた作品が集められたアンソロジーです。サブタイトルにあるとおり執筆陣のほとんどは作家であるため、事実を書き残すことは主眼ではな...
displaysed -故郷、故国を失った、はずされた、追放された、難民、流民 難民としての経験をした筆者たちが出自について回想し、アイデンティティを問うた作品が集められたアンソロジーです。サブタイトルにあるとおり執筆陣のほとんどは作家であるため、事実を書き残すことは主眼ではなく文学的なトーンを帯びた作品が多くを占めています。編者をはじめとして難民としてだけではなく文学者であることに強く意識を向けて書かれたものも少なくありません。 客観的な記録・報告文を期待すると当てが外れて、戸惑うかもしれません。
Posted by 
エッセイ、ノンフィクションなんだよね、つまりこれは現実。 どんな国で、どんな状況で、どうして難民になるのか、そして行った先の国でどんなことが待ち受けているのか。まるで知らなかった。 悲惨で読むのがつらい話もあったが、そうだよねきっとそうだよねと共感するところも。 どれもよかった...
エッセイ、ノンフィクションなんだよね、つまりこれは現実。 どんな国で、どんな状況で、どうして難民になるのか、そして行った先の国でどんなことが待ち受けているのか。まるで知らなかった。 悲惨で読むのがつらい話もあったが、そうだよねきっとそうだよねと共感するところも。 どれもよかったけれど、中でも『トランプの壁は、つくられる前からおいしい食べものに負けていた』(アリエル・ドルフマン)、『恩知らずの難民』(ティナ・ナイェリー)がよかった。
Posted by 


