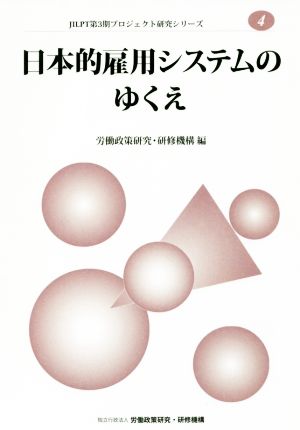
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1210-02-00
日本的雇用システムのゆくえ JILPT第3期プロジェクト研究シリーズ4
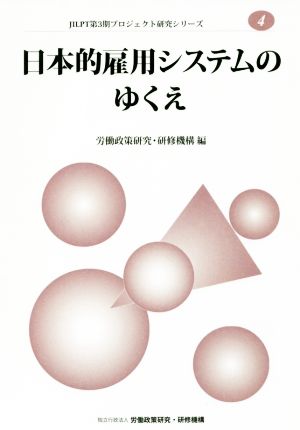
定価 ¥2,750
550円 定価より2,200円(80%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 労働政策研究・研修機構 |
| 発売年月日 | 2017/12/01 |
| JAN | 9784538520049 |
- 書籍
- 書籍
日本的雇用システムのゆくえ
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
日本的雇用システムのゆくえ
¥550
在庫なし
商品レビュー
5
1件のお客様レビュー
本書を編集したJILPTの正式名称は「労働政策研究・研修機構」であり、厚生労働省所管の独立行政法人。法人のHPには、「内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員...
本書を編集したJILPTの正式名称は「労働政策研究・研修機構」であり、厚生労働省所管の独立行政法人。法人のHPには、「内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うことにより、我が国の労働政策の立案及びその効果的かつ効率的な推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展に資すること」が組織のミッションであることが示されている。質の高い研究成果をまとめた書籍・冊子や統計情報を公開している。本書は、その研究をまとめた1冊である。 本書の目的は「特に"日本的雇用システム"のゆくえ(=持続していくもの、変化していくもの、新たな問題)を見通すこと」とされている。なお、「日本的雇用システム」とは、「主に高度経済成長期以降の大手・製造企業に典型的に見られた、成員に対する生活保障・能力開発を図る雇用・労働の仕組み」と定義されており、構成要素としては、(a)長期雇用慣行(b)年功的賃金・昇進(c)協調的労使関係(d)OJTを中心とした幅広い教育訓練(e)雇用のバッファーとしての一定数の非成員労働者の存在(f)労使の規範意識と国民からの支持、の6つがあるとしている。 高度経済成長期から安定成長期に発展・完成したと言われる「日本的雇用システム」であるが、バブル経済崩壊以降の日本企業・日本経済低迷の中で変容しつつあるとも言われている。それは、例えば、非正規労働者の増大や一時期流行した「成果主義」に基づく評価・報酬制度の導入、また、日本の人口構成や社会的慣行の変化により、若年労働者が減少し高齢者が増加、あるいは、女性労働者が増加している等の構成の多様化も「日本的雇用システム」に大きな影響を与えていると言われている。 本書では、「日本的雇用システムを見通す」ことの意義として、(1)大局を見据えた政策形成を可能にするから(2)重要な労働法制と密接不可分の関係にあるから(3)人事労務管理・労使関係諸制度の現状と変化を総体的に把握できるから(4)海外に向けた情報発信力を高められるから、としている。 雇用システムは、個々の企業の労使の合意の集合体でもあるが、現実にはそれをサポートする、あるいは、それを前提とする労働法制(労働基準法制ばかりでなく労働組合法制・社会保険法制・労働保険法制・労働安全法制など幅広い)や労働政策・仕組み(労働基準監督署、ハローワーク、失業保険、職業訓練など、これも幅広い)、更には社会システム(例えば税制や教育システム)と密接に関係しながら成立しているし、また、財界(経団連とか)や労働組合(個々の労働組合ばかりではなく、連合などのナショナルセンターも)等が、法制や政策決定に影響を持っている。それだけ、社会に深く埋め込まれたシステムであり、また利害関係者も多く、従って、現状や将来に対しての客観的な分析・予測が必要になる。そういった役割を果たそうとするための組織であり、研究だ。 貴重な組織だと思うし、本書のような研究成果は貴重な情報だと思う。
Posted by 

