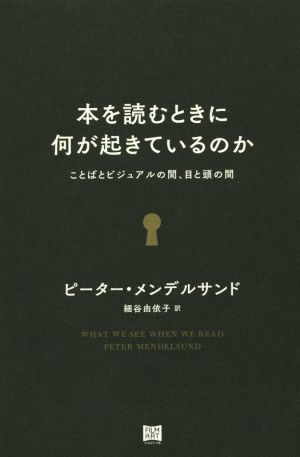
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1206-01-01
本を読むときに何が起きているのか ことばとビジュアルの間、目と頭の間
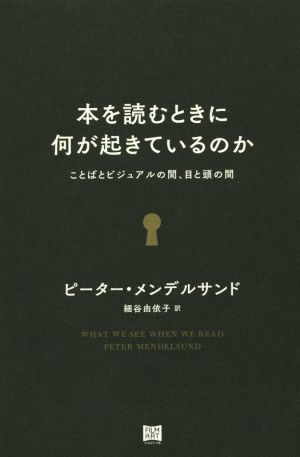
定価 ¥2,860
1,430円 定価より1,430円(50%)おトク
獲得ポイント13P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:12/13(土)~12/18(木)
店舗到着予定:12/13(土)~12/18(木)
店舗受取目安:12/13(土)~12/18(木)
店舗到着予定
12/13(土)~12/18

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
12/13(土)~12/18(木)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | フイルムアート社 |
| 発売年月日 | 2015/06/01 |
| JAN | 9784845914524 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
12/13(土)~12/18(木)
- 書籍
- 書籍
本を読むときに何が起きているのか
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
本を読むときに何が起きているのか
¥1,430
在庫あり
商品レビュー
3.6
40件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・ココで言う本は、小説のこと。 ・作家は書くときに要約し、読者も読むときに要約する。わたしたちは、要約して世界を理解する。 ・人は文脈を見て、描いて、思い出す作業をしている、読み進めながらそれを修正し続ける。アンナ・カレーニアの顔をイメージすることの例 ・物語を思い描くことは、絵の中で人物が陰にされてしまうように要約することである。そうすることで、意味を作り出す。 ・読書とは、文字を通して記憶と想像を呼び起こす行為
Posted by 
常識に囚われないような斬新な本。印象的なのは見開きでイラストや本の図解をしていて、我々が本を読む時の目線やぼんやりとした理解の表現に挑戦している事。例えば、文字がびっしりの小説を速読する時、細部のひらがなや情景描写などは飛ばして、漢字やセリフのやり取りの拾い読みになる事がある。そ...
常識に囚われないような斬新な本。印象的なのは見開きでイラストや本の図解をしていて、我々が本を読む時の目線やぼんやりとした理解の表現に挑戦している事。例えば、文字がびっしりの小説を速読する時、細部のひらがなや情景描写などは飛ばして、漢字やセリフのやり取りの拾い読みになる事がある。それを文字の塗り潰しや色の濃さ、イラストで再現されていて、言いたい事がよく伝わってくる。確かに我々の読書とは、解像度をいかに上げていくか、という作業でもある。 一つ気に入った表現があるので思い出しながら書き記したい。「アルファベットのDを反時計回りに90度回転せよ。その下にアルファベットのJを組み合わせ、天気をイメージせよ」。こうした文章から情景を思い描く所作が読解。読書では、常時こうした変換作業が求められる。 こうした試みでイラスト満載、文字少なめ(見開きで3行程度のページも多い)のため、分厚い辞書みたいな重量感だが、一時間程度で読み終える。読書に纏わるエピグラフも多く、読書好きには楽しい一冊だ。 ー 本の中で言及されている対象がわからない文章を読んでいる時、(不注意に一節読み飛ばしてしまった時など)、まるで、構造的には正しいが意味的には機能しない、意味のない「ナンセンス」な文章を読んでいるような気分になる。その文章は意味ありげな雰囲気を持っているため、意味深長に感じ、その文法の造が私を先へと押し進めるのだが、実際には私は何も理解していくして思い描けて)いない。このような、意味の保留は、読書中にどれくらいあるだろうか? ー 私たちは不完全な素描を完成させる。読書は素描行為のようなものであり、読みながら、内容の空白を埋めたり、ニュアンスをつけたり、色づけをしたりするのだ。私たちの思考は、共通点のない部品を統合して、単なる輪郭に過ぎなかったものから絵を描く(ここでは、意味としてのプロセスを説明するために視覚的な比喩を用いているにすぎないが)。
Posted by 
古い書評スクラップを見ていてほしくなった。買ってからもう一度読んでみようとしたがそれが見つからないったら見つからない(笑)どこ行った? 結局合わないので途中でやめた。
Posted by 
