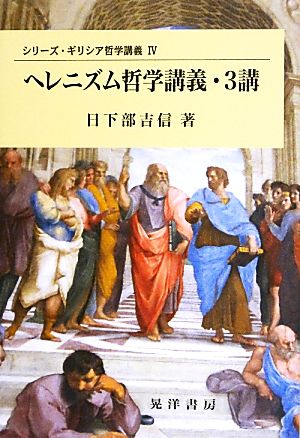
- 中古
- 書籍
- 書籍
ヘレニズム哲学講義・3講 シリーズ・ギリシア哲学講義4
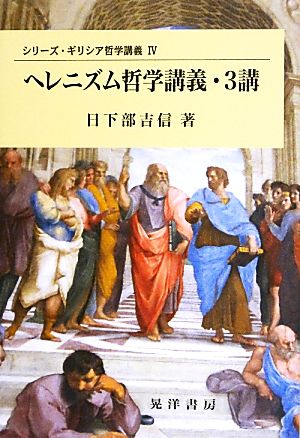
定価 ¥1,100
825円 定価より275円(25%)おトク
獲得ポイント7P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 晃洋書房 |
| 発売年月日 | 2013/04/11 |
| JAN | 9784771023680 |
- 書籍
- 書籍
ヘレニズム哲学講義・3講
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ヘレニズム哲学講義・3講
¥825
在庫なし
商品レビュー
4.5
3件のお客様レビュー
・ヘレニズムというのは一般にアレクサンドロス大王の死(前323年)からローマ共和制の終結(前31年のアクティウムの戦い)にいたるまでのほぼ三世紀にわたるギリシア・ローマ時代を言います。 ・ストア学徒によれば、それゆえ、世界は神々や人間や動物や植物や諸物によって構成されたひとつの...
・ヘレニズムというのは一般にアレクサンドロス大王の死(前323年)からローマ共和制の終結(前31年のアクティウムの戦い)にいたるまでのほぼ三世紀にわたるギリシア・ローマ時代を言います。 ・ストア学徒によれば、それゆえ、世界は神々や人間や動物や植物や諸物によって構成されたひとつの「巨大なポリス」なのであります。人間を男女の差、身分、家柄、貧富、国家といった違いを超え、さらにギリシア人や異民族といった民族的差異性をすら超えた「世界市民」として捉える世界市民主義がストアの世界観を貫く基調でした。 ・欲望をエピクロスは「自然的で、必須なもの」と「自然的ではあるが、必須ではないもの」と「自然的でも、必須でもないもの」とに区別しました。 ・「飢えない、渇かない、寒くないが肉体の要求であるが、これを満たさんとして、満たすにいたれば、人はゼウスとさえ幸福を競いうるであろう」
Posted by 
読みやすすぎるヘレニズム期。 「ストア派」「エピクロス派」に加えて「懐疑派」の3つの章立てでヘレニズム期を俯瞰する内容。 各派ごとに「論理、自然、倫理」の3つをおもに取り上げてあり、それら思想の違いや影響などが解説してあり単純に読み物としておもしろい。ストア派の「善・悪・どちら...
読みやすすぎるヘレニズム期。 「ストア派」「エピクロス派」に加えて「懐疑派」の3つの章立てでヘレニズム期を俯瞰する内容。 各派ごとに「論理、自然、倫理」の3つをおもに取り上げてあり、それら思想の違いや影響などが解説してあり単純に読み物としておもしろい。ストア派の「善・悪・どちらでもないもの」「(生や死などの)どうでもよいもの」なんかサラッと書いて終わる割にはこの書き方は心に残る。 とくに快楽主義としてのエピクロス派とキュレネ派との違いについての「倫理学」の解説がためになった。 エピクロス派の倫理について「感情(パトス)が教えるものは快か苦であって、それ以外のものではありません」と解説が始まって、 快を追求する→永続的な快の状態にはとどまれない→不快を感じる→煩わしい→「快を追及すると必然的に煩わしさを感じてしまう」なのでエピクロス派は「苦痛のない状態を快とする」。 このあたりがACT療法の考え方に近いのですね。 (というかACTがエピクロス派に近いのだが)
Posted by 
ヘレニズム期の哲学、ストア派、エピクロス派、懐疑派を中心に、学派の成り立ちやその学説が簡潔、かつ丁寧に解説されている。山川から出ている「世界史リブレット」と似たサイズ感で、頁はさほどの量もないが、要点が凝縮されている印象を受けた。各学派の研究の基本文献も紹介されている点も良い。...
ヘレニズム期の哲学、ストア派、エピクロス派、懐疑派を中心に、学派の成り立ちやその学説が簡潔、かつ丁寧に解説されている。山川から出ている「世界史リブレット」と似たサイズ感で、頁はさほどの量もないが、要点が凝縮されている印象を受けた。各学派の研究の基本文献も紹介されている点も良い。 ヘレニズム期といえば、美術好きとしては、異文化の化学反応による黄金期というイメージが先行するが、政治的には大混乱の時代であって、そうした背景の舞台にあがったのが、形而哲学ではなく、実践哲学であったという。著者はこう表現している。 「コスモポリタンとなって広大無辺な世界に投げ出され、拠り所を失った人々が必要としたものが、(中略)もっぱら個人の生き方に指針を与える主観的な実践哲学でしかなかった」。 また著者はマルクスの言葉を借りて、「広大な世界に投げ出されたとき、個人はむしろ自己を反省し、自己意識となる」とも指摘する。ヘレニズム哲学を代表する3学派がいずれもアパテイア(不動心)、あるいはアタラクシア(平静な心境)を目指したことが、その証左といえる。そして同様の社会不安が個人を飲み込まんとするとき、発現する。エピキュリアンとして、ガッサンディ、ディドロ、アナトール・フランス、マルクスの名が挙げられている。そういわれてみると、アナトール・フランスは『神々は渇く』で、ルクレティウスの詩に重大な役割を与えている。時代や国を超えた、普遍的な哲学ともいえる。私的真理を追求する姿勢は、しかし公的に生きんとするローマ人とはそりが合わず、ギリシアの衰退とローマの繁栄に比例して、その影響力を失っていった。 モンテーニュの『エセー』を読んだ際、しきりにストア派の学説が登場した。彼の生きた時代も、宗教内乱によって情勢は大混乱に陥っていた。彼が公的な場を早くに離れ、国家理性ではなく、一個人の真理を追求せんと隠棲したのは、ストア派を知る彼にとっては至極当然の成り行きだったようだ。 著者も指摘しているが、ヘレニズム哲学は決して古くない。おそらく現代でも、未来でも、多くの人が彼らの主張に賛同するだろう。現代哲学で提唱された理論が、すでにヘレニズム哲学に見出せる。本書が良き導き手となってくれたので、次はより専門的な概括本を読みたい。 追記: アナトール・フランス『神々は渇く』に登場するのはルクレティウスの詩ですが、当初思い違いでセネカと書いて投稿してしまいました。お恥ずかしながら、本書を読んではじめてアナトール・フランスがエピキュリアンだと知り、『神々は渇く』を再読しました。初読時、アナトール・フランスがルクレティウスの詩にどんな意味を込めているのか、非常に興味を持ちましたが、彼がエピキュリアンであったとわかり、なぜ彼がタイトルに「神々」les Dieux と記したのか、これはもちろん皮肉なわけですが、どうしてそれが皮肉なのかという理由の片鱗がみえたように思います。すなわち、ルクレティウスがうたうように、「神々」は人間の世界には存在しないにも関わらず、あるときは「神々」を創造して畏れ、またあるときはまるで自身が「神々」のひとりとなったかのように勘違いをし、無益な血を流す、その愚かさ。当時の革命家はあたかも神のように崇められていましたし、革命政府は実際にギリシア ・ローマの神々に似せて、新たな祝祭、新たな宗教をつくろうとしていました。そしておそらくは、国家理性の暴走による個人の消失の恐ろしさも。しかし理解はまだ浅いでしょうから、まずは『エピクロスの園』を読んでみたいと思います。
Posted by 



