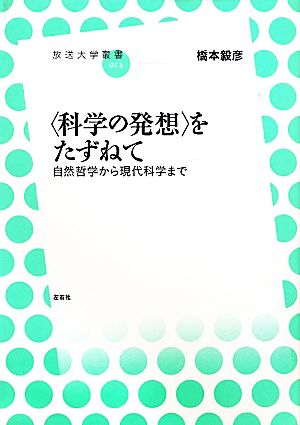
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1213-01-00
“科学の発想"をたずねて 自然哲学から現代科学まで 放送大学叢書012
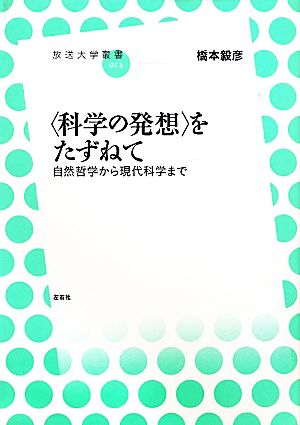
定価 ¥1,780
1,210円 定価より570円(32%)おトク
獲得ポイント11P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 左右社 |
| 発売年月日 | 2010/10/15 |
| JAN | 9784903500423 |
- 書籍
- 書籍
“科学の発想"をたずねて
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
“科学の発想"をたずねて
¥1,210
在庫なし
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
1. 明治政府と西洋科学の導入 - 明治政府は開国し、文明開化を図るために西洋の学問を積極的に導入した。 - 東京大学の前身である教育機関に、多くの外国人教師が招かれ、西洋の学問や技術が教授された。 2. ベルツの科学観 - ベルツは日本に滞在し、西洋の科学の本質について異なる...
1. 明治政府と西洋科学の導入 - 明治政府は開国し、文明開化を図るために西洋の学問を積極的に導入した。 - 東京大学の前身である教育機関に、多くの外国人教師が招かれ、西洋の学問や技術が教授された。 2. ベルツの科学観 - ベルツは日本に滞在し、西洋の科学の本質について異なる見解を持っていた。 - 日本人は西洋の科学を「機械」として理解しているが、ベルツはそれを「生命」と捉え、科学の成長には特定の気候や大気が必要だと述べた。 3. 科学の発展とその背景 - 西洋の科学の精神は、古代ギリシャの哲学者たちの努力によって育まれた。 - 科学は単なる機械的な働きではなく、自然の探求と世界の謎の解明を目指す精神的な活動である。 4. 研究者の精神 - 科学研究は整然とした順序で進行しないことが多く、問題設定や理論構築は雑然とした環境の中で行われることがある。 - 研究者はさまざまな角度から厳しいチェックを行い、新たな理論を生み出していく。 5. ギリシャ科学の起源 - ベルツは古代ギリシャが科学の発達において重要な役割を果たしたことを強調した。 - アリストテレスなどの哲学者が、科学の基礎を築くための知識体系を整理し、自然を探求するための概念を提供した。 6. 中世から近代への移行 - 中世哲学者たちはアリストテレスの自然学を基に研究を進めたが、デカルトの機械論的自然観が台頭する。 - ニュートンは万有引力の法則を提案し、デカルトの理論を超える新たな自然観を示した。 7. 近代科学の発展 - 19世紀には化学の近代化に取り組む科学者たちが登場し、特にリービッヒが有機化学の発展に寄与した。 - 有機物質の化学的組成の決定に挑戦する中で、合成染料の発明などが行われた。 8. 量子力学の誕生 - 20世紀に入ると、量子力学が新たな物理学として確立され、特にボーアの原子論が注目された。 - 波と粒子の二重性が理解されるようになり、物理学の根本的な考え方が変わった。 9. 科学研究の変化 - 20世紀の科学研究は、組織や制度、資金など物質的な環境が重要であることが明らかになった。 - 科学の成長には、精神的な「大気」と物質的な「土壌」の両方が必要であるとした。 10. 現代科学の課題 - 科学は大きな成果を上げた一方で、生命を脅かす技術も生み出している。 - ベルツが提起した「生命体としての科学」の概念は、現代においても考察され続けている。
Posted by 
本書は、冒頭のドイツ人医学者、ベルツの印象的なスピーチから始まる。「私の見るところでは、西洋の科学の起源と本質の関して日本人では、しばしば間違った見方がとられているように思われます。日本の人々はこの科学を、一年にこれだけだけの仕事をする機会であり、どこか他の場所へたやすく運んで、...
本書は、冒頭のドイツ人医学者、ベルツの印象的なスピーチから始まる。「私の見るところでは、西洋の科学の起源と本質の関して日本人では、しばしば間違った見方がとられているように思われます。日本の人々はこの科学を、一年にこれだけだけの仕事をする機会であり、どこか他の場所へたやすく運んで、そこで仕事をさせることのできる機械であると考えています。これは誤りです。西洋の科学の世界は決して機械ではなく、一つの生命なのでありまして、その成長には他のすべての姓名と同様に一定の気候、一定の大気が必要なのであります。」このスピーチに本書で作者が述べたかったこと全てが詰まっていると感じる。科学の成長は、時代背景、特にその時代の哲学感に影響を受けてきた。特に、第二次世界大戦時期の原爆の開発と、世界の動向が印象的だった。 もしあの時代に、原爆の開発がなされていなかったら、広島に原爆は投下されていなかっただろうか、と考えると、タイミングというものの不思議さに恐ろしさを覚える。
Posted by 



