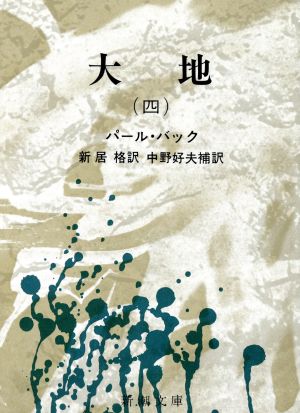
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1225-16-06
大地(4) 新潮文庫
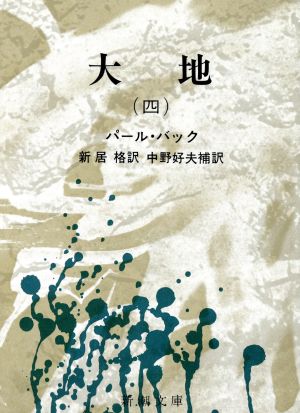
定価 ¥825
440円 定価より385円(46%)おトク
獲得ポイント4P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 新潮社/新潮社 |
| 発売年月日 | 1982/10/01 |
| JAN | 9784102099049 |
- 書籍
- 文庫
大地(4)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
大地(4)
¥440
在庫なし
商品レビュー
4
32件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
解説に曰く、猛がはじめ身を投じたのは国民党で、それに失望して共産党に鞍替えしたらしい。『The Good Earth』につづく二部目『Sons』の発表が1932年で、三部目『A House Devided』の発表が1935年らしいが、その時ですでに国民党や共産党などを認識していたのは脱帽もの。 淵も美齢も、その共産党が奠都した先で、自らの人生を切り拓いていこうという夢を本巻後半で語っているが、その後の共産党もまた歴史の繰り返しに過ぎなかったという歴史の皮肉。作中で猛の"崇高な"理想をきかされた淵自身が、そんなことは今まで主君が易るたびにきかされてきたことだと皮肉っていたのに、幕引きの直前に、美齢の抱負をきかされて変心しているあたり、やはり淵は信用できない。笑 思えば、三巻、四巻と、いづれも主に淵を中心として物語が展開されてきたが、淵の考えに筋らしい筋もついぞ見出せぬまま、幕引けと相なってしまった。個人的には美齢と最後に結ばれたオチが非常に残念。心変わりが劇しく、自己中心的で、世間知らずで、信念もない上に、好きな女一人碌に大事にできず、好きだ好きだの一点張り攻勢で女を口説けると思っている頭の弱い中二病。美齢ともあろう賢女がなにゆえここにきて眼が利かぬ。作者の新時代に対する期待感を無理やりに押しつけられたとしか思えない。 そうとはいえ、人間に対する観察眼や、情勢を悟る肌感、そして中国への理解はやはりいづれもピカイチ。 p.173 ……紅梅は春、白百合は夏、黄菊は秋、雪の下に赤い実をつけている万年青(おもと)は冬を代表していた。 【疑問】日本では万年青は秋の季語になっているらしいが、中国では冬なのか。しかも『大辞林』には常緑多年草と説明がある。
Posted by 
王虎の息子淵の半生が語られる。 死刑を免れ窮地を脱して留学した外国(米国)での六年間は彼にとっては先進文明を体感し、「大学の講義を受け、図書館に行って書籍に埋まって読み・書き抜き・思索に耽る」ことのできた素晴らしい時間であった。従兄弟たちは新しい時代を満喫し恋愛やダンスに興じるな...
王虎の息子淵の半生が語られる。 死刑を免れ窮地を脱して留学した外国(米国)での六年間は彼にとっては先進文明を体感し、「大学の講義を受け、図書館に行って書籍に埋まって読み・書き抜き・思索に耽る」ことのできた素晴らしい時間であった。従兄弟たちは新しい時代を満喫し恋愛やダンスに興じるなか、淵は学問に没頭し尊敬する老教授一家に迎えられ、娘のメアリーと意気投合するが一線は守る。 故郷に帰り、久しぶりに見た父王虎は無残に老いさらばえていた、又淵のために王ニから巨額の借財を重ねたことも知らされ返済を約す。母が引き取って育てた孤児の美齢を見初め恋に落ちる。従兄弟猛の手引きで革命政府の大学教授になり学生の教育に勤む。故郷の家で美齢とともに父の往生を看取る。新しい時代の到来で混沌のなか昔からの慣習や思潮との狭間を美齢と一緒に切り拓いていくことを決意する。この大河小説の幕引きである。 中国大陸で水呑百姓から大地主になり、子孫がその財産をもとに商人・高利貸しや軍人に、そしてその子が大地を耕す農業の研究者・教師になるという王家一族の三代にわたる顛末である。 当たり前のことであるが、勤勉や努力そして他への誠実と愛という人にとって必須の普遍的な価値が社会や時代の激動に打ち勝つということを言いたかったのであろう。イデオロギーより人道の話であり、中国大陸に生涯を尽くした「戦う宣教師」の父、その娘パール・バックの渾身の大作である。ノーベル賞も宜なるかなだ。 ともに働き抜いた妻の阿蘭から三番目の妻となる梨花、そして淵と結婚する美麗への世代を超えた連なりがこの小説を貫く芯棒となり、人間の未来への希望を感じさせる。
Posted by 
いつか読みたいと20年思い続けていた宿題を、ようやく読むことができた。知らなければ、白人が書いた作品だとは到底思えない。激動の時代におけるミクロな生活の描写力や東洋的価値観への理解度もさることながら、それらに対する潜在的な人種的優越感がまったく感じられないことに感動した。中国育ち...
いつか読みたいと20年思い続けていた宿題を、ようやく読むことができた。知らなければ、白人が書いた作品だとは到底思えない。激動の時代におけるミクロな生活の描写力や東洋的価値観への理解度もさることながら、それらに対する潜在的な人種的優越感がまったく感じられないことに感動した。中国育ちとはいえ、時代的にも、なかなかできることではないと思う。土に振り下ろされる鍬の音が聞こえてくるような、骨太な大河小説。堪能した。
Posted by 



