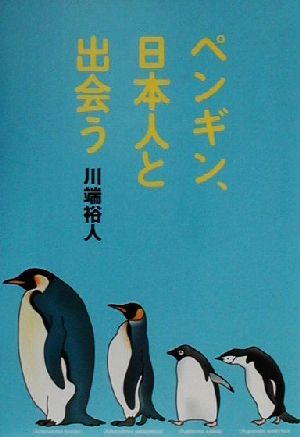
- 中古
- 書籍
- 書籍
ペンギン、日本人と出会う
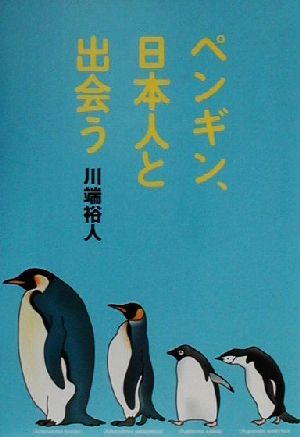
定価 ¥1,885
880円 定価より1,005円(53%)おトク
獲得ポイント8P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 文藝春秋/ |
| 発売年月日 | 2001/03/20 |
| JAN | 9784163572000 |
- 書籍
- 書籍
ペンギン、日本人と出会う
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ペンギン、日本人と出会う
¥880
在庫なし
商品レビュー
4.5
10件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
日本人がどうしてこんなに「ペンギンかわいいよペンギン」なのかがつぶさに明かされていく前半は特に面白かった。とはいえ2000年ごろの話なので、後発の関連書も探して読んでみたい。
Posted by 
ペンギンという動物は万国共通で親しみを感じる動物だと思っていましたが、どうも日本が飛びぬけて彼らを好きらしいです。 好きと言うのは「可愛い」という事が一番の原因であって、それほど彼らの生態や行動に関心があるわけではありません。 動物園に行けば一定数必ず張り付いたように、彼らの一挙...
ペンギンという動物は万国共通で親しみを感じる動物だと思っていましたが、どうも日本が飛びぬけて彼らを好きらしいです。 好きと言うのは「可愛い」という事が一番の原因であって、それほど彼らの生態や行動に関心があるわけではありません。 動物園に行けば一定数必ず張り付いたように、彼らの一挙手一投足から目を離せず歓声を上げる人々がいます。そう、それが私だ。 そのペンギン熱に一役買ったのが、戦後のタンパク質や油脂の製造に大貢献した捕鯨船です。お土産に持ち帰ったペンギンを動物園で見ることが出来るようになり、次第にペンギンの愛らしさが浸透して、世界でも有数のペンギン飼育大国になったというのが実情のようです。 ピングーの意匠使用件数も世界一、CMでも過去色々なペンギンアニメーションが使われていた記憶があります。JRのスイカもペンギンのキャラクターです。 昔は野生動物に対する考え方も緩く、簡単に捕まえられるから捕まえて船倉に入れて持って帰ってくるという、今では考えられないような捕獲方法だったようです。当然愛着を持って接していた人は沢山いたのでしょうが、その土地に生きている生物を持って帰ってくるということは、とても残酷な事だと思います。 実際意識が低い時代は、殴り殺してはく製にして持ち帰ったりもしていたようで、非常に悲しい思いがしました。 コミカルな動きで癒されるのですが、彼らは純然たる野生動物です。本当はその土地の厳しい環境で生きて死んでいくのが一番幸せに決まっています。 後半ではそんなペンギンたちを守る為に、日本のペンギンファンたちが「ペンギン基金」「ペンギン会議」を作って国際的な活動に発展していく所まで書かれています。 これによって、可愛いから飼うという無邪気で残酷な状況からはなんとか脱しているようでした。 ただし、読んでいて思ったのは、昨今の野生動物飼育ブームについても、何らか意識改革か規制が出来ないものがと思います。特にフクロウやみみずくの猛禽類を飼う事に関してはどうしても承服できません。ペットショップで見ましたが本当にかわいいです。欲しくなる気持ちは十二分に分かります。でもそこをぐっとこらえる事が必要ではないでしょうか。 固い話ばかりですが、グリーンガムやサンスター、サントリーの懐かしいペンギン等々、本当に日本人はペンギンが好きですよね。動物園や水族館でその姿を見るとその愛らしさに癒されるのは確かです。でももうどこかから連れてこなくてもいいです。今いる子たちを大事に飼育していって欲しいです。
Posted by 
ヒトとペンギンの関わり方について、平易な文章で興味深くつづった書。 日本人が北半球随一の「ペンギン好き」であることやその理由などから始まり、どのようにして水族館などにペンギンが届けられたのかということや、ペンギンを取り巻く研究者とその活動、「ペンギン基金」「ペンギン会議」などを紹...
ヒトとペンギンの関わり方について、平易な文章で興味深くつづった書。 日本人が北半球随一の「ペンギン好き」であることやその理由などから始まり、どのようにして水族館などにペンギンが届けられたのかということや、ペンギンを取り巻く研究者とその活動、「ペンギン基金」「ペンギン会議」などを紹介していく。 学術書というよりも、「読み物」に近く、スラスラと読むことができる。
Posted by 



