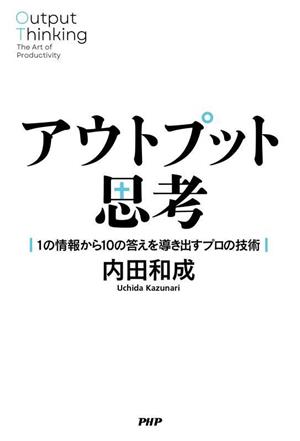アウトプット思考 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
インプット→アウトプット、では成果が出ない。普通の人がやることだから。 レースが終わってから馬に掛けることはできない=完璧な答えを探してインプットすることは不可能。 仕事と作業の区別をする。作業は減らす、仕事は減らさない。 3割の情報で意思決定する訓練。 情報整理はアナログでいい。箱に入れてしばらくして見直す。すぐには整理しない。20の引き出しで整理する。 キョロキョロする好奇心=電車通勤でいろいろなものを見る。
Posted by
この本で共感できたこととしては、 「一次情報を大事にする」ということ。 現代では情報化が進み二次情報で溢れかえっている。そのためインプット偏重では他の人との差別化が出来ず、自分の価値を見出すことが困難になる。 あえて情報源をアナログにしたりなど、情報のエントロピーをマイナスにする...
この本で共感できたこととしては、 「一次情報を大事にする」ということ。 現代では情報化が進み二次情報で溢れかえっている。そのためインプット偏重では他の人との差別化が出来ず、自分の価値を見出すことが困難になる。 あえて情報源をアナログにしたりなど、情報のエントロピーをマイナスにする意識が重要だと感じた。
Posted by
2023年現在の、内田和成さんの仕事術という感じの書籍。本質的な内容だけでなくTips的な内容もある。他の『○○思考』シリーズよりはライトでさらりと読めると思う。現代人はインプット過多、アウトプットを先にすべきというのはまったくそう思う。先に読んだ『だから僕は、ググらない』に共通...
2023年現在の、内田和成さんの仕事術という感じの書籍。本質的な内容だけでなくTips的な内容もある。他の『○○思考』シリーズよりはライトでさらりと読めると思う。現代人はインプット過多、アウトプットを先にすべきというのはまったくそう思う。先に読んだ『だから僕は、ググらない』に共通する部分も多い。 (とはいえ自分の最近の耳読書習慣もインプット偏重だなあという自己矛盾。とりあえず頭の引き出しに放り込んでおくことにする)
Posted by
前半は情報の整理の仕方。 後半はそのための具体的な方法の提示。 前半は参考になるところもあるが、後半は人によると思う。
Posted by
アウトプットのためにどう情報を仕入れ、解釈して差別化したアウトプットに繋げるか、が解説されている。大変読みやすいが、その分内容が浅く、それで?と思ってしまう。
Posted by
感想 逆算する。何を作りたいかを考えて情報を取り入れる。取り入れる量でAIに勝つなんて不可能。ではどうするか。アウトプットの質で勝つしかない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
アウトプットを基準に考える、というもの? インプットにはそこまで価値はなく、アウトプットにこそ価値がでてくる。 そして、インプット→アウトプットの順番を逆にし、アウトプットしてから、足りない情報をインプットしていく方がいいという。 情報を入れすぎると判断に迷いが生じることもあり、インプットは必ずしも良いことではない。 多すぎる本を読んでいたら、気づけば何年も経っていた今の自分の状況に刺さる本だった。 集めすぎて不自由になっていたのか、ただのマニアに近づいただけだったのか。 情報収集だけでは、頭のいい人には絶対に叶わない。頭のいい人に勝つには、知らないことは知らないといい、とにかくアホになりきり行動量を増やすしかないんじゃないかと思うようになってきた。 インプットは一次情報にも価値はあり、本だけが全てではないと知った。行動、行動。
Posted by
アウトプット思考。よくありそうな思考術の類であり、一種のハウツー本。ここですべての考え方を網羅することはできないが、特に現場に足を運び、様々なプロフェッショナルと「雑談」することが重要であるということや、雑談を重ねるうちに、経験や知識が積み上がり、良いアウトプットが生み出せるよ...
アウトプット思考。よくありそうな思考術の類であり、一種のハウツー本。ここですべての考え方を網羅することはできないが、特に現場に足を運び、様々なプロフェッショナルと「雑談」することが重要であるということや、雑談を重ねるうちに、経験や知識が積み上がり、良いアウトプットが生み出せるようになること。また、ネットワークを広げることで、さまざまな情報に触れる機会が増え、より多角的な視点で物事を捉えることができるようになるということは、当たり前のようではあるが、読んでいて納得感が得られた。
Posted by
アウトプットを意識して、効率的にインプットしていく。インターネット時代ではインプットの差はつかない。それより情報過多に対して、何をアウトプットするために、情報を得るのか、逆算が重要だと。 アウトプットに慣れるため、少ない情報で意思決定をする機会を設ける。頭の中にレ点をつける(意識...
アウトプットを意識して、効率的にインプットしていく。インターネット時代ではインプットの差はつかない。それより情報過多に対して、何をアウトプットするために、情報を得るのか、逆算が重要だと。 アウトプットに慣れるため、少ない情報で意思決定をする機会を設ける。頭の中にレ点をつける(意識するだけで必要な情報が目につく)。頭の中に20個程度の引き出しを持ち、ネタを収納する。 インプット→分析•加工→アウトプット。この分析•加工も大切。
Posted by
『#アウトプット思考』 ほぼ日書評 Day750 内田和成氏も随分と軽い本を書くようになったものだ。2011年の『プロの知的生産術』に大幅加筆訂正をしたものとのことだが…。 アナログを大事にしろとか、友達を大事にしろとか、もちろん間違ったことを言ってるわけではないが、金を払...
『#アウトプット思考』 ほぼ日書評 Day750 内田和成氏も随分と軽い本を書くようになったものだ。2011年の『プロの知的生産術』に大幅加筆訂正をしたものとのことだが…。 アナログを大事にしろとか、友達を大事にしろとか、もちろん間違ったことを言ってるわけではないが、金を払ってこの内容では、かなり寂しい。 唯一面白いと思ったのは(著者の発案ではないようだが)「情報とはマイナスのエントロピー」という表現。 いわく、エントロピーを減少すればするほど、事象の確実性は高まる。膨大な情報の中から、何が「エントロピーを減少させる情報かを考える」ことが、意思決定のための情報収集の助けとなる。 一方で、時は金なりで、いかに少ない情報だけで正しい判断を下せるかが、優秀なリーダーの条件となるのである。 https://amzn.to/3SedLfS
Posted by