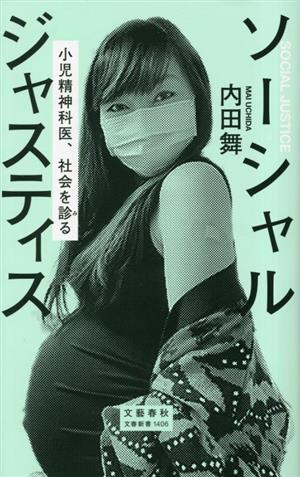ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る の商品レビュー
社会的に、私的に、さまざまなことを感じた後だからこそ、読む価値のあった本。これを読んで変わってくれる人がどれだけいるのか、そもそも読んでくれる人がいるのか、想像すると少し悲しくもなる。社会科学の側面からも、こうした書籍の大切さが広く理解されることを願う。
Posted by
信じたい、そうであってほしいものを事実として認識してまう 感じるままではなく、感じたものを頭で考えて行動したい
Posted by
中田敦彦さんとのYouTube共演の動画をきっかけにこの本を知りました。全章有益で面白かったです。日常で気になったことがあっても名前を付けて考えたことのない社会的問題が挙げられており、大変共感しました。医学的・科学的根拠のもと、努力して培った女性の発言に励まされ得るものの多い書で...
中田敦彦さんとのYouTube共演の動画をきっかけにこの本を知りました。全章有益で面白かったです。日常で気になったことがあっても名前を付けて考えたことのない社会的問題が挙げられており、大変共感しました。医学的・科学的根拠のもと、努力して培った女性の発言に励まされ得るものの多い書でした。
Posted by
悪気なく、気づかない発言で、他人を傷つける可能性がある。時代背景や文化によっても、その内容は異なってくる。そんな時の身の守り方なども書かれている。「再評価」はその中でも効果的、リフレーミングのような物かな、と。 本の中身的には横文字が多く、苦手な自分としては、何度も前のページを見...
悪気なく、気づかない発言で、他人を傷つける可能性がある。時代背景や文化によっても、その内容は異なってくる。そんな時の身の守り方なども書かれている。「再評価」はその中でも効果的、リフレーミングのような物かな、と。 本の中身的には横文字が多く、苦手な自分としては、何度も前のページを見返してしまった。笑
Posted by
ぐうの音も出ないほどの優秀さに頭が下がる思い出いっぱいだった。この境地にたどり着くまでにどれだけの努力と経験を積み重ねてきたのだろう。決して相手を否定せず、相手がどんな立場でどういったプロセス・方法で語り、その危険性は何かを悟し、そっと処方箋を置いていく。 最高にエレガントな...
ぐうの音も出ないほどの優秀さに頭が下がる思い出いっぱいだった。この境地にたどり着くまでにどれだけの努力と経験を積み重ねてきたのだろう。決して相手を否定せず、相手がどんな立場でどういったプロセス・方法で語り、その危険性は何かを悟し、そっと処方箋を置いていく。 最高にエレガントな人だと思う。 これを全員が考えられるようになることは100% 不可能だし、そもそも相手にする必要はないと思ってしまう。しかし、それでも今後の社会をよりよく残していくために考え、厳しくもちゃんと伝えていく精神。 それは世阿弥が能をいかに現代に残すか考え、模索する姿に近いものを感じる。
Posted by
⚫︎感想 大切だと思ったフレーズ 「言語化できない違和感に言葉(名前)を与えることで、自分や相手の感情や考えを明確化すること。論理の整理は自分の心を守ってくれる強い鎧となってくれる。」 ホワットアバウティズム ストローマンストラテジー ガスライティング …などの様々な論理のすり替...
⚫︎感想 大切だと思ったフレーズ 「言語化できない違和感に言葉(名前)を与えることで、自分や相手の感情や考えを明確化すること。論理の整理は自分の心を守ってくれる強い鎧となってくれる。」 ホワットアバウティズム ストローマンストラテジー ガスライティング …などの様々な論理のすり替えの手法を紹介してくれる。たしかに言葉を与えると、今相手はホワットアバウティズムで私を打ち負かそうとしているな…と対応できるが、知らなければ、言葉に詰まることもあるかもしれない。 正しく「知る」、論理的に頭を整理することは 物事に対して自分の考えを持ち、尚且つ柔軟に対応するための唯一の方法だと思った。 また、小説のことも連想した。 言葉にならない感覚を、小説も示してくれるからだ。小説を読むこともまた、人を強くしてくれるのだと思う。 ⚫︎あらすじ(本概要より転載) 恐れず変化の種をまくために。 炎上や論破ゲームに乗らず、 分断と差別を乗り越えるためには。 ハーバード大学准教授で小児精神科医・ 脳科学者でもある著者が、心と脳のメカニズムに立ち戻り、 激動の時代のアメリカ社会の変化を捉え、 三人の子どもを育てる母親の立場から考える希望の書。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー プロローグ 妊婦のワクチン啓発で気づいたThemとUs 第I部 炎上はなぜ起きるのか 第1章 脳科学で考える炎上のメカニズム 第2章 炎上への処方箋 第II部 差別と分断を乗り越えるために 第3章 子どもに学ぶ同意とアドボカシー 第4章 マイクロアグレッション ムズムズした気持ちに名前がつくことで 第5章 アメリカ社会の差別から学ぶ アジア人男性とハリウッド 第6章 ベトナム帰還兵との対話 ThemとUsは簡単には分けられない 第7章 沈黙を破る 「沈黙は共犯」の後で 第III部 女性小児精神科医が考えた日本社会への処方箋 第8章 子どものメンタルヘルスに向けられる偏見に打ち勝つ脳科学 第9章 女性を苦しめる労働環境は男性をも苦しめる 第10章 「母」への眼差し、女性の身体の自己決定権 エピローグ ラジカル・アクセプタンス ソーシャルジャスティスを育てるために
Posted by
日本社会に存在する目に見えない偏見や差別、抑圧などについて、海外に出たからこそ得られた客観的な視点で書かれていると思った。社会の分断にどうやって立ち向かえば良いのか、その考え方も極めて冷静沈着。RBGの本を読んだときのように、社会にインパクトを与える真の知性とはこういうものだと、...
日本社会に存在する目に見えない偏見や差別、抑圧などについて、海外に出たからこそ得られた客観的な視点で書かれていると思った。社会の分断にどうやって立ち向かえば良いのか、その考え方も極めて冷静沈着。RBGの本を読んだときのように、社会にインパクトを与える真の知性とはこういうものだと、尊敬しかない。 SNS炎上で見られる論理のねじれ、同意とアドボカシー、マイクロアグレッション、ラジカルアクセプタンスなどなど、この本で初めて知った概念は数知れず、もっともっと勉強したいなと思わされた。最後の旦那さんとのエピソードなども、愛情豊かな人柄が感じられてほっこり。
Posted by
再評価とは、 ネガティブな感情を感じた時に一旦立ち止まり、その感情を客観的に再度 「本当に今このような感情を感じる必要があるのか」を評価して、 感情や状況をポジティブな方向に持っていくプロセスのこと。 顔の見えないsnsの世界で 他者を攻撃する前に自分の感情と向き合う事が大切だと...
再評価とは、 ネガティブな感情を感じた時に一旦立ち止まり、その感情を客観的に再度 「本当に今このような感情を感じる必要があるのか」を評価して、 感情や状況をポジティブな方向に持っていくプロセスのこと。 顔の見えないsnsの世界で 他者を攻撃する前に自分の感情と向き合う事が大切だと思う。 再評価、ぜひ実践していきたい。
Posted by
脳科学者で小児精神科医で3児の母である米国在住の著者の視点から、SNSなどでの炎上のメカニズムや人種差別、男女の役割の押し付け、子供のメンタルヘルスについて実例を示しつつ、どうやって解消していったらよいか述べられている。個人的には、正しいと思って戦地に行ってやったことでずっと後悔...
脳科学者で小児精神科医で3児の母である米国在住の著者の視点から、SNSなどでの炎上のメカニズムや人種差別、男女の役割の押し付け、子供のメンタルヘルスについて実例を示しつつ、どうやって解消していったらよいか述べられている。個人的には、正しいと思って戦地に行ってやったことでずっと後悔し、それが自身の生活の妨げになっていたベトナム帰還兵との対話のシーンが非常に印象的だった。自分と他者の個を尊重し、無意識のうちに行われていることを認識し、理解すること。それが正しいことか再評価すること、そこからやってみようと思う。
Posted by
著者は妊娠中に新型コロナワクチンを接種したことをSNSに投稿して話題となったアメリカの小児精神科医である内田舞さん。ハーバード大学医学部准教授、マサチューセッツ総合病院小児うつ病センター長の肩書も持ち、三児の母でもある。 「炎上」のメカニズムを様々な名前で分類していて興味深かっ...
著者は妊娠中に新型コロナワクチンを接種したことをSNSに投稿して話題となったアメリカの小児精神科医である内田舞さん。ハーバード大学医学部准教授、マサチューセッツ総合病院小児うつ病センター長の肩書も持ち、三児の母でもある。 「炎上」のメカニズムを様々な名前で分類していて興味深かった。承認欲求をも脳科学的に説明されている。 Whataboutism(そっちこそどうなんだ主義)、Strawman Strategy(かかし術)、Gaslighting(悪いのは被害者?)、Ad Hominem(人格を否定することで、その人の意見を否定する)など、なるほどあれはそういうことだったのかと理解できた。 また、ドラえもんのしずかちゃんを理想像として描く日本の女性感への違和感から日本を飛び出してアメリカで働くことを選んだこと、「女性が働きやすい」という言葉が「女性が育児をしやすい」と同義に使われていることの裏には女性が育児をやるべきという無意識のロールの押しつけがあること、「男並みに働く」の「男並み」という言葉は「家事や育児をすべてやってくれる妻がいる男性と同じだけの時間、仕事にコミットできるという意味だということ」など、日本の女性が置かれた立場について明快に問題点を指摘していることにも感銘を受けた。
Posted by