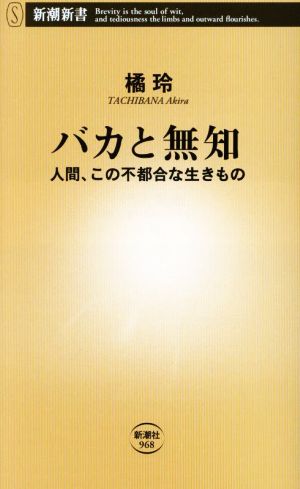バカと無知 の商品レビュー
バカは気付かない
人間にはバカだと思われないようにする防衛本能がある、それじぁあ仕方が無いと思ってしまった。
にょろ
本屋でよく目にしていた本ですが、煽り感の強いタイトルが苦手でなかなか手に取れませんでしたが、特にバカと書かれていることが悲しくなるというかなんというか。人を見下すような内容なのでは…と思いましたが,違いましたね。 時々、主観的かな?ということも書かれてはいますが、男と女の違いは生...
本屋でよく目にしていた本ですが、煽り感の強いタイトルが苦手でなかなか手に取れませんでしたが、特にバカと書かれていることが悲しくなるというかなんというか。人を見下すような内容なのでは…と思いましたが,違いましたね。 時々、主観的かな?ということも書かれてはいますが、男と女の違いは生物学的に証明されているわけだから、それによって価値観も全く違ってくるというような内容にはとても納得できました。その他にも「偏見」について、偏見をもつなと教育されるよりも、無意識であるほうが偏見は少ないのかもしれないということ。それから、記憶は流動的で、完全に完璧にインプットされているわけではないこと。 など、興味深いことがたくさん書かれていました。 呼んでいる間は驚きがいっぱいで刺激的でしたが、こういった本は私はどうしてもすぐに忘れてしまうので、また日を改めて読みたいです。
Posted by
すごく面白い内容でした。 一般ではあまり見聞きできないような実験的な事実が色々と書いてあり、何だか人間って愚かだなとかおかしいなとか考えながら読めました。 内容は行動心理関係が多く、もう忘れてしまっていることもあるので何度も読み返したいなと思います。
Posted by
タイトルが過激で気になり読みました。 内容は、きれいごと社会の残酷な現実が書かれています。 三人集まれば文殊の知恵という諺があるが、これには、新たな知恵が出てくるのためには条件があることなど今までに知らなかったことを科学的環境をつけて説明されていて、非常に納得させられることば...
タイトルが過激で気になり読みました。 内容は、きれいごと社会の残酷な現実が書かれています。 三人集まれば文殊の知恵という諺があるが、これには、新たな知恵が出てくるのためには条件があることなど今までに知らなかったことを科学的環境をつけて説明されていて、非常に納得させられることばかりでした。
Posted by
言ってはいけないことだらけの本。 みんながうっすら感じてるけど、言葉にしちゃいかんだろ、ってことをあえて言語化していく、そんな本。 また、この本ではあらゆる苦しみの根源がリベラルであると論じている。 筆者曰くリベラルとは、「この世に生を受けた以上、自分の人生は自分で決めたい」「...
言ってはいけないことだらけの本。 みんながうっすら感じてるけど、言葉にしちゃいかんだろ、ってことをあえて言語化していく、そんな本。 また、この本ではあらゆる苦しみの根源がリベラルであると論じている。 筆者曰くリベラルとは、「この世に生を受けた以上、自分の人生は自分で決めたい」「自分らしく生きたい」という価値観のこと。 これの“おかげで”人生が豊かになったという捉え方をする人が多いと思うが、筆者はこれの“せいで”生きづらさが出てきたという。 (こちらの詳細は改めて記載予定) ▼言ってはいけないことの一例 -- 「女は男より数学が苦手だ」というのは典型的なステレオタイプで、ずっと批判されてきた。だがその一方で、「生まれたばかりの赤ちゃんでも、男の子はモノに、女の子はヒトに興味を示す」とか、「男の言語能力は左脳に偏り、右脳を論理・数学的な処理に使っているが、女は左脳だけでなく右脳も使って言語処理をしている(したがって女の方が言語能力が高い)」などの生物学的な説明がなされている。 --
Posted by
バカの問題は、自分がバカであることに気づいていないことだ。 ほとんどの人がほとんどの分野において「たいていの人よりは上である。すなわち平均より自分は上だと思っている」 たいていのことは人よりうまくできるというアンケートに、とてもそう思うと答え続けてきた自分も危ないなと思った。 様...
バカの問題は、自分がバカであることに気づいていないことだ。 ほとんどの人がほとんどの分野において「たいていの人よりは上である。すなわち平均より自分は上だと思っている」 たいていのことは人よりうまくできるというアンケートに、とてもそう思うと答え続けてきた自分も危ないなと思った。 様々な研究を根拠に自説を述べている。 集団に対してえこひいきしてしまう習性を利用するために、何が何でも身内側になったほうがいいということが分かった。 壁シリーズとか似たようなことを多く読んできたため、特に新しい発見はなかったように思える。
Posted by
『バカはバカであることに気づけない』 自分の常識だけでなく、自分の経験からなる記憶にまで疑いを向けなければいけない。脳はそのくらい適当らしい。 だけれどその欠陥を認識しているのとしていないとでは天地の差だろう。自分の意見ではなく時に真逆の他人の意見にも耳を傾けることが出来るよ...
『バカはバカであることに気づけない』 自分の常識だけでなく、自分の経験からなる記憶にまで疑いを向けなければいけない。脳はそのくらい適当らしい。 だけれどその欠陥を認識しているのとしていないとでは天地の差だろう。自分の意見ではなく時に真逆の他人の意見にも耳を傾けることが出来るようになればまずバカであることに気づくための1歩かもしれない。 他にも本書では差別はなぜ生まれるのかについて生物学的に説明される。だからしょうがないとはならないがこの世界の地獄について整理されたひとつの補助線を引くことが出来る。 この世界に事実はなく、解釈があるだけだと誰かが言っていたが物の見方のレパートリーを増やしたいと思う人にはおすすめの著書です。
Posted by
作者の頭の中では繋がっているのだろうけど、いろんな情報をポイントでまとめられていて、ぶつぶつと書かれている感じで、読んだあと、あまり残らなかった。 紹介されているそれぞれを深めて読んでいったら知識にもなると思うので、入り口としてこの本を参考にできたらいいなと思った
Posted by
橘玲さんの著書は、色々な知識や観点から構成されていて。これは、この題材とどう関わりがあるのか?と考えさせられて読んでいる感じ。面白い情報や知見と出会うことが出来るが、このバカと無知とどう繋がるのかな?と思いながら読むので、あんまり入ってこない。多分、嫌必ず私がバカなのだろう。でも...
橘玲さんの著書は、色々な知識や観点から構成されていて。これは、この題材とどう関わりがあるのか?と考えさせられて読んでいる感じ。面白い情報や知見と出会うことが出来るが、このバカと無知とどう繋がるのかな?と思いながら読むので、あんまり入ってこない。多分、嫌必ず私がバカなのだろう。でも人間の本性について勉強になったのでそれなりの評価をさせてください。
Posted by
シロクマ効果など勉強になった。自身がまずは何らかのバイアスがかかっていることを認識してニュースなどに触れる必要ごあると感じた
Posted by