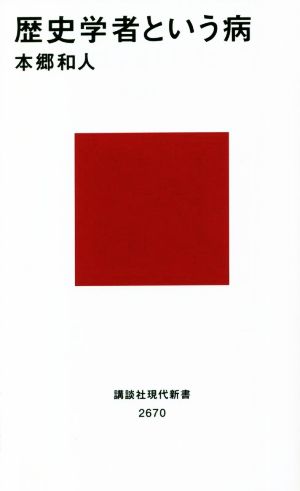歴史学者という病 の商品レビュー
歴史学者からの『告発』?!
2023年11月読了。
著者は最近、テレビ等の媒体でもよくお見掛けするし、著作や連載等も楽しんできた一読者であった。
だから本書も「何か歴史学のトリビアが…」くらいの気安さで読み始めたのだが、読んでビックリ!
これは、一人の日本史の歴史学者の嘘偽りない懺...
2023年11月読了。
著者は最近、テレビ等の媒体でもよくお見掛けするし、著作や連載等も楽しんできた一読者であった。
だから本書も「何か歴史学のトリビアが…」くらいの気安さで読み始めたのだが、読んでビックリ!
これは、一人の日本史の歴史学者の嘘偽りない懺悔であり告白であり、尚且つ『このままでは歴史学が形骸化してしまう』と云う告発書ではないか!
「歴史」特に「日本史」と云うものは、小説や漫画で読む分には楽しいものの、「学校の教科」として見れば《年号の暗記ばかりでちっとも楽しくない科目》であるのは、誰一人否定しないと思う。
それでも尚「司馬遼太郎らが書いてるのは大衆文学」等と研究者(専門家)は背を向け、世の若者の好奇心を削いでいる現状を鑑みれば、一般市民が「研究者に期待すること」等も全く無いと思っていた。
しかし本書を読んで、本郷先生の《本気度》に触れ、いつの日か「日本の歴史観」がしっかりと地に根を張る日が来るのではないかと、心躍る様な気分で読み終えた。
システマティックに予算配分したり、上の意向に沿って「英語とIT」を日本史研究のテーマに据えようと思っている文科官僚は、本書を読んで《自分達は国の税金を使って、一体何をしようとしているのか》を国民に正々堂々と説明出来るのか、良く考えて欲しい。
本書は『自分の国の歴史』への責任感を、しっかりと感じ取れる良書である。特に、歴史好きの若い人達には是非読んでいただきたい。
左衛門佐
著者の自伝として読みながら、歴史を扱うとはどういう事かを知ることができる。 時代が変われば歴史も変わるという話は、イギリスの産業革命の有無がイギリスの景気で変わるという話と近い物があって面白い。 歴史において真実の情報だけを集めること、そこからつなげて叙述を作り出すこと。このせめ...
著者の自伝として読みながら、歴史を扱うとはどういう事かを知ることができる。 時代が変われば歴史も変わるという話は、イギリスの産業革命の有無がイギリスの景気で変わるという話と近い物があって面白い。 歴史において真実の情報だけを集めること、そこからつなげて叙述を作り出すこと。このせめぎ合いがとても難しいバランスで安易に新しい発見や面白い解釈を信じてしまう自分としては気をつけねばと思った。
Posted by
図書館で借りた。 東京大学の本郷先生の自伝であり、歴史学とは・歴史学者の仕事とは、というものを教えてくれる本でもあり、歴史学会の流派・流儀を知れる本でもあり、戦前から現在にかけて「教育」の変遷を知れる本でもある。 ちょうど難しめの歴史学の本を読もうとしていたので、その前に軽く読む...
図書館で借りた。 東京大学の本郷先生の自伝であり、歴史学とは・歴史学者の仕事とは、というものを教えてくれる本でもあり、歴史学会の流派・流儀を知れる本でもあり、戦前から現在にかけて「教育」の変遷を知れる本でもある。 ちょうど難しめの歴史学の本を読もうとしていたので、その前に軽く読む新書として満足できた。 自分の近い分野に数学科があり、よく「数学が好き・得意だからといって軽い気持ちで数学科に行ってはいけない。別物だからだ」なんて聞くが、歴史学もその面では似ているな、と思った。 また、歴史学者がどんなことをしているのかを垣間見ることができた。本郷先生の人間味がちょいちょい顔を出すのもこの本のスパイス的に楽しかった点。
Posted by
今回は歴史の話もあったけど、学者としての裏話というか業界に入った経緯も含めた1冊で、それなりに面白かった。この手の道を選択しなくてよかった。真理の追求は「面白い」だけではやっていけない。
Posted by
すごく面白い。 いつのまにか学問は、「研究」ではなく「仕事」になっている。実証にこだわるあまり、考えなくなっている。あらゆるところで、アレントが言う「行為」の空間は削られているのだ! そこに危機感を持って、素朴に社会へ発信しようとする著者の公共精神にしびれる。現代の知識人とは...
すごく面白い。 いつのまにか学問は、「研究」ではなく「仕事」になっている。実証にこだわるあまり、考えなくなっている。あらゆるところで、アレントが言う「行為」の空間は削られているのだ! そこに危機感を持って、素朴に社会へ発信しようとする著者の公共精神にしびれる。現代の知識人とは、大学の研究者のことではない。著者のような「社会のために」をしっかりと考えてきた知の担い手のことである。 東京・亀有の大家族に生まれたという生い立ちの振り返りからして面白い。戦後歴史学のおよその流れとして、第〇世代「皇国史観の歴史学」、第一世代「マルクス主義史観の歴史学」、第二世代「社会史「四人組の時代」」、第四世代「現在」というまとめも、実に分かりやすい。著者の歩んだ研究者人生と、戦後歴史学とがクロスして、実感として頭に入ってくる。 ある程度やり遂げた40代。仲間作りを始めるといったくだり。実によく分かる。業界のマウント取りが、ばからしくなるころだ。気づくと周りは、その特定の業界や組織の論理を反復するだけで、考えなくなっている。くだらない。著者の怒りはよく分かる。京都定点観測の歴史像、エリートの押し付ける歴史への批判(p183)なんかも、実に共感できる。 著者が体験した教科書づくり。「暗記」の脱却を目指す試みは見事に挫折。結局は先例にならったものができあがる。なぜか? ことはそう簡単ではないからだ。教科書は高校の先生が扱う。高校の先生には生徒を合格させるというミッションがある。そして大学受験は「暗記」でできている。そう、戦う相手は日本の教育システム全体だったのだ! 実証をめぐる著者の思い。ただ上から下へ自動的に落ちるような作業を「牛のよだれ」(p196)と痛烈に批判するが、結局、研究という知的行為も、いつのまにか自動的な「労働」に成り下がっている!!調べるだけで「考える」がないのだ(p202) といって網野史観への指摘もバランスがいい(p210)。神聖視するのも間違っているが、民衆を持ち上げすぎるのもどうか、と。 最後。「あなたが居座ろうと思っている今の歴史学界隈はこのまま存続できると思ってますか?」)(p220)この指摘は重い。 いつのまにか、居座っている人たちが多い。その人たちはいつまでも更新しない。外とつながろうとしない。だからこそ、著者のような存在が際立つ。研究者や、あるいは、ある程度年を重ねた社会人は、本書を読んで、自らの行為がここでいう「研究」ではなく「仕事」に置き換わっていないか、自問すべきだろう。名著。
Posted by
筆者自身の経験から語っているので、さらっと読めるし、面白い。しかし、内容は実は深い。物語としての歴史と、科学としての歴史。歴史における実証とは。恥ずかしながら初めて理解できた。大学で学問としての歴史をしたいと志す高校生が読むのにも適しているのではないか。
Posted by
歴史学者が博士号を取るのは、実はけっこう後というのが新たな発見だった。確かに、そうした仮説や発見は、一朝一夕にできるものではないし、ずっと学び続けることの面白さのようなものがあるのだなと感じた。
Posted by
歴史学者、本郷和人氏の自伝的エッセイ。 庶民の私から見たら本郷氏もどうみてもエリートなんだけれど、東大及び史料編纂所にはそれ以上の天才が数多いるらしく雲の上を垣間見ることができて面白い。 佐藤進一、網野義彦、石井進など20世紀を代表する歴史学者に対する本郷氏の印象や彼らとのエ...
歴史学者、本郷和人氏の自伝的エッセイ。 庶民の私から見たら本郷氏もどうみてもエリートなんだけれど、東大及び史料編纂所にはそれ以上の天才が数多いるらしく雲の上を垣間見ることができて面白い。 佐藤進一、網野義彦、石井進など20世紀を代表する歴史学者に対する本郷氏の印象や彼らとのエピソードも面白い。特に本郷氏が恩師であると自認している石井進氏に対する愛憎が入り混じったようなお話は面白く、名前しか知らなかった歴史学の権威の人間臭さを知れて良かった。 皇国史観を代表する歴史学者、平泉澄の名言「豚に歴史はありますか?」はとても衝撃的であり、歴史に対する考え方は世相や時代に反映されているというくだりを読んだときは、E.H.カーの『歴史とは何か』を想起した。史料編纂所の所員でありながら「実証への疑念」「史料への疑念」を呈する本郷氏の姿勢も同様にそれを想起させる。 歴史及び歴史学に対して興味をそそらせる良い本だった。
Posted by
「半生記にして反省の記」という帯のノリにどれくらい乗っかって良いものか・・・ 前半はご自分の生い立ちや学生時代などをユーモアを交えて書かれているが、終盤に近づくにつれてマジになり、専門的な話になり、私の頭脳では消化できなくなってくる。 (まあ、頭脳は消化器官ではないわけだが) ...
「半生記にして反省の記」という帯のノリにどれくらい乗っかって良いものか・・・ 前半はご自分の生い立ちや学生時代などをユーモアを交えて書かれているが、終盤に近づくにつれてマジになり、専門的な話になり、私の頭脳では消化できなくなってくる。 (まあ、頭脳は消化器官ではないわけだが) 本郷先生は、時々テレビにも出演されているから顔と名前が一致する学者さんで、とても面白い方だということも分かっている。 「東京大学資料編纂室」という肩書きも知っていたが、そこが何をするところなのか知らなかった。 たとえば誰もが知っている「日本書紀」みたいな歴史書を編纂しているのだという。 驚いた。 そして、そこでの上司が奥様であり、本郷先生がどれだけ奥様を尊敬していらっしゃるのかも分かった。 歴史は、理系のように答えがはっきり出るものではなく、時代や研究者によって考え方が違ってしまうのだという。 例えば、戦前までの「皇国史観」 印象的だったのは、皇国史観ゴリゴリのとある先生が、農民一揆をテーマに卒論を書きたいと言って来た教え子に「豚に歴史はありますか」と言い放ったということ。 歴史はエリートのものだというのだ。 逆に、歴史は名もなき人々のものだという考えの先生もいる。 なかなか難しい。 いろんな先生たちのことを書きすぎている気がするが大丈夫なのか(笑) 資料があって、それを研究して、「考える」ということが必要なのに、試験で良い点を取るためには「暗記さえすればいい」と言われ、つまらない科目だと思われているのが悔しいという。 歴史学はどんどん研究予算も削られている。 テレビに出たりするのは、歴史学の魅力をもっと広く知らしめたい、という動機らしい。 私たち市井の歴史好きは、十分楽しませていただいているけれど、もっと上つ方にアピールできないと、予算にはつながらないんでしょうねえ・・・
Posted by
p29 韜晦 とうかい 自分の才能や本心を他のことで隠すこと p81 新選組という存在は、ほぼ小説家・司馬遼太郎の影響下にあるロマンの結晶とも言え、多数の史料の精読を重ねるという学問の対象にしずらい。要するに史料が少なく、研究対象にならないのである p83 歴史上の人物の心の...
p29 韜晦 とうかい 自分の才能や本心を他のことで隠すこと p81 新選組という存在は、ほぼ小説家・司馬遼太郎の影響下にあるロマンの結晶とも言え、多数の史料の精読を重ねるという学問の対象にしずらい。要するに史料が少なく、研究対象にならないのである p83 歴史上の人物の心の中へ分け入り、「当時はこんなことを考えていたのだ」ということを語るーそれは作家や文学研究者の仕事である。歴史学を研究する者の立ち入るべき場所ではない 現在の歴史学の主流は実証を重んじる科学なので、人間の内面にこだわってはいけない。 p91 本能寺の変 学説と呼べるレベルに達しているのは「四国説」しかない。 四国の長宗我部氏をめぐる信長と光秀の対立を指し、この対立が本能寺の変の遠因だったのでは p93 大人になるということは、自分に詰腹をきらせることだ 西部邁 (強制的に責任をとらされたり辞職させられたりすること) p145 皇典講究所 国学院大学の基 p185 鎌倉時代、地頭たちへの命令書には、必ず「先例に任せてその沙汰をいたすべし」という決り文句が書かれている。あなたを地頭に任命するが、詳細は、その土地の先例どおりにやりなさいということだ
Posted by