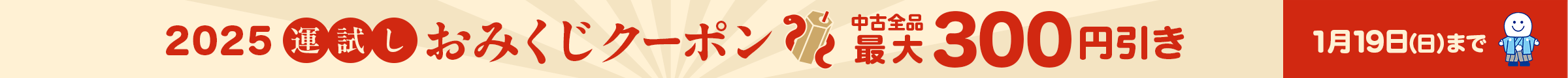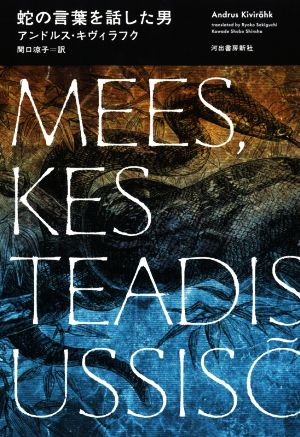蛇の言葉を話した男 の商品レビュー
どこにも行けない、滅ぶしか道が無い者たちの物語。エストニアを舞台としたファンタジー小説であり、時代についての言及はされていないものの、キリスト教が広がり始めていることから中世くらいのイメージが立ち現れる。語り手であるレーメットは森に住まう者の一員であり、蛇の言葉を使うことができる...
どこにも行けない、滅ぶしか道が無い者たちの物語。エストニアを舞台としたファンタジー小説であり、時代についての言及はされていないものの、キリスト教が広がり始めていることから中世くらいのイメージが立ち現れる。語り手であるレーメットは森に住まう者の一員であり、蛇の言葉を使うことができる。蛇の言葉は動物との対話を可能とし、従わせることで森から恩恵を授かれる便利な技術だ。しかし今この言葉を使う者はほとんどいない。みんな蛇の言葉を忘れてしまい、そこに秘められた力についての憧憬も薄れてしまっている。 森の近くには村があり、西洋から持ち込まれたキリスト教によって急速に近代化が進みつつあった。森の住人たちの中にもちらほらとそちらの生活に移行する者が現れ始め、森と人間たちの関係は変化し、その流れを止めることは誰にもできない。語り手のレーメット自身にもそれは同様だ。 この小説は何かを変えようとすることを描いた物語ではない。 何かを受け入れる物語でもない。 ただ、そのような避けられない流れがあったこと。いまなおそれは流れ続けていること。そのことをファンタジーという装置を使い、伝えようとした小説なのだと思う。 語り手のレーメットは馴染んだ森での生活から離れようとする気はなく、畑を耕したり、パンを食べたり、馬の糞についてだらだらしゃべっている村の生活のことを心底バカバカしいと思っている。一方で、村人たちはキリスト教の教えに従い、騎士に憧れたりしながら森人たちのことを軽く軽蔑している。双方に受け入れることは無く、双方に自分たちの方に賢さが備わっていると思っているようだ。 つまり、語り手であるレーメットの視点に立ちながら話は進んでいくものの、時代に取り残された者(=レーメットたち)の生活を理想化するわけではなく、かといって村人たちの善良さを強調するわけでもない。それが本書をより深みのあるものにしている。ここで描かれているのは双方に知恵があり、双方に愚かだということなのだ。 読みながら思い出したのはデヴィッド・グレーバーの『万物の黎明』で、あの本に書かれていたように、森の住人たちには森の住人たちなりの理論があり、それは西洋で形作られた考え方と優劣を付けられるようなものではない。だからこの物語では、森の中にいる邪悪な存在のこともちゃんと描くし、騎士という西洋および戦の象徴である人たちのことも優劣無しで描く。価値観をどこかに据え置こうとはしない。見せたいのは、感じ取ってほしいのは歴史であり、であるがゆえに全体の視点はフラットだ。 物語はときにゆるやかに、ときに激烈に進行する。それまで何行もかけてレーメットの気持ちを描写していたかと思えば、次の行では突然彼にとっての大事な人がぼろきれのように死に、ただの肉と化す。そのテンポは独特で、平静でありながらイメージが豊潤なためドライブ感が強い。エストニアの歴史や近代化がたどった流れを風刺しているようなので、そのすべてを捉えきることは(解説を見るまで)できなかったけれど、何より「おとぎ話」としての、つまり虚構としての強靭さに惹きつけられる。 これは悲劇であり喜劇だ。 どこかで違っていれば別の可能性があったはずなのに、というレーメットの言葉は近代化によって失われた数々の文化に対する哀愁と言えるだろう。だがそこで彼は必要以上に悲観に暮れることをしない。もはやすべては過ぎ去ったことであり、いまさら変えようも無いことなのだと諦念を抱いてそこで終わり。近代化によって形成された社会と、祖先からの知恵を受け継ぎ守られてきた社会。双方に価値があり、双方に知恵がある。それは逆説的に双方に価値は無く、双方に愚かなのだと言い換えることが可能なのだ。 一人称フェチとしては、主人公のフラットでありながらフリースタイルのように次々と言葉を繰り出し、イメージを想起させる”濃い”語りが好きだった。なおかつ語り手を「ヒーロー」とすることはなく、愚かさを抱えた人間のひとりとして描いていたところも嗜好に刺さる(それは物語の要請上からくるものではあるが)。 唐突に放り込まれる暴力と、言葉を理解する蛇や熊との対話。村と森との関係性。どれもがファンタジックで素敵な手触りを持ち、しかし一方で、メタファーとして「いま・ここ」にある世界の像をより深く見つめさせる力を持っている。そんな稀有な小説だった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・少なくとも五年ぶりくらい読書というものに没頭できた。感謝。 ・動物と人間は今よりもっと近いものだったかもしれない。 ・森を捨てていった人たちに感覚が近い私だから、本の世界にいたらなんて前時代的なことを、非合理的なことを、古臭くてださいことをと主人公のことを思ってしまうと思う。知らないものや洗練されたものに憧れるけれど、どちらがいいかはその人次第。自分が古臭いと思うものを馬鹿にしないように。そこには豊かな文化があるかもしれない。私よりも敬意を払うべきものかもしれない。誰がどんな選択をしようがその人の自由だけれど、その評価はその人がその人自身に下せばいいものであり、外野がとやかく言うことではない。人に影響力を与えようとすると滑稽なことになるかもしれないよ。争いになるかもしれないよ。
Posted by
ぼくは眠りの中を泳いだ。眠りは波のように僕をあやし、ほとんど手で触れられるようだった。眠りは苔のように柔らかく、同時に、砂のように指の間に入り込んできた。 引き込まれて一気に読んだ
Posted by
初めて読んだエストニアの本。 これがどんな本かって?トールキン、ベケット、M.トウェイン、宮崎駿が世界の終わりに一緒に酒を呑みながら最後の焚き火を囲んで語ってる、そんな話さ。エストニア発壮大なファンタジー。 この意味がよく分かった気がする。エストニアが森を大事にする理由もまたよく...
初めて読んだエストニアの本。 これがどんな本かって?トールキン、ベケット、M.トウェイン、宮崎駿が世界の終わりに一緒に酒を呑みながら最後の焚き火を囲んで語ってる、そんな話さ。エストニア発壮大なファンタジー。 この意味がよく分かった気がする。エストニアが森を大事にする理由もまたよく分かった。読みやすいです。
Posted by
これは面白かった。 古い文化や蛇の言語が残る”森”に暮らす主人公レーメット含む一族。かつては多くの人々が暮らしていた森だが、今では住民も少なく、その住民たちも森での未来に希望を見いだせず、”村”へと居住区を移している。 村では多くの人が役割を与えられて暮らしている。そして面白いの...
これは面白かった。 古い文化や蛇の言語が残る”森”に暮らす主人公レーメット含む一族。かつては多くの人々が暮らしていた森だが、今では住民も少なく、その住民たちも森での未来に希望を見いだせず、”村”へと居住区を移している。 村では多くの人が役割を与えられて暮らしている。そして面白いのが、そのほとんどがキリスト教を信奉している。 森の人々の中には精霊を信奉している人もいる。 主人公レーメットは森と村を行ったり来たりしながらそのどちらにも属さない。 どちらにも惹かれる部分と愚かしい部分がある。 物語の終盤に大きなカタストロフが起きる。結構ショックではあるのだが、カラッとした作風であるためか、非常に辛い出来事が起きつつも読後はそこまで辛くない。 というか清々しくも感じた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
"「かつては、どんな生き物の身体も今より大きかった。信じられないほど巨大なものもいたが、今では消えてしまったか、姿を隠している。闇の中に永遠に眠っているのだ。大きければ大きいほど、眠りも長い。もしかするとそういった巨大で誇らしい生き物は二度と目覚めないかもしれない。世界はそんな生き物たちが存在していたことを忘れてしまうだろう。だからこそ、普段は毛づくろいで取り去ってしまうシラミが、たとえ数匹でも、先史時代の怪物のように大きくなると嬉しいんだ。レーメット、よく見てごらん。今目にしているのは、何十万年も前の世界のわずかな断片なんだ!」" P.57 下段 "その頃ぼくたちは影でしかなくなっていたが、死ぬ前に、黄昏のもとその影は伸びていた。今、ぼくは消えたのだ。ぼくが今でも生きているとは誰も知らない。" P.166 上段 失われてゆくもの、失われてしまったものへの憧憬はきっと『三つ目がとおる』で植えつけられた。だから、本書のタイトルに惹かれたのだと思う。かつて在り、失われてしまったもの、ラスト・オブ・○○なカンジに見えたから。 物語のはじまりとおわり、また途中のところどころはそんなふうにも読める。だがしかし。 序盤、クマとオカンの生臭さに鼻をつまむことになる。 中盤にいたって、これまでそんなふうに感じる作品と出会うことは皆無であったと思えるのだが、近頃ショッキングな出来事が出来したためであろうか、松本零士作品の風合いを感じて面白くなった。どんな風合いかというと、ボコボコにやられてオノレと再び挑んではまたボコられる、あの風合いである。 主人公の祖父が登場するにいたって松本零士感は頂点に達し、以後、薄れるたびにその印象は強化されてクライマックスに至る。 劇中に描かれた、四つ巴の死の連鎖。 これが象徴するものが、本書のキモ、なのであろうか。 本書はたしかに失われたもの、失われていくものを扱っている。だが、去りゆくものをただ良きものとはしていない。去りゆくものにも、今あるものと同程度に瑕疵があり、今あるものよりも優れていたわけではない。謎マナー講師が発明したおまじないによって世界はいつでも腐ってゆける。そんなことを述べている。 誤解や無理解による悲劇は思いもかけぬところに飛び火し、誤解や無理解によるため責任を感じることもなく、ただ忘れ得ぬ憎しみが残る。 そんなことを読み取った気にもなれるが、いささか雑でくどい会話もあり、うんざりしないわけではない。 巻末の『フランス語版訳者による解説』は一読の価値あり。
Posted by
ものすごい本だった こんなに分厚くて文量も多いのにこのスピード感で読み終わったのは初めてかもしれない ほんとうに、地獄が続く どこまで落ちていっても落ち切らないくらいの展開が止まらなくて、とても疲れた すごい本だった
Posted by
エストニア文学って多分ほぼほぼ初めて目を通したんだけども、これが異色なのか基本こういう感じなのか…!??? 蛇の言葉とは。命とは。
Posted by
徹頭徹尾、失われてゆくものらとその道筋についての物語。現在進行形で滅びる文化を看取る最後の世代(人間)となってしまった主人公の手記。
Posted by
近代化で失われるものがある。でも失われるものも、かつての何かを置き換えたもの。全ての人間、動物、植物が静かに次の世代と交代する。ある意味残酷な現実が淡々と語られる。
Posted by