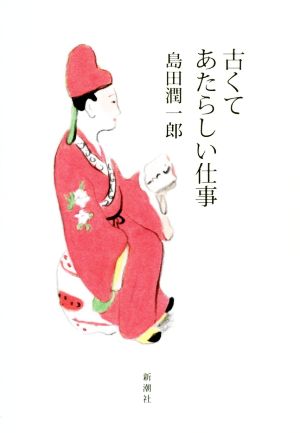古くてあたらしい仕事 の商品レビュー
これは島田さんによる「私小説」ではないか、と私は思いました。精興社の字体も、雰囲気にあっていて。 内容はたった一人で出版社を始めることになった経緯と、その後の仕事の進め方についてですが、その心の裡にあるものがあまりある思いになって溢れ出す。シンプルだけれど、選ばれたことばを使って...
これは島田さんによる「私小説」ではないか、と私は思いました。精興社の字体も、雰囲気にあっていて。 内容はたった一人で出版社を始めることになった経緯と、その後の仕事の進め方についてですが、その心の裡にあるものがあまりある思いになって溢れ出す。シンプルだけれど、選ばれたことばを使って、こう表現されると、美しいかたちを持った私小説に思えてしまうのです。(じっさい、小説家を目指していた方だった) 「仕事とは何か」を前半のほとんどを使って考えている件は作者の苦悩を感じるけれど、仕事でお金をもらうことも自分にとって必要だが、誰か他の人のために働く、ということが重要だった、という結論にたどり着きます。 後半の、和田誠さんや、庄野潤三さんのご家族とのエピソードは、島田さんが仕事を依頼する時の、丁寧な手紙を想像させます。仕事への取り組み方が真摯であったからこそ、実現したのでしょう。 だんだんなくなっていく町の書店。その一方、若い人たちがコンセプトを持って書店を開いていく。あたらしい本屋さんの形が見えてきました。 本は美しいもの。良い本は形に残していかなくてはならない、という島田さんのおもいにも、共感する人たちが増えているのでしょう。 地方の郡部に住む私は、本を買うときはネット書店を頼りがちです。これを読むと、時間やガソリン代がかかっても、町の本屋さんに受け取りに行くべきなのかな・・・と思ったり。 地方にいたら、ありがたいのは図書館です。ここならたくさんの本が棚に並んでいるのを見ることができます。(書店と違い、借りられた本は並んでないことがネックですが)ネットを使えば、読みたい本を予約することもできます。 この本も思いがけず、いつも行く小さな図書館の棚に並んでいるのを見つけました。並んだ本の中から、一冊の本を見つけ出す喜び。出会い。こういう本を、買っていてくれたんだ、という司書さんの選書の目のありがたさ。本が並んでいるという光景を、失いたくはありません。 自宅に本を増やしたくない私は、買った本は、読んだ後、ほとんどを寄贈しています。でも年に一度くらい、自分が手放したくない、と思える本を、寄贈してみようかなと思いました。手始めに、石川直樹さんの写真集を。
Posted by
ひとり出版社「夏葉社」は良書の復刊をコンセプトにした出版社です。 夏葉社の本は最近本屋さんでも見る機会が多くなりました。 本自体がとても美しいので思わず手に取ってしまいますが、この本を読むと本は美しいものであるという事が基本に有るんですね。 物によりますが目が惹きつけられるような...
ひとり出版社「夏葉社」は良書の復刊をコンセプトにした出版社です。 夏葉社の本は最近本屋さんでも見る機会が多くなりました。 本自体がとても美しいので思わず手に取ってしまいますが、この本を読むと本は美しいものであるという事が基本に有るんですね。 物によりますが目が惹きつけられるような美しい本と、ギラギラと目は惹くけれど美しくはない本もあります。彼はそういった前者の本を作る事を志しています。 てっきり有能で迷いのない人なのだろうと思いましたが、就職出来ずもんもんとしている中で有る機会が有り、一人で出版社を興そうと考えた珍しい人です。 誠実で不器用で、それでいて人間を愛している人柄が出ている本たちが、どうやって生み出されたのか読む事が出来てとても有意義で楽しい本でした。
Posted by
ようやく読むことが出来た。タイミングはあるのだろう。いまの自分の中で読むには涙する箇所のなんと多いことか。 夏葉社に限らず、活版印刷やハンドメイド作品に魅かれている自分はいて、それをこの本が「あぁ、そういうことなんだよな」とすっと心に落としてくれた。 そして。夏葉社と気づかな...
ようやく読むことが出来た。タイミングはあるのだろう。いまの自分の中で読むには涙する箇所のなんと多いことか。 夏葉社に限らず、活版印刷やハンドメイド作品に魅かれている自分はいて、それをこの本が「あぁ、そういうことなんだよな」とすっと心に落としてくれた。 そして。夏葉社と気づかないまま、手元には『神様のいる街』や『冬の本』、『さよならのあとで』があった。 自分も信じたい。こういう本のつながりというか、本の力を。
Posted by
夏葉社という出版社をたった一人で経営している著者の本に対する想いがつづられた本。 もともと作家志望だったこともあり文章はとても気持ちよく読めます。 出版業界の不況と言われる中、小さな出版社や書店が独自の工夫とアプローチで新しい需要を生み出している。 まさに古くてあたらしい仕...
夏葉社という出版社をたった一人で経営している著者の本に対する想いがつづられた本。 もともと作家志望だったこともあり文章はとても気持ちよく読めます。 出版業界の不況と言われる中、小さな出版社や書店が独自の工夫とアプローチで新しい需要を生み出している。 まさに古くてあたらしい仕事。 頑張れ出版社、頑張れ本屋。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
出版不況と言われて久しい。 近年も、本屋にまつわる話、出版業界に関する本で、気になるものが、年に何冊かあり手に取る。本書のそのひとつだった。夏頃、本屋の店頭で少し立ち読みした。その後、バタバタしていて忘れていたけど、ようやく落ち着いて読めた。良かった。 我々が書店を訪れる理由、本を読む理由がそこにある。 『幸福書房の四十年』で岩楯店主はこう言っていた; 「自由に気持ちを広げられるのが本屋という場所なんだから。」 本書の著者は、『ガケ書房の頃』から山下賢二氏の言葉を引いて、本屋の存在価値を語る。 「本屋は勝者のための空間ではなく、敗者のための空間じゃないかと思っている。誰でも敗者になったときは、町の本屋へ駈け込んだらいい」 この一文を読んだときに、 「自分の仕事の意味が、ようやくわかったような気持ちになった。」 と著者は言う。 タイトルにあるように、この本は、「仕事」に関する本だ。 1976年生まれの著者は、いわゆる氷河期世代なのだろう、大学を出てすんなり企業に就職して、終身雇用でそのまま安泰して勤め上げるという道筋はたどらない。 就職するも短期で退社、アルバイト、派遣を得て、30代で未経験の本の世界(出版業)へ単身飛び込んでいく。 が、そこに、時流に乗るとか、インターネットを活かしてとか、儲けなきゃ稼がなきゃという“焦り”はない。自分の尺で、自分の手の及ぶ範囲を見極め、大手出版社が手掛けない、絶版書の復刊をメインに、小さな実績を積み重ね事業を展開していく。 大手チェーン店の跋扈する駅前商店街の変遷、巨大資本に飲み込まれ消えていく町の本屋に哀惜を感じつつも、時代の流れもしっかり認識し、SNSの力や、大型書店の存在も認めている。 “インターネットが社会の隅々まで行き渡ったことにより、本との出会い方は多様になり、オンライン書店と大型書店は、「ロングテール」という言葉とともに、ベストセラー以外の多種多様な書籍に光を当てることが可能であることを証明しはじめていた。” 大局も捉えながら、ニッチなところで勝負した。その目の付けどころは、実はしっかりしている。分を弁えつつも、最初に手掛ける一冊の装丁を和田誠に依頼するなど、実は大胆不敵。そこには、何も持たないが、本への一途な信頼感を、素直にまっすぐ相手に伝えるひたむきさがあったからこそだろう。 本の魅力、本の持つ価値を信頼して信じる言葉が、随所に出てくる。 “当時、「本はやがてなくなる」といったり、書いた人は数えきれないくらいいた。でもぼくは、その本の変わらないところが好きだった。信頼していた、といってもいい。” “本はただ単に、情報を紙に印刷して、それを束にしたものではない。それよりも、もっと美しいものだし、もっとあこがれるようなものだ。” “自分がつくったものを、読者を信じて、できれば長いあいだ待つこと。自分がつくった商品の価値を信頼すること。” 自分が信じた商品を創り出す仕事だ。やりがいが無いわけがない。 “古くてあたらしい”のは、業種や商品ではなく、物事への向き合い方なんだなと気づかされる。それは、自分の生き方、人生との向き合い方でもある。 人の人生なんて、もう何万年も、多くの人が繰り返し繰り返し、過ごしてきた。それでも、人は自分の人生を送るのは、それが誰の真似でもない、自分だけの生き方だからだろう。 “古くてあたらしい”人生を。 自分の人生は、いつでも新しい。 そんな、自分の生きたかを見つける勇気をくれる示唆に富んだ一冊だ。
Posted by
人生でもっとも大切なのは、人から必要とされることだ。 会社を経営するということは、ぼくが想像していた以上には難しくはなかった。経営に必要な才覚なんて、たぶんない。やると覚悟を決めれば、だれでも、いつでもはじめられる。あとは全部はじめてから考えればいい。毎日毎日、軌道修正していけば...
人生でもっとも大切なのは、人から必要とされることだ。 会社を経営するということは、ぼくが想像していた以上には難しくはなかった。経営に必要な才覚なんて、たぶんない。やると覚悟を決めれば、だれでも、いつでもはじめられる。あとは全部はじめてから考えればいい。毎日毎日、軌道修正していけばいい。 だれかのための仕事は、世の中がどんなに便利になっても、消えてなくなるものではない。
Posted by
気がつけば「小さな仕事」をしている方の本を読んでいる。この本もそうだ。 「小さな仕事」とは、「悪い仕事」ではなく「大きな仕事をしているところではできない仕事」なのだということがこの本で話されていてスッと理解ができた。私も大きな仕事ができるタチではないと思うので、小さな仕事をコツコ...
気がつけば「小さな仕事」をしている方の本を読んでいる。この本もそうだ。 「小さな仕事」とは、「悪い仕事」ではなく「大きな仕事をしているところではできない仕事」なのだということがこの本で話されていてスッと理解ができた。私も大きな仕事ができるタチではないと思うので、小さな仕事をコツコツと積み重ねていきたい。
Posted by
ところどころで、泣きそうに。 本が好きで、本に助けられ、本に楽しませてもらい、本に教わった経験がある人なら、同様にきゅーんとするのではないかしら。 転職活動に失敗し続け、ひとり出版社をすることになった著者が、これまでの経緯や本と本にまつわる人々について書いてあります。そんな内容で...
ところどころで、泣きそうに。 本が好きで、本に助けられ、本に楽しませてもらい、本に教わった経験がある人なら、同様にきゅーんとするのではないかしら。 転職活動に失敗し続け、ひとり出版社をすることになった著者が、これまでの経緯や本と本にまつわる人々について書いてあります。そんな内容でなぜ涙腺に訴えかけてくるのかというと、普遍的な人の弱さや本の持つ力、価値、本の世界を旅した人が味わう感覚を丁寧に描いてくれているから。 「だれかになろうとしないこと」 「自分の頭と身体と経験のすべてを使うことができる仕事をしたい。」 単に本についてだけではなく、これからをどんな風に、何を大切に生きていきたいのかを僕はこうやってきたよ、と語ることで、読者にも自問する機会をくれる良書。 夏葉社さんの本も読んでみよう。
Posted by
具体的で手応えのある仕事をコツコツしている姿に感動した。 こういう仕事をわたしも作りたい。 以下、線を引いた箇所の写経 もしかしたら、ぼくは大した仕事ができないかもしれない、とも思う。 けれど、そもそも世間に認められたくて、仕事をするのではない。だれかを打ち負かすために、仕...
具体的で手応えのある仕事をコツコツしている姿に感動した。 こういう仕事をわたしも作りたい。 以下、線を引いた箇所の写経 もしかしたら、ぼくは大した仕事ができないかもしれない、とも思う。 けれど、そもそも世間に認められたくて、仕事をするのではない。だれかを打ち負かすために、仕事をするのでもない。自分が全力をそ削ぐことができる仕事を自分で設計し、それに専念する。 (略) 重要なのは、自分の能力を過大評価しないことだろう。 かといって、見くびらないこと。 これまで培ってきた経験上で、すべてを考えるということ。 なぜ二五〇〇部という数字にこだわっているかというと、それがぼくが具体的に想像できる数字だからだ。自分がなんとか把握できて、利益もちゃんと確保できる数字。 新刊ができあがると、印刷会社が玄関先まで本を運んできてくれて、それをマンションのワンルームに積み上げる。二五〇〇部の本は、部屋の面積のおおよそ四分の一を占める。 ぼくは、刷りあがったばかりの本を郵便局を通してほんやさんにおろす。そして、読者に無事買ってもらうことができたら、それがぼくの給料となる。 (略) 刷り部数を増やせば、その分経費もかかるが、利益は大きくなる。けれど、そうすると、ぼくにはそのマーケットの広さが想像できない。ひとりひとりの人間の顔がみえない。 ぼくの仕事は、いつまでたっても安定とはほど遠い。日々、試行錯誤だ。それでも十年という間、仕事を続けてこられたのは、これまでの仕事が具体的であったからだと思う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
声高ではない。とても穏やかだ。正直でもある。 そして、何より、しずかな反骨心を感じる。 雑にならない。心を込める。 願わくば、一日も早く、新潮文庫に入って欲しい。 少し薄めの一冊になるかもしれないけれど。
Posted by