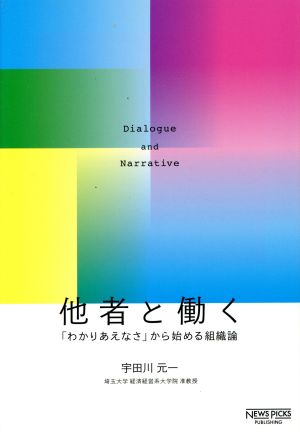他者と働く 「わかりあえなさ」から始める組織論 の商品レビュー
ナラティヴ 物語、解釈の枠組み、という事らしいが、その人の属性や立場からくる思考回路、行動原理みたいな事かなと。
Posted by
3.5点。社内スピーチを取り繕うために読んだ。他人を理解するプロセスは、リモートワーク下だとかなり困難なのでそれを解決する手法も知りたい。
Posted by
実質的なお話というより概念的なお話の印象。 「ナラティヴ」という解釈の枠組みについて、自分と他者はそれぞれで異なるナラティヴを持っていて、その間には溝があり、その溝に橋を築くように新しい関係性を築いていく、という話がメイン。 その溝(適応課題)に挑むためには、準備:溝に気付く→観...
実質的なお話というより概念的なお話の印象。 「ナラティヴ」という解釈の枠組みについて、自分と他者はそれぞれで異なるナラティヴを持っていて、その間には溝があり、その溝に橋を築くように新しい関係性を築いていく、という話がメイン。 その溝(適応課題)に挑むためには、準備:溝に気付く→観察:溝の向こうを眺める→解釈:溝を渡り橋を設計する→介入:溝に橋を架けるというプロセスを回すことが大切だという考えは納得。 とはいえ、橋を必要としない向こう側の人に対して橋をかけたいときはどうしたらいいんだ....という気持ちにもなった。その一方、「橋を必要としない向こう側」というのは私のナラティヴが勝手にそう解釈しただけで、自分のナラティヴを一度脇に置き、向こうを観察することが大切なのか....? といも思った。観察して橋をどう架けたらいいのか目処がつけられるって、それだけですごく優秀な人な気がするというのは、できない私の僻みかもしれない。
Posted by
課題には2種類ある。①技術的課題②適応課題。 適応課題をどう解決するか、人と人との相互作用から考える一冊。わかりやすくてハードル低い。
Posted by
会社の人間関係で悩んでいる人の参考になるかなと思って読みました。 対話の必要性や、そのときに陥りがちなことについてはよくわかったけれど、橋渡しの方法まではないか...。 「Iメッセージ」や声がけの方法と、この本のような指針の間にある本を読みたいなぁ〜
Posted by
組織の問題の大半が、適応課題じゃん!って読んで納得。そして、その解決のためには地道な「対話」という作業が必要不可欠。 GAFAは日本が過去に出来ていた組織と個の繋がりを、ダイバーシティの環境下で構築したという一文はハッとさせられた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
なぜ組織運営がうまくいかないのか、その本質を相手と自分のナラティブが違うからだという概念でわかりやすく説明している。組織における課題を、技術問題(既存の知識・方法で解決できる問題)と適応課題(関係性の中で生じる問題)という二つに分けて示したことも重要なポイント。そして、適応課題を技術的アプローチで解決することはできず、最大の鍵は対話にあるとしている。 自分自身、他人と理解し合うためには、お互いの中にある「前提」あるいは「物語」をすり合わせることが大事であると常々感じてきたので、非常に納得性の高い内容だった。更に言えば、課題解決という観点で見たときに、「相手がこう考えているだろう」と観察することはあっても、折り合わない、あるいは相手が間違っていると決めつけて、介入を諦めてしまうことばかりであったとも気付かされた。 他者と共に何かを成し遂げるための大事なエッセンスが詰め込まれている良書。また、明晰なステップの開示によって、より良いものを成し遂げるための内なる炎を静かに灯してくれる内容であった。
Posted by
人と分かり合うためには対話が必要で、論点が技術的問題ではなく適応課題の場合には、準備−観察−解釈−介入のプロセスで彼我に橋を架けるように進めなさい、という趣旨。 参考文献として、ロナルド・ハイフェッツのリーダーシップ論、ケネス・ガーゲンの社会構成主義論。
Posted by
当然そうするべきなのはわかるのですが、そうできないから問題が生じるのであって、、、と思ってしまった。なかなか難しいです。
Posted by
うーん、対話か… ちょうどここ数ヶ月、自分の部署の特定のメンバーと、あんまり上手く行ってないなと感じているので、また、ひいては属している組織全体でも、まぁ、本当につまらない毎日だなあと、日々過ごしているので、何かこの状況を変えるのでも、受け入れるのでも、どちらでも良いので、ヒント...
うーん、対話か… ちょうどここ数ヶ月、自分の部署の特定のメンバーと、あんまり上手く行ってないなと感じているので、また、ひいては属している組織全体でも、まぁ、本当につまらない毎日だなあと、日々過ごしているので、何かこの状況を変えるのでも、受け入れるのでも、どちらでも良いので、ヒントのようなものが書かれてはいないかと思い読んだのだが、確かに、まぁ、ヒントといえばヒントになりそうなことが全くないわけではないんだけど、つまるところ、持った感想は“つまらない”だった。 でもそれもまた、この本で書かれていることに照らせば、こういう話を読んでそう思う自分の気持ちは自分のナラティブ(一般常識?)なのだから、それを一旦脇に置いて、相手のナラティブとの溝を観察すれば、また違う考えを得られるということなのかもしれないな。
Posted by