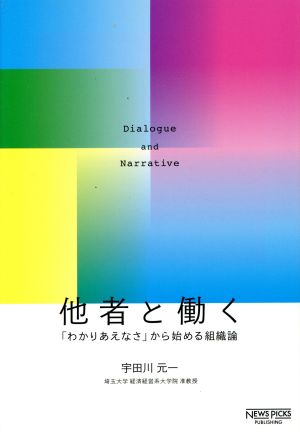他者と働く 「わかりあえなさ」から始める組織論 の商品レビュー
組織の中で他者と働くために必要な事をまとめられた本。内容は会社組織を例にあげて説明されているが、プライベートでもそのまま適用できる考え方で、とても参考になった。 誤解を恐れずに端的にまとめると、自分の理解は以下の通り。 人や組織にはそれぞれ個別のナラティブ「物語の語りを生み出す...
組織の中で他者と働くために必要な事をまとめられた本。内容は会社組織を例にあげて説明されているが、プライベートでもそのまま適用できる考え方で、とても参考になった。 誤解を恐れずに端的にまとめると、自分の理解は以下の通り。 人や組織にはそれぞれ個別のナラティブ「物語の語りを生み出す解釈の仕組み」を持っており、そのナラティブに従って主張を行う。そのナラティブにギャッブがある状態で議論しても、噛み合わない。 ナラティブに差があるのが当然と理解した上で、自分のナラティブを一旦脇において、相手のナラティブが何なのかを探り、相手の立場に立って相手が良いと思えることが何かを考える。それを後は提案、実行していくと言うもの。 中々難しい事かと思うけど、それを粛々とやっていけることが、成功につなげられる数少ない方法であると思った。
Posted by
人ととのかかわり方についてやさしい文体でわかりやすく書かれている本です。最初は本屋さんで装丁に目を引かれ、ぱらぱらと立ち読みしました。これは立ち読みで終わらせるには本当にもったいない、そう思って、気づくとレジでお会計を済ませていました。家に帰ると読みたい熱が冷めて、積読になってし...
人ととのかかわり方についてやさしい文体でわかりやすく書かれている本です。最初は本屋さんで装丁に目を引かれ、ぱらぱらと立ち読みしました。これは立ち読みで終わらせるには本当にもったいない、そう思って、気づくとレジでお会計を済ませていました。家に帰ると読みたい熱が冷めて、積読になってしまう、というケースも多いですが、この本は帰宅後すぐにページをめくりたくなる、不思議な魅力があります。
Posted by
語り方を変えることで、組織を変える。 今ある自分の「語り方=モノの見方」を脇に置き、 他者の語り方を知ろうと努め、 それぞれの語り方に共通項を見出し、 その共通項を共有していく。 ナラティブアプローチを組織論に適応した、 極めて実践的な本でした。 ただ、その具体的な実践が極...
語り方を変えることで、組織を変える。 今ある自分の「語り方=モノの見方」を脇に置き、 他者の語り方を知ろうと努め、 それぞれの語り方に共通項を見出し、 その共通項を共有していく。 ナラティブアプローチを組織論に適応した、 極めて実践的な本でした。 ただ、その具体的な実践が極めて難しいので、 (というか、自分で考えるしかないわけですが、) 著者の次著『組織が変わる』も読んでみたいと思います。
Posted by
同世代ですが,苦労が身になっている。そして,人文知を経営学に生かすことのひとつの卓越した実例だと思う。山口周は著者の爪の垢でも煎じて飲めば良いと思う。 「技術的問題」と「適応課題」 はロナルド・ハイフェッツから。 「私とそれ」 「私とあなた」 はブーバーから。 「対話とは,...
同世代ですが,苦労が身になっている。そして,人文知を経営学に生かすことのひとつの卓越した実例だと思う。山口周は著者の爪の垢でも煎じて飲めば良いと思う。 「技術的問題」と「適応課題」 はロナルド・ハイフェッツから。 「私とそれ」 「私とあなた」 はブーバーから。 「対話とは,自分の中に相手を見いだすこと,相手の中に自分を見いだすこと」 つまりは,「相手が,私であったかもしれない」という関係性の構築。 「ナラティブ」とは物語,つまりその語りを生み出す「解釈の枠組み」 ナラティブの溝に橋を架ける4プロセス ①準備「溝に気付く」 ②観察「溝の向こうを眺める」 ③解釈「溝を渡り橋を設計する」 ④介入「溝に橋を架ける」 「眺める」と「見つめる」 対話のプロセスは繰り返す 反脆弱性 社会構成主義 ナラティブ・アプローチ 中立な人間は原理的に考えてもこの世界には存在しません。誰もがそれぞれのナラティブを生きているという意味で偏った存在であり,それは自分もそうだということです。
Posted by
「私がもしも相手であったなら、同じように行動したかもしれない」と思えるような関係、という表現がなんだかしっくりきた。『他者と働く』というタイトルだけど、仕事の場面に限らず、生きていくうえでいろいろな場面で必要になることだと思う。対話やナラティブ・アプローチについてもう少し学んでみ...
「私がもしも相手であったなら、同じように行動したかもしれない」と思えるような関係、という表現がなんだかしっくりきた。『他者と働く』というタイトルだけど、仕事の場面に限らず、生きていくうえでいろいろな場面で必要になることだと思う。対話やナラティブ・アプローチについてもう少し学んでみたいな〜。 【読んだ目的・理由】本屋で気になったから 【入手経路】買った 【詳細評価】☆4.0 【一番好きな表現】現実は社会的に構成されている、社会の中身は会話である、だから、私たちは何を語るのかによって、現実を本当に少しずつだけれど、変えていくことができるかもしれない。(本文から引用)
Posted by
難しそう、と構えて読んだけど、 一気に読めました。読みやすかった。 内容も難しいことは書かれていない。 でも、 難しい。 そんなお釈迦様みたいになれるのだろうか? 「マウントをとってくる」みたいな、 総合格闘技用語が普通に使われる現在、 そんな相手に対話できるのだろうか?? 考え...
難しそう、と構えて読んだけど、 一気に読めました。読みやすかった。 内容も難しいことは書かれていない。 でも、 難しい。 そんなお釈迦様みたいになれるのだろうか? 「マウントをとってくる」みたいな、 総合格闘技用語が普通に使われる現在、 そんな相手に対話できるのだろうか?? 考えさせられた。 でも、読んでいて、 否定的な気持ちにはなりませんでした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ナラティブとは視点の違いにとどまらず、その人たちが置かれている「一般常識」のようなもの。こちらのナラティヴとあちらのナラティヴとの間に溝があることを見つけて言わば溝に橋をかけていくことが対話。 他者との関係性のあり方を考えさせてくれる内容であり、人に優しくなれそうだなと思えた一冊でした。
Posted by
対人関係、組織間の関係において、わかっていないことが何かがわかっていない、というのは確かにと思わされる。 相手のナラティブで物事を捉える、前にまずメタ認知で自分のナラティブに気付く必要がある。みたいなことなのかな… 適応課題・対立があるときには、自分のナラティブを脇に置く、という...
対人関係、組織間の関係において、わかっていないことが何かがわかっていない、というのは確かにと思わされる。 相手のナラティブで物事を捉える、前にまずメタ認知で自分のナラティブに気付く必要がある。みたいなことなのかな… 適応課題・対立があるときには、自分のナラティブを脇に置く、という意識を持つことを習慣付けたい。
Posted by
関係性を眺めることは、人と一緒に何かをしている全ての人に共通して言えることだなぁ。そんな俯瞰した視点を持ちたい。
Posted by
「ナラティヴ」という切り口で他者とのかかわりを見直すには新たな視点ではあるが、対話をもって相手の視点に立って関係性を構築するといった内容。 図解も多くイメージがしやすかった。 少しキレイな表現で書かれすぎかなという印象で、現実的に入ってきにくいなとは感じた。 具体的にどうすれば...
「ナラティヴ」という切り口で他者とのかかわりを見直すには新たな視点ではあるが、対話をもって相手の視点に立って関係性を構築するといった内容。 図解も多くイメージがしやすかった。 少しキレイな表現で書かれすぎかなという印象で、現実的に入ってきにくいなとは感じた。 具体的にどうすればいいか悩んでいる時には向かない気がするので、別のタイミングで読み直してみたい。
Posted by