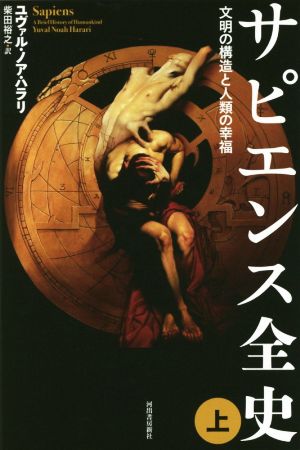サピエンス全史(上) の商品レビュー
途中まで読んで3年くらい電子積読していたのをようやく読み終えた。最初の方はほんと面白くてサクサク読めたけど、中盤くらいからはやや単調に感じた。それでも読んでみればそこそこ楽しめましたが。 以下、面白いと思った箇所を私なりに噛み砕いて記載します。 ホモ・サピエンスが現在に至るま...
途中まで読んで3年くらい電子積読していたのをようやく読み終えた。最初の方はほんと面白くてサクサク読めたけど、中盤くらいからはやや単調に感じた。それでも読んでみればそこそこ楽しめましたが。 以下、面白いと思った箇所を私なりに噛み砕いて記載します。 ホモ・サピエンスが現在に至るまで繁栄してこれて理由は、抽象的思考ができるからである。「言葉を使う」ことをもって繁栄をもたらせた説は良く聞くが、それだけでは不十分。言葉に準ずるようなやり取りは動物であってもしている。その言葉をもって抽象的思考をすることで、他の動物では成し得ない繁栄を続けてきた。 例えば、本著によると猿の群れというのは最大で100頭を率いるのが限界らしい。いかに優れたリーダーであっても、その行動や力といった具体性をもって統率できるのは100頭が限界。それ以上を率いようと思ったら、抽象的概念が必要となってくる。 例えば、本著では自動車メーカーのプジョーが例として使われているが、会社というのは一見具体的な存在のように思えるが、実際には抽象的なものでありプジョーなる具体的なものは存在しない。皆が、プジョーという抽象的概念を信じるから企業というものは成り立ち、そこへの帰属意識も生まれる。 仮にプジョーというブランドに圧倒的な価値を感じている人にとっては、その概念がありそこに属しているだけで愛社精神なども湧くだろうが、実際にはそんな人ばかりではないので、そうした人を繋ぎ止めるために、企業理念があったり事業方針がある。あるいは消費者に対してはCMを打ったりして良いイメージを作り上げたりする。 つまりは、多くの人を率いるためには「物語」が必要となる。そういえば、これも散々寝かせた挙句最近ようやく見終わった『ゲーム・オブ・スローン』 でティリオンが同じようなことを言っていた(見てない人にはさっぱりわからない)。 物語はその時々で、宗教、信念、目標…と様々な形態をとる。 これは会社経営と言うものを考える上で非常に示唆に富んだ視点だと感じた(私は経営者ではないが、一応それに近いところで仕事をしている)。 経営者は、具体的な能力や力や行動を以ってのみで支配をしようと思ってはいけない。具体をもって支配できるのは100人が限界なのは猿の群れと同様だ。その規模の会社であれば所謂「ワンマン社長」で成り立つかもしれないが、それ以上の社員を率いるには、「良い物語」が必要となる。 個別には100人以内に収まる部門、部署が存在し、それらを率いるリーダーはある意味具体的な支配力でやっていけるかもしれないが、彼らを更に統率するためには、強固な物語が必要となる。 「企業理念なんか誰も気にしてないでしょ?」みたいなのは大きな間違いで、会社という抽象的な存在を支えるには必ず理念が要る。ただし余程のブランドホルダーでもない限りは、そこで働く人を繋ぎ止めるのに、企業名と理念だけでは不十分。理念に属した中長期の事業計画があり、それをきちんと「物語」として機能させる必要がある。 こうしたことを軽視して、ただ強いリーダーが組織を強くする、あるいは強い現場が組織を強くする、と思い込むのは、ホモ・サピエンスの繁栄の歴史を軽視する愚行とも言える。繰り返しになるが、100人を率いたいならそれで良いが、その何倍の人を率いるには良質な物語を作り、語ることが必要なのだ。 偉い真面目に語ってしまった。下巻を読むのにまた3年かかりそう。
Posted by
著者は歴史学者。サピエンスの歴史、進化、どうやって地球上で今日の最強の地位を築いたのか、興味深い視点、観点が多い。 認知革命によって、どうやって人類が地球という生態系の中でこれほどまでに繁栄できるようになったのか、農業革命によって人類は何を得たのか、貨幣とは何なのか、丁寧に説明...
著者は歴史学者。サピエンスの歴史、進化、どうやって地球上で今日の最強の地位を築いたのか、興味深い視点、観点が多い。 認知革命によって、どうやって人類が地球という生態系の中でこれほどまでに繁栄できるようになったのか、農業革命によって人類は何を得たのか、貨幣とは何なのか、丁寧に説明されていて面白い。
Posted by
重厚感があるが読み始めると止まらない。 ・むしろそれは、全く存在しないものについての情報を伝達する力だ ・その秘密はおそらく、虚構の登場にある。厖大な数の見知らぬ人どうしも、共通の神話を信じることによって、首尾よく協力できるのだ ・歴史を動かす重大な要因の多くは、共同主観的なもの...
重厚感があるが読み始めると止まらない。 ・むしろそれは、全く存在しないものについての情報を伝達する力だ ・その秘密はおそらく、虚構の登場にある。厖大な数の見知らぬ人どうしも、共通の神話を信じることによって、首尾よく協力できるのだ ・歴史を動かす重大な要因の多くは、共同主観的なものだ ・自由連想と網羅的思考法は、分類と官僚制に道を譲ったのだ(書紀体系の発明) ・ホモ・サピエンスの異なる集団どうしの生物学的区別は、無視できるほどしかない ・インド社会の複雑さやアメリカ大陸の人種的ダイナミクスは生物学では説明できない。 ・想像力が生み出した虚構を、残忍で非常に現実味のある社会構造に変換した出来事や事情、力関係を学ぶしかない →歴史を学ぶ重要な理由の1つ (想像上のヒエラルキーと差別)
Posted by
農業革命が人々を貧しくさせた、のが目から鱗だった。来たるスタグフレーションの時代。みんなが貧しくなる時代。考えさせられる。
Posted by
YouTube大学で本書の紹介がされていたので、いつか読んでみたいと思っていた。 チャレンジ出来て良かった。 人間とは何か、どういう構造に基づいて今があるのか、歴史や、宗教、社会学など、 多角的に書かれている。下巻もチャレンジしたい。
Posted by
世界史を学んだ人にとっては簡素に映るかもしれないが、読み進めるほどに頭の中の年表が輪郭をハッキリさせてくる感覚が快適。
Posted by
全史。社会史や経済史と言ったジャンルではなく、ホモ・サピエンスに限ったカテゴリーでもない。 サピエンスの全史。それは教科書には乗っていなかった、わたしたちの歴史だった。 そも〝歴史〟は〝人間社会が経てきた変遷・発展の経過。また、その記録。〟とある。〝人間〟は〝ひと。人...
全史。社会史や経済史と言ったジャンルではなく、ホモ・サピエンスに限ったカテゴリーでもない。 サピエンスの全史。それは教科書には乗っていなかった、わたしたちの歴史だった。 そも〝歴史〟は〝人間社会が経てきた変遷・発展の経過。また、その記録。〟とある。〝人間〟は〝ひと。人類。〟とある。 人はホモサピエンスだけじゃなかった。そんなことすら知らなかった。200万年も繁栄した人類もあった。絶滅の末、最後に残った人類がホモ・サピエンスだった。もう驚愕である。 そんな〝唯一生き残った人類種〟の仕組みは、脳がとりわけ発達してるわけでも、肉体的に優れているわけでもないというのだから、私は、自分について全く知らなかったわけだ。 私たちの最大の特徴である〝虚構〟に基づいた〝共同主観による連帯〟。言葉にされると背筋が凍るような思いになる。 厳密に言えば会社は存在しない。実態すらない。だけど問題なく私たちは空想の産物である会社に勤め、同じく空想の信用である貨幣を使い生計を立て、ご飯を食べている。 仮想通貨を思い浮かべる人もいるかもしれない。 けど、そもそも通貨そのものが仮想概念だ。 そんな私たちの世界は恵まれているのか?幸福なのか? 私は大きな誤解をしていたが、認知革命に次ぐ農業革命は、人類にとって最適解であって、個人にとっては地獄の始まりだった。 家畜は疫病を流行らせ、天災や飢饉による貯蓄の必然性が未来への不安を強め、持つものと持たざるもののヒエラルキーを生み、労働と搾取に裏付けられた飽くなき発展が始まった。 小麦はそれまでマイナーな植物だったのに、今では最も繁栄している。家畜もそうだ。 経済の正体はDNAの複製意欲に思える。 科学革命は資本主義と結びついて、統一のビジョンを持つ〝帝国〟によって拡大と連携を繰り返していく。 まるで、ウイルスが急激な増殖によって人体を蝕んで行くかの如く、人類種そのものが、飽くなき感染と拡大を繰り返している。 人類の理不尽に対する著者の見解は見ものだ。女性、黒人とへの差別には、穢れの意識が強く働いているという。 病気や死などの生理的な現象と結びついた、差別神話は感覚や潜在意識まで刻まれてしまってる。社会の至る所に差別のメタメッセージを読み取ることができるかもしれない。 権力者は神話を用い、自身の保身を確保してきた。よくよく考えみれば、誰か特定の人間が得するようになっているのが世の仕組みだ。 常識や道徳にまで落とし込まれ、教育という皮を被った、この構造を支えるための洗脳行為によって、信者が疑問を持った人間を潰しにかかる。普通は、とか、当たり前、を用いて。 こうした差別、ヒエラルキー、搾取が、持つものによって想像上の秩序となって平和とよばらる状態が維持される。 これを著者は脱出不可能の牢獄と表現する。 ここまでマクロな目線で見ると、甘い汁を啜っているグループも搾取され貧困や差別に喘ぐグループもこの、広大な人類種の繁栄の一部分にしか思えなくなってくる。 そもそも自分の意思で行動しているのか? DNAの意識に突き動かされているだけだとしたら? と本書からは壮大で複数の視点を獲得できる。 自分という生き物の正体が少しずつ明らかになってくる感覚が、ページをめくるたびに仄かに差す。 〝自分〟は自分だと考えている主体ではない、共同主体と、生理的欲求に基づいて生きている。これが上巻のエッセンスと言える。 わたしたちは、思っているより、自分自身のことをまだ知らない。それが分かる一冊。
Posted by
ホモ・サピエンスが起こした3つの革命の内、上巻では、認知革命、農業革命によって、ホモ・サピエンスがどのような進化をしてきたか、どのような影響を与えたか、という内容だった。 なぜ、ホモ・サピエンスがここまで繁栄できたのか、人類なら一度は読むべき傑作。
Posted by
再読。 1度目も衝撃的だったけど、 再読はさらに深くじっくり読めたので、 日常生活の中でも何かにつけてこの本を引き合いに出して考えることが多くなった。 筆者ユヴァル・ノア・ハラリは、 人類誕生から今日現在まで3つの分岐点を 認知革命、農業革命、科学革命と名づける。 まず上巻で...
再読。 1度目も衝撃的だったけど、 再読はさらに深くじっくり読めたので、 日常生活の中でも何かにつけてこの本を引き合いに出して考えることが多くなった。 筆者ユヴァル・ノア・ハラリは、 人類誕生から今日現在まで3つの分岐点を 認知革命、農業革命、科学革命と名づける。 まず上巻ではこのうちの2つ、 主に認知革命と農業革命について 詳しく語られていく。 まず認知革命で人類は「虚構」を信じ、 その「虚構」を他人と共有することによって 見知らぬ大勢の他人といろんな協力をできるようになった。 これ、当たり前のことなんだけどよくよく考えてみるとめっちゃ凄い。 「虚構」と一括りに言われると、 神話とか宗教的なことかな?ふーん…って思ってたんだけど、 今現在当たり前のように流通する貨幣、市場経済、モノの善悪、多様性を素晴らしいとする価値観、 果ては人権なんかまで、 ああ、確かに身の回りにあるほとんどのものは 「虚構」で回っているんだな、 ということに気づかされる。 他の動物に比べ腕力などに劣る人類が、 生存戦略として持っているもののかなり大きな部分で「社会性」というのがあるけど、 この「社会性」を根本で支えるのが他者と虚構を共有できる能力なんだよな。 この辺を読んでいるだけでなんか賢くなった気分になるし、いろいろ感想や新たな気づきがどんどん浮かんでくる。(そしてこうやって感想を書いておく頃にはどんどん忘れている) その熱も冷めないままに農業革命の部に突入すれば、有史以来、人類が選んできた種としての選択は果たして正しいのか?と 足下のゆらぐ記述にぶちあたる。 そして種としての成功と合わせて個としての幸せについて、いろいろ深く考えさせられるのだ。 …いやマジで小麦すげぇな。 また、振り返って人類も認知革命を経ているという以外に実はそう他と変わらない1種の動物であるという事実がとても重たい。 第3部、人類の統一では帝国についての記述があるんだけど、ウクライナ危機の今読み返すと、なんとも表現できない不気味さを感じてしまった。 一読目では全然感想が纏まらなくて、 とりあえず再読して備忘録にするつもりが、 読み進めるうちにどんどん思考が拡散されてやっぱり上手く纏められないや。 いやぁ、なんにせよ一言に尽きる。 この本、凄いわ。 とりあえず下巻も再読するぞ。
Posted by
人類史に触れるために読んでみたが、人類の進化について様々な可能性を読者に想像させる一冊だった。 虚構がなぜ生み出されたのか。それにより、詳細な目的を共有した集団意識生まれた。 また、男女間の格差ひとつとってみても、世界のどの場所でも同じように起こっているが、その理由につ...
人類史に触れるために読んでみたが、人類の進化について様々な可能性を読者に想像させる一冊だった。 虚構がなぜ生み出されたのか。それにより、詳細な目的を共有した集団意識生まれた。 また、男女間の格差ひとつとってみても、世界のどの場所でも同じように起こっているが、その理由については明らかになっていない。 本書は、決して断定することなく、あらゆる角度から疑問点について追及している。革命ごとのつながりが明らかにるので、より興味を引き付けられる。 また、つながりを明らかにすることは、歴史だけでなく現代の私たちにも十分通じるところがあると思う。
Posted by