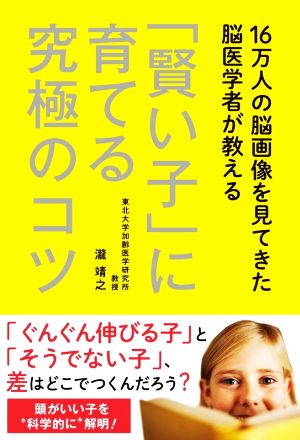「賢い子」に育てる究極のコツ の商品レビュー
脳医学者が教える「賢い子」の育て方を紹介した本。「好きなこと」「好奇心」が大切であること。3つの秘密道具は、「図鑑」「虫取り網」「楽器」であること。脳の成長年齢マップ:0歳から図鑑・絵本・音楽、3歳から楽器・運動、8歳から語学、10歳から社会性・コミュニケーション能力であること。...
脳医学者が教える「賢い子」の育て方を紹介した本。「好きなこと」「好奇心」が大切であること。3つの秘密道具は、「図鑑」「虫取り網」「楽器」であること。脳の成長年齢マップ:0歳から図鑑・絵本・音楽、3歳から楽器・運動、8歳から語学、10歳から社会性・コミュニケーション能力であること。親の役割は「好奇心の種をまくこと」「子どもの伸びやすい時期を見つけて背中を押してあげること」。脳医学からはとにかく「好奇心」がものすごく大切なのだということを改めて認識した。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
とても興味深く読んだ。 大事なのは知的好奇心。 知的好奇心を育むには? 3~4歳までの好き嫌いが出てくる前に、遅くとも3歳までに「図鑑」に触れさせること。ただ、それだけではなく、「バーチャルの知識」と「リアルな体験」をつなげてあげること。これが重要。そして、親も図鑑が好きだということを示すこと。短時間でもいい、できる範囲で毎日。これを結びつけるアイテム(例えば虫取り網)があるとなおGood。 加えて、親がかける言葉も工夫する。「何のはっぱかな?」「帰って図鑑を見てみよう!」それが子供の興味を広げるコツなのだ。1日ひとつは新しいことを教えてあげよう!まさにこれがキーワード!! 次に、脳の成長過程上、後ろからつくられ、前から壊れていくという仕組み上、子供の年齢に合わせたものが大事。 0歳~:図鑑・絵本・音楽 3~5歳:楽器・運動 8~10歳:語学 10歳~:コミュニケーション能力 さらに、これは基本だけれど、朝食と睡眠。まあ、当たり前といえば当たり前か。 ゲーム・スマホ…させたくないことをどうするか。止めようとすると逆効果。世の中にはゲームより面白いことがあるという実感を子供にもたせるしかない!それ以外の面白いことを見せる努力を惜しまない。ときには怒鳴るかもしれない、でもその悪影響を子供に身をもって体験させていると割り切ることがおすすめされている。それくらいの気持ちでいないといけないのだなと思わされた。 最後の、これはまさに本当にそうだと思う。私自身、子どもを産みたかったのはある意味これに尽きる。「子供も大人も、好奇心を持つことで、いつまでも健康に、自己実現をしていくことができる。毎日を、より楽しめる。」 子供がうまれて、イライラすることがあっても、ここに戻りたいと思う。子供と一緒により楽しい人生を送りたい!!それが人生の至上命題ではないか?そして、輝きの源がきっと好奇心だ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
わかりやすい内容だった。 年齢別に何をしてあげたらいいのか書かれているのが、実践しやすい。 まずは絵本 次に3-5歳で音楽 そして8-10歳で語学。 でも何よりも好奇心を大切にしてあげること。 叱り過ぎずに、これが好きなんだね、って言ってあげたい。
Posted by
ついつい口出ししたり、無意識のうちに否定的な言葉を使って子供の成長を妨げてしまう時がある。子供の好奇心を大切にしたい。一人一人の子供の特徴を観察して、個々の性格に合わせた言葉のかけ方や対応ができるようになりたいと思えた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
好奇心を呼び起こすもの(図鑑や楽器)を与えて、子が興味を持ったらその後押しをしてあげる。それが親の役目。 絶対音感の獲得やバイリンガルに育てることが重要なことのように書かれているがこのへんは人それぞれだと思う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
非常に読み易く1時間かからず読了した。最近読んでいた子育て、教育本とやはり根本は同じなのだなと思った。著者自身も子育て中とのことで、お子さんに対する愛情を感じた。読みながらニコニコしてしまうくらい優しい文章。図鑑でインプットして現実と結びつけるというのはとても納得!ピアノも私や夫が毎日弾いているので自然に興味を抱いてくれたら嬉しいな。英語は小学生以降で良いかな。"親は努力はしても無理はしない" この言葉が一番響きました。子供を誰かと比べない。その子自身をよく観察する。本当にこれに尽きる。
Posted by
著者後出の、グングン伸びる〜 の方を先に読んでしまったため、 特に目新しい発見はなし。 脳の成長が後ろから前で、 脳の後退は前から後ろ。 というのは、唯一面白い発見。
Posted by
3歳頃から絵本の読み聞かせは、非常に脳に良いとされている。3歳から5歳までは音楽や外で遊ぶことを優先させた方が良い‼︎英会話は8歳頃からでも大丈夫。英語の前に先に日本語を‼︎10歳からはコミュニケーション能力を学ばせることが大切。親も積極的に子供にコミュニケーションができる場所を...
3歳頃から絵本の読み聞かせは、非常に脳に良いとされている。3歳から5歳までは音楽や外で遊ぶことを優先させた方が良い‼︎英会話は8歳頃からでも大丈夫。英語の前に先に日本語を‼︎10歳からはコミュニケーション能力を学ばせることが大切。親も積極的に子供にコミュニケーションができる場所をセッティングする。 また、子供にとって一番良くないのは、無関心であることがよくない。 英会話は小さい頃からさせた方がいいとか、いろいろな論説がある中、脳科学的には、8歳頃からでも充分であるということ。理由は、余りにも小さい時に、習得すると、活用しないことは、脳から消えていくから。など、たくさん勉強になった‼︎
Posted by
脳の成長に合わせた取り組み方 0歳〜図鑑、音楽、絵本 3歳〜楽器、運動 8歳〜英語 賢い子に育てるコツは好奇心を伸ばすこと。 脳医学に基づいた内容なので説得力があった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[超要約] 子供を賢く育てる方法は、好奇心を育てること。 図鑑などを使い、子供の好奇心を伸ばす ⇩ バーチャルな知識とリアルな体験を結びつける 1日1つは新しいこと教えるら、 ただ好奇心を持てさえすれば、99パーセント忘れていい そして、親に応援されている安心感 何歳になってめ新しい能力 は身につけられる 今の環境で、してあげられることを考える 親は努力はしても無理はしない 自信のある子 睡眠大事! 運動大事! 叱る、怒るはよく考えて 口を開けば注意→子供に恒常的ストレス→脳を萎縮 怒りすぎは要注意!
Posted by