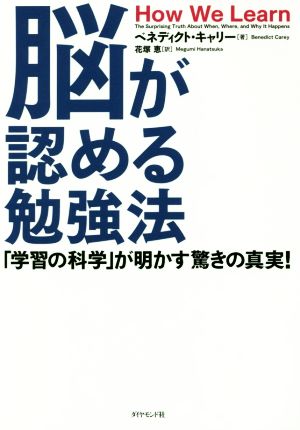脳が認める勉強法 の商品レビュー
この本を読んでると“簡単な”問題しか解いてこなかったんだなと思った。得た知識を応用し、使うなんてそんなことを意識したことはない。
Posted by
正直まねしづらい。 できたらそれをやるやり方が知りたいと読んでいて思ってしまう。自分には合わなかった
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
めちゃくちゃためになった。 一度覚えたことは必ず脳内にある。しかし、それを探索する能力が長けているか欠けているかで思い出せるのかが決まる。 つまり、探索能力を伸ばすことが大事。 もう一回読む
Posted by
なんでこの本を買ったのか忘れてしまったのだが、ずっと本棚にあって放置されていたのを最近になって読み始め、ゆっくり読み進めてようやく読了。 タイトルがあまりにもなんていうか「あやしい自己啓発本」っぽい邦題なのでちょっと警戒していたのだが(じゃ何で買ったんだw)、これは面白かった!...
なんでこの本を買ったのか忘れてしまったのだが、ずっと本棚にあって放置されていたのを最近になって読み始め、ゆっくり読み進めてようやく読了。 タイトルがあまりにもなんていうか「あやしい自己啓発本」っぽい邦題なのでちょっと警戒していたのだが(じゃ何で買ったんだw)、これは面白かった! 原題の「How We Learn」、つまり「われわれはどのようにして学習するのか」の通り、学習に関するさまざまな研究や理論を紹介している極めて真面目で実は硬派な本だ。 楽して頭がよくなる!勉強ができる裏ワザ!みたいなのを期待するとつまらないかもしれないが、実はよく読むと「学習の研究結果から理に適った、効率的な記憶や勉強法」がふんだんに書かれていることがわかる。 忘却曲線、分散学習、ツァイガルニク効果、などなど「これ受験前に読んでおけばよかった…」という内容がもりもり。睡眠相と学習内容の関係などは、理論上はそうかもしれないけどそこまでコントロールするのは難しいでしょ、というツッコミを入れたくなったりはするものの読んでいて楽しい。 集中してひとつのことを繰り返すよりはいろんなことを折り混ぜて練習する方が獲得にはよい、とか生活の中で実感することも書いてあったりして、なるほどなあと思う(私の場合、ひとつの曲を覚えるのに何度も繰り返し聴くより別の曲も混ぜて聴く方が覚えやすい気がしていたので)。 著者はベテランのサイエンスライターとのこと。 翻訳もよいのだろうが、原文も読みやすい、読者に親切な文章なのだろうなと推測できる、わかりやすくて興味深い一冊だった。 技能の習得などにも有用なので、何かを学ぶ機会のある人にはお勧めの本。
Posted by
同じ場所で出来るようになるまで集中して反復演習するという勉強法が実は間違いであった。一度忘れる、時間を分ける、テストの前にテストをする、場所を変える、騒がしい場所が良い、中断する、一つのことをしない、別のことをやる、寝る。これが記憶の研究から分かった正しい勉強法である。 こう...
同じ場所で出来るようになるまで集中して反復演習するという勉強法が実は間違いであった。一度忘れる、時間を分ける、テストの前にテストをする、場所を変える、騒がしい場所が良い、中断する、一つのことをしない、別のことをやる、寝る。これが記憶の研究から分かった正しい勉強法である。 こうやって並べると、よくないとされていたことが実は正しかったということになる。ところで、行き詰ったときに気分転換でコーヒーを飲んだり、あきらめて寝たりした後、悩んでいたことが嘘のように理解できるようになったという経験があるのではないかと思う。これは「中断」した後も脳は考え続けており、しかも無意識のうちにさまざまな検討をしているからだという。また、思い出すときに記憶が定着しやすいということも分かっており、それが「一度忘れる」「時間を分ける」ということであり、強制的に思い出す状態を作り出すのが「テストの前にテストをする」ということになる。「場所を変える」「騒がしい場所」は思い出すための取っ掛かりを増やすことにつながる。 従来の勉強法である反復演習も間違ってはいないが、これは0を1にするのには適しているが1を10にするのには向いていないということである。また、同じ場所で同じことを繰り返すと「その場所」でなければできなくなってしまう。場所によらず、さらに応用力を身に付けるためには「場所を変える」「一つのことをしない」「別のことをやる」必要があるということである。 科学的な裏付けによってこれまで勉強のときにやってはいけないとされていたことが、実はやった方が良いものであったというのは非常に興味深い。中断してコーヒーを飲む、敢えて寝てしまうなどは無意識のうちに正しいことをやっていたことになる。「さあやるぞ」といって机に向かうよりも成り行きに任せるような勉強の方が案外うまくいくのかもしれない。
Posted by
大脳生理学から、学習を考察した書。 ブームのはしりだったような。闇雲に経験則をふりまわすのではなく、科学的に実証された方法論で学習を進めていくことは、時代にあっていると思います。
Posted by
記憶に定着しやすい学習の仕方として、 学習する時に、場所や音楽など環境を変えながらやった方がよい。 勉強時間を分散させる。1日後、1週間後、1か月後、など。間隔を広くとると、長く記憶にとどまる。 流暢性の幻想に囚われないために、覚える時間と練習する時間の比率は4:6程度がよい。 ...
記憶に定着しやすい学習の仕方として、 学習する時に、場所や音楽など環境を変えながらやった方がよい。 勉強時間を分散させる。1日後、1週間後、1か月後、など。間隔を広くとると、長く記憶にとどまる。 流暢性の幻想に囚われないために、覚える時間と練習する時間の比率は4:6程度がよい。 自己テストや事前テストをすることが効果的。 思い出さなけばならない状況を作ることが有効ということ。 休憩を入れながら、取り組んだ方が解決を思いつきやすい。 途中でやめた方がよい。ずっと脳は考える。 ランダムに様々なやり方で練習した方が結果的に定着する。 PLM、知覚学習モジュールを活用して、五感を活用した方がよい。 睡眠も大事。 環境要因、生態学的要因、課題要因に有効に働く方法を示してくれている。
Posted by
難しかったです。 スラスラ読めなくて途中で終わってしまいました。 翻訳された本は表現が入ってきにくくて難しい。 ただ,実験や理論を詳細に説明されていたので,ちゃんと読めればすごく有益な本だと思いました。
Posted by
結論、 没入する方向でやっていれば大体において合っている。 なぜなら、それは脳が感じていることであり、脳は成長を楽しいと感じ、成長がなければ面白いと感じなくなる。 インターリーブ学習や分散学習は、 反復練習による限界を感じている場合には、超有用な学習法で、 集中力が明らかに増...
結論、 没入する方向でやっていれば大体において合っている。 なぜなら、それは脳が感じていることであり、脳は成長を楽しいと感じ、成長がなければ面白いと感じなくなる。 インターリーブ学習や分散学習は、 反復練習による限界を感じている場合には、超有用な学習法で、 集中力が明らかに増すのを実感する。 それはつまり、 脳の神経回路が新たに構築されて、進化し続けていっていることを意味しているのだろう。 楽器演奏の技術習得に活用しまくれる。
Posted by
一度覚えたことを忘れる。しかし一度忘れたことを思い出す傾向もある。 映像、写真、絵、風景などと結びついていると、数日後に浮かび上がってくる。 2回目に思い出したほうが、よく思い出せる。 音があったほうが、記憶しやすい。 分散学習または分散効果。一度に学習するより、少しずつ勉強す...
一度覚えたことを忘れる。しかし一度忘れたことを思い出す傾向もある。 映像、写真、絵、風景などと結びついていると、数日後に浮かび上がってくる。 2回目に思い出したほうが、よく思い出せる。 音があったほうが、記憶しやすい。 分散学習または分散効果。一度に学習するより、少しずつ勉強するほうが脳にとどまりやすい。 ジェームズメソッド=英語の学習法・五感を使って覚える。 二ヶ月空けた復習のほうが良く覚えられる。毎回が新鮮な記憶になるほうがいい。一度、思い出すために忘れる。 間隔をあけて復習する。 ふ化段階にひらめきが出る。 完了していない目標は、長く記憶に残る=ツイニガル効果。 チャンスは、それに意識を向けること。 何回も繰り返して練習しない。練習するなら、いろいろなことを練習する。人は対応を覚える。 同じ種類の問題を解くのではだめ。復習を兼ねてかつての問題もいっしょにやる。
Posted by