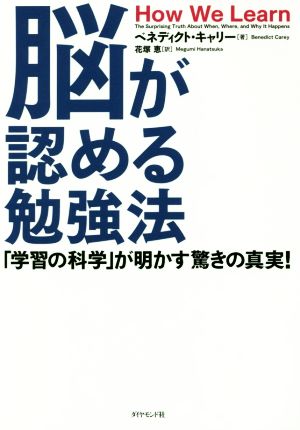脳が認める勉強法 の商品レビュー
脳科学の方面から、どのような時と場所と方法で勉強すれば効果があるのかについて書かれています。脳の働きというものを、どのように記憶と考え方の向上につなげていくのか。今までもこのような本は出ており、それと一部重なるものもあるのですが、具体的な例が豊富にあり、そのため分かりやすく、かつ...
脳科学の方面から、どのような時と場所と方法で勉強すれば効果があるのかについて書かれています。脳の働きというものを、どのように記憶と考え方の向上につなげていくのか。今までもこのような本は出ており、それと一部重なるものもあるのですが、具体的な例が豊富にあり、そのため分かりやすく、かつ楽しく読むことができました。またすぐに実行できるものが主で、日々の勉強に役立てることができることが多数あることが良かったです。勉強は無理してするものではなく、また諦めることなく続けていくことということかと思います。筋肉を付けるような気持ちで、脳を鍛えていくこと。その方法が学べるのではないかと思います。
Posted by
脳の記憶メカニズムに即した勉強法を提示する本書。 ただ単に方法をわかりやすく紹介する簡易版と違い、研究者たちによる数々の実験、そして発見に至るまでの経緯を明快に示してくれる。読者の多くは自分の勉強法の改善のため、または他者への教授のために本書を手に取るのだと思うが、その目的は...
脳の記憶メカニズムに即した勉強法を提示する本書。 ただ単に方法をわかりやすく紹介する簡易版と違い、研究者たちによる数々の実験、そして発見に至るまでの経緯を明快に示してくれる。読者の多くは自分の勉強法の改善のため、または他者への教授のために本書を手に取るのだと思うが、その目的は表面上の理論理解だけでは達成できない。背景にある経緯や実験結果まで知ることで、本当の意味での「効率的な勉強法」を深く理解することできるのではないか。
Posted by
文句なく面白かった。脳はまだまだ不思議なことを隠している。 様々な実験の結果から、どのように勉強したら効果的かが書かれている。直感やいままで信じていたことと違う事実が示されると、「おっ」となる。それが随所に現れる。 一人でも実験できるんだなあという驚きと、なぜ学生時代に私自身...
文句なく面白かった。脳はまだまだ不思議なことを隠している。 様々な実験の結果から、どのように勉強したら効果的かが書かれている。直感やいままで信じていたことと違う事実が示されると、「おっ」となる。それが随所に現れる。 一人でも実験できるんだなあという驚きと、なぜ学生時代に私自身で実験できなかったのかという悔しさがある。
Posted by
How We Learn: The Surprising Truth About When, Where, and Why It Happens http://www.diamond.co.jp/book/9784478021835.html , http://diamond...
How We Learn: The Surprising Truth About When, Where, and Why It Happens http://www.diamond.co.jp/book/9784478021835.html , http://diamond.jp/category/s-nougamitomerubenkyouhou
Posted by
どんな方法で勉強すれば一番効率よく学ぶことができるか。 脳の仕組みから学び方を考察していきます。 柔術を学ぶ、という点においてもなぜ色々な人の手を取って稽古することが良いのかがこの本を読むとよくわかります。 学ぶ上では量より質という考え方、質よりも量という考え方が二つあると...
どんな方法で勉強すれば一番効率よく学ぶことができるか。 脳の仕組みから学び方を考察していきます。 柔術を学ぶ、という点においてもなぜ色々な人の手を取って稽古することが良いのかがこの本を読むとよくわかります。 学ぶ上では量より質という考え方、質よりも量という考え方が二つあると思いますが大事なのはバランス。 とはいえ、そのバランスの取り方が難しいんですけどね。 面白かったです。
Posted by
題名から How to本のような印象を受けるが、中身は、ジャーナリストによる論文レビュー。そのためAmazon等には辛口の書評が多いが、入り口を間違えなければ良書。「オレはこう思う!」的な自己啓発本よりも、研究成果を紹介しながら自己の経験を合わせて進む本書の方が、理解しやすく納得...
題名から How to本のような印象を受けるが、中身は、ジャーナリストによる論文レビュー。そのためAmazon等には辛口の書評が多いが、入り口を間違えなければ良書。「オレはこう思う!」的な自己啓発本よりも、研究成果を紹介しながら自己の経験を合わせて進む本書の方が、理解しやすく納得感も高い。 有名なエビングハウスの忘却曲線は、ランダムな文字列による実験の結果らしく、意味のある言葉の場合は異なる、など、目から鱗なネタが多い。
Posted by
脳科学に基づく効果的な学習方法の解説書。何かを覚えるには、睡眠を挟んで直前直後が良い。復習は翌日、翌々日、1週間後、一ヶ月後のサイクルが効果的。暗記テストは普通に就寝し、深い眠り、早朝復習。運動能力や創造的思考は、遅くまで起きて準備。学習の途中にインタンバルを入れる事は有効。
Posted by
環境(場所)に変化をつける 方法を変える(読む、議論、キーボード入力、手書き、鏡、BGM 睡眠 勉強時間を分散させる 覚える1:自己テスト2 行き詰ったら中断して別のことをする(その間も脳は無意識にそのことを考えている) 一度の練習時間に複数のことを混ぜる(インターリーブ) 知覚...
環境(場所)に変化をつける 方法を変える(読む、議論、キーボード入力、手書き、鏡、BGM 睡眠 勉強時間を分散させる 覚える1:自己テスト2 行き詰ったら中断して別のことをする(その間も脳は無意識にそのことを考えている) 一度の練習時間に複数のことを混ぜる(インターリーブ) 知覚学習PLM 「秩序を乱す何か、その場にそぐわない何かを目にすることが、事実上脳を目覚めさせる。っして、『なぜそれがここにあるのか?』と潜在意識に問いかけて、その情報を掘り下げさせる」 種類を混ぜた練習を行うと、学ぶ力全体が向上し、ものごとの違いを理解する力が高まる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
学習における分散効果について いわゆる記憶の力には保存する力と検索する力の二種類がある。保存する力は衰えることはないが、検索する力は強化していないとすぐに衰える。記憶した時の背景や環境を手がかりとして思い出すことも多く、例えば覚える時と同じ色調の紙に書く方が別の色調の紙よりも思い出しやすいし、BGMが流れている環境で覚えたことは同じBGMがあると思い出しやすい。ただし、BGMが違うと思い出す力はBGMなしと同じなので、あまり意味はないかも(Smith, Am J Psychol 98:591-603, 1985) 学習においては分散効果が重要になる。一気に集中するよりも何日かに分けたほうがよい。本書ではテスト、インターリーブ、睡眠の効果についても述べられているが、全て分散効果の一型とみなすべきなのかもしれない。一夜漬けは一夜漬けで意味はあるものの、あとに残らない。1−2日空けて反復すると一週間ほど記憶が残る。一ヶ月空けると一年残る。テストも有効で、三分の1の時間を覚えることに使い、残り3分の2を暗唱に使うのが一番効率よく覚えられる。 バドミントンのサーブの練習を調べた研究によると、同じ種類のサーブを続けて練習し、次のサーブの練習に移るよりも、複数のサーブをランダムに練習する方が上達する。他の運動でも同様の結果が確認されており、このように他の行為を差し挟むことをインターリーブという。インターリーブで印象的なのは、被験者は同じ練習を反復するブロック学習のほうをランダム学習よりも高く評価していたということだ。しかし、実際にはランダム学習のほうが効果が高い。ブロック学習による反復練習はすぐに技術が向上するような幻想を生みやすい。 ノートに線を引く、書き写す、すぐに反復する、などの受け身の行為は実際には理解を深める効果がないにも関わらず、自分が知っているかのような錯覚を起こす。(流暢性の幻想) 睡眠により記憶が定着するという知見も分散効果の一種ではないかという。 レム睡眠はパターン認識や創造力を必要とする問題解決、情動を伴った記憶に、Stage2は運動に関する学習に、SWSは陳述的記憶の定着に関係がある(これはSWS断眠の研究からもある程度確からしい)のではないか。だからピアノの発表会のようなスキルを必要とする時やパターン認識などが要求される数学の試験前などは朝寝をした方がよいというが、やや突っ走り過ぎか。昼寝はSWSとレムの比率が多く、一時間程度の昼寝は有効だというが、これも証拠はやや希薄。
Posted by
勉強の仕方でその効果が変わることがわかったら、だれもがその方法を知り、そして実践したいと思うだろう。 この本で行っているのは効果が高い勉強法は復習をすること。そして自分自身の理解を確認するテストをする事。 また復習や自己テストを実施する感覚によっても効果が違う事などを各種の実験...
勉強の仕方でその効果が変わることがわかったら、だれもがその方法を知り、そして実践したいと思うだろう。 この本で行っているのは効果が高い勉強法は復習をすること。そして自分自身の理解を確認するテストをする事。 また復習や自己テストを実施する感覚によっても効果が違う事などを各種の実験の結果をもとに紹介している。 本書は主に4つのパートからできており。 ・脳細胞がどのように形成され、新しい情報をどう保存すかの説明 ・情報を保持する力を高めるテクニックの紹介 ・問題解決力の向上にいかせるテクニック ・テクニックの効果を高めるために無意識を活用する方法 特に2つ目の情報を保持するテクニックの紹介は今後自分や子供の学習に取り入れたいと思った。 分散学習:一気に集中して勉強するのと、勉強時間を分散するのとでは、覚える量は同じでも脳にとどまる時間はずっと長くなる。 試験までの期間によって最適な学習間隔は違うが、学習した翌日と1週間後に復習すると脳の情報保持の効果が高い事が理解できた。 そして切羽詰まった時の一夜漬けは、翌日の試験当日の記憶という点では分散学習と効果は同じだが、その記憶は長くとどまらないので長い目で見ると効果的な方法とは言えないことが理解できた。 流暢性:情報が最適に素早く処理し出力する能力の事。 その時言えた公式などは翌日以降も思い出せると信じてしまうが、人は忘れるという事実を忘れてしまい、これ以上勉強する必要はないと思い込む。 記憶は、受動的に繰り返されたことよりも、受動的に繰り返したことの方が強く脳に刻まれる。 例えば、何かを暗記しようとしてほぼ覚えたとき、時間をおいてから記憶をたどって思い出す方が、もう一度本を開くよりも効果が高い。 覚える時間と練習する時間(暗唱する時間)の理想的な比率は1:3 テストという形で勉強したことをすぐに思い返すことは、学んだことを記憶にとどめ易くするために効果的。 問題解決の4つのプロセス 1.準備:論理的思考または創造性が必要となる問題に奮闘している時間 2.孵化(インキュベーション):問題を一時的にわきに置いたときにはじまる。無意識な知的活動。問題そのものを一度構成する要素まで分解し再度組み立てるなど。 3.ひらめき:アハ体験を得る瞬間。解決策が突如現れる。 4.検証:ひらめいた問題が本当に問題解決に繋がるかを確かめる。 学習効果を高めるQ&A(興味があったものを抜粋)P336 ・勉強のルールを設ける必要はあるのか?(勉強する場所を決めるなど) 決める必要はない ・勉強や練習に適量は存在するのか どれくらい勉強するかよりも、どのように勉強時間を配分するかの方が重要 ・詰め込みはいけないのか 必ずしもそうとは限らないが、詰め込みで覚えたことはあとから思い出すことが難しいという事を理解する必要がある。 ・自分で自分にテストをすることは役に立つのか? 非常に役に立つ。自分の理解を試す自己テストは最も効果の高い学習テクニックの1つ ・授業で取ったノートの復習はどれくらい役に立つのか 復習の仕方によって変わる。ただノートを見返す受動的な方法ではなく、自己テストを実施するなど能動的な方法を実施する。
Posted by