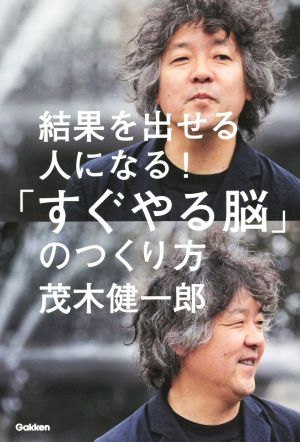結果を出せる人になる! 「すぐやる脳」のつくり方 の商品レビュー
脳の抑制機能が効いているため、すぐやれなくなっている。 この機能を外すにはあまり深く考えないことを習慣化するたのこと。 自分がしていることを特別なものと考えない。 ジョギングを習慣化するためにまず散歩から始めるというように敷居を下げる。 脳内ダイエットとはやらない事を決めて、脳内...
脳の抑制機能が効いているため、すぐやれなくなっている。 この機能を外すにはあまり深く考えないことを習慣化するたのこと。 自分がしていることを特別なものと考えない。 ジョギングを習慣化するためにまず散歩から始めるというように敷居を下げる。 脳内ダイエットとはやらない事を決めて、脳内に空き地を作ること。 すぐやる脳をつくる3法則 1.瞬間トップスピードを習慣化する。 やると決めたらすぐやる。 2.雑談の時間を作る。 3.ベストエフォート方式。 あきらめてやらないよりも、途中からでもやった方がいいという考え方。 やれる範囲のことをやる。 体を鍛えることが脳を鍛えることにつながる。 脳に負荷をかけることが、脳へのトレーニングとなる。 負荷には制限時間を設けるものや公言するものなどがある。 セレンディピティの3条件 まず行動すること。 次に気づき。 最後は受容。現実を素直に受け入れる。 著者はこれをリスクを取り、新しい世界にチャレンジすること。と言っている。 常に臆病に徹する。最悪の状況を思い描ける。 自分の好きという基準を深める。 クリエイティブな作業に求められること、それは締め切りを作ること。 つまり制約を作ること。 命令されると脳は自分から動けない。 自律的に行動するように視点を変えてあげることが大切。 やらされてる感があると脳が抑制されてやる気の回路がなかなか働かなくなる。 自分との対話を心がける。つまり、自分を客観視する。 脳にやる気を与えるため、小さくてもいいので成功体験を積み重ねる。 他人ではなく自分で決める。 成功した時はきちんと喜ぶ。 大切なのは他人を意識しないこと。 ルーチン化をすることで脳の無意識は整えられる。 そこでセーブした分、ここぞという場で大きな力が発揮できる。 今一番重要なことは何なのか、それを判断しながら自分の舵取りをしてゆく。 todoリストをイメージでとらえてみる。 瞬間切り替えができるように日々トレーニングする。 脳が活発に動き出すために、意味付けをして仕事に取り組む。つまり、ビジョンを持つ。 迷った時は利他の視点で取り組む。世の中に役立つ自分を想像する。 何かを学ぶためには、自分で体験する以上にいい方法はない。アインシュタイン。 まずは体験してみる。脳の抑制、一般常識や固定概念を外す。 思い立ったが吉日。 人間の脳は行動することでしか鍛えられない。 どんな些細な仕事でもベストを尽くして行動する。
Posted by
仕事の先送り 後回しするクセ→ぐずぐずスパイラル 仕事=やるもの→やらされるもの すぐやる人 集中すべき時・席に着いた途端にスタート・To Doリストのチェックがどんどん・残業ゼロ・充実の内容の課題を提出 日々のちょっとした意識や習慣を変えるだけで新しく神経回路が強化 決め...
仕事の先送り 後回しするクセ→ぐずぐずスパイラル 仕事=やるもの→やらされるもの すぐやる人 集中すべき時・席に着いた途端にスタート・To Doリストのチェックがどんどん・残業ゼロ・充実の内容の課題を提出 日々のちょっとした意識や習慣を変えるだけで新しく神経回路が強化 決められる人、決められない人→すぐやれない=脳の前頭葉が指示通りに機能し抑制が効いている 真面目な日本人 抑制の外し方を知らない 深く考えないことを習慣化する☆思いついたことを実行・やらないときは負けたと思え・お店に一人で入るとき ジョギング 努力する回路→習慣化、継続化には向かない→脳のエネルギーを消費する 何も意識せずに行えるようにする 脳内ダイエット 何かをやらないと決めることで脳の中に空き地☆英語に集中・簿記はやらない・気象予報士の勉強 ワクワクできる空き地→チャレンジ精神、フロンティア精神→自分で自由に決めていい状況でないとやる気は生まれない ①瞬間トップスピードを習慣化 PC起動後→すぐ原稿(意識せずに習慣化) ②雑談で創造力☆喫茶店でコーヒー・人間観察で代用 ③ベストエフォート方式 毎日やる→1日途切れても気にせずまたやる やれる範囲のことをやる やる気が起きない→体力不足☆体幹トレーニング 脳の成長には無茶ぶり→「アベノミクスを英語で1分で言ってみな!」・1分間スピーチの練習 ウソのプレッシャー 大統領になったつもりで報道陣に語りかけるイメトレ☆不祥事、死亡事故を起こしたと想定した準備 →負荷が大きいほど克服した喜びが大きい 正社員→リスクを取れる層 セレンディピティserendipity セレンディップの3人の王子(The Three Princes of Serendip)という童話にちなんだもの(偶然の巡り合いを引き付ける力)→行動、気づき、受容(現実を素直に受け入れる)→柔らかい自然体の心でひたすら継続していく→新しい自分 最悪の状況を思い描ける人→「最悪、こうすればいいや」 複数の選択肢→どんな状況でも取り乱さない 生物の脳→不安定な環境では何もしない本能あり・体力消耗防ぐ 脳がリスクを楽しめるか不安に思うかはドーパミンのレセプターDA-2の影響(遺伝的要素もあり) 家康・三方ヶ原の戦い(1573年vs信玄に敗戦)・しかみ像→ネガティブ思考の人がよくやる行動 しかみ像を身近に置いて脳のカンフル剤にした(抑制するために使ったのではない) おとなしくてもいざリスクを取って行動ができればよい 自己評価の高い人(羽生・金メダルでも「自分の演技ができなくてくやしい」) ナルシストとは違う ソニー、ホンダ、テレビ局 広告収入、家賃収入あり→問題を解決する習慣を先送り 5年10年後の先読み 新聞、CD→ネット時代への対応は? 大学のシステム 少子化 反転授業(動画を見て質問を受ける授業) 人工知能 物流、医者 クリエイティブな作業→締切りをつくること・成果品が大切 脳にプレッシャー 夏目漱石こころ「先生と遺書」=次に連載する弟子が失踪したため漱石が物語を引き延ばすための策 脳→やらされていると判断→やる気の回路が働かない 脳の前頭葉 意思決定・継続→自分の成長にこれはどんな意味があるのかを整理→内面化 課題変換→宿題→将来の夢→自分からやろう! ゲーム化 成長のスピードで満足感 ドーパミン アプリでも応用 走った距離を表示→達成感 やる気を出すには過去の成功体験 脳をフローの状態にする→不安、焦り、緊張などに感情が揺れ動かず、勝手な意味づけ、思い込みに脳がとらわれていない状態 フローが途切れている状態を戻すトレーニング 集中力がない原因分析→フローへ戻す フローに不可欠な緊張との戦い→×背伸びしたコメント〇失敗して経験から学ぶ☆会議でしゃべるときに緊張・クセを分析すること 頑張ることを習慣化→余計な所でエネルギーを使わない 宇宙飛行士→同じことの繰り返し→いざというときに複雑な状況判断可能 出張の際もいかに1秒ごとに有効活用できるか意識 電車内ですること 自分の横にもう一人の自分が立つイメージ 仕事に意味付け 3人のレンガ職人 自分の仕事に誇りを持って成功している人の共通点→他人を喜ばせるのが好き→サプライズ脳 自分に喜びが返ってくる アインシュタイン「何かを学ぶためには、自分で体験する以上にいい方法はない」 すぐやること→勇気が必要 常識、固定観念が抑制→まずは体験
Posted by
結果を出せる人になる すぐやる脳の作り方 茂木健一郎氏 ◆すぐやる脳とグズグズ脳 ・セレンディピティ条件 行動 気づき 受容 このサイクルをまわしていくうち成功要因の人金ものに突き当たるチャンスにあたる ◆リスクとってすぐやる脳 ・常にBプラン用意 複数の状況を想定しながら複...
結果を出せる人になる すぐやる脳の作り方 茂木健一郎氏 ◆すぐやる脳とグズグズ脳 ・セレンディピティ条件 行動 気づき 受容 このサイクルをまわしていくうち成功要因の人金ものに突き当たるチャンスにあたる ◆リスクとってすぐやる脳 ・常にBプラン用意 複数の状況を想定しながら複数の選択を思い描く ・ネガティブな人ほど大きな結果を叩き出す ◆安定しない人が未来の成功を手に入れる ・好きにこだわれば感性は磨かれる 創造性を発揮する分野は機械にはできないこと ・5年10年後の自分がみえているか ◆脳をやる気にさせる自律のメカニズム ・ご褒美が脳のドーパミン誘い出す 自分の価値観で達成感を定義 ・自分と対話する人が最後勝つ ◆すぐやる脳に変われば人生がらりと好転 ・オーバースペックな人材を目指せ 今目の前の業務に何かしらかけあわせる。 イノベーションが起こるかも
Posted by
パラパラと読める一冊の本 結果を出しているビジネスマンは切り替え力が強いとのこと. すぐに行動すること
Posted by
正直…。うん。 考え方のヒントにはなるかもしれませんが人それぞれでしょうしね。 なのでこの本にもありましたが自分を理解すること。 過去の体験からどんなに些細なことでも成功した体験を思い出せば行動に移しやすくなるんじゃないかなと思いました。 1番良いかなと思ったのは脳をフロー状態に...
正直…。うん。 考え方のヒントにはなるかもしれませんが人それぞれでしょうしね。 なのでこの本にもありましたが自分を理解すること。 過去の体験からどんなに些細なことでも成功した体験を思い出せば行動に移しやすくなるんじゃないかなと思いました。 1番良いかなと思ったのは脳をフロー状態にするというところでした。 僕もたまにというかよくありますがカットをしてる時に友達やお客さんと喋っていると遊んでる時の状態というか少なくともあまり仕事してるという感覚でなくなる時があります。 それがどうも脳のフロー状態というらしいのですが多分なんの仕事をするのにもこの状態をすぐに作れればと思いました。 茂木健一郎ってでもなんかあれですよね…。 YouTubeとかで動画とかも結構見たことありますけどちょっとおかしいですよね。w 脳科学者やさんってそんなもんなんですかね。
Posted by
脳科学者の茂木健一郎さんが書いた本。脳の専門家が書くから小難しいのかなと思いきや、自己啓発本のような要素が多めで、脳科学の観点はあまりなかったけど、わかりやすくて元気が出る本だった。 私はめんどくさがりやで物事を後回しにしてしまいがちになる。そして後回し後回しがたまってやる気が失...
脳科学者の茂木健一郎さんが書いた本。脳の専門家が書くから小難しいのかなと思いきや、自己啓発本のような要素が多めで、脳科学の観点はあまりなかったけど、わかりやすくて元気が出る本だった。 私はめんどくさがりやで物事を後回しにしてしまいがちになる。そして後回し後回しがたまってやる気が失せていくタイプだ。少しずつ生活に生かしていきたい。 メモ↓ 人間の脳には、すぐやる脳とぐずぐず脳がしっかり共存していて、すぐやる脳の活性化は、脳の抑制を外せるかどうか。→脳の脱抑制 深く考えない方がうまくいく。 無駄をそぎ落とす。 すぐやる脳をつくる3つの法則。 習慣化する。 雑談の時間をつくる。 ベストエフォート方式→あきらめてやらないよりも、途中からでもやったほうがいい。 脳の成長には負荷が必要。 セレンディピティ=偶然の巡り合いを引き寄せる力。 セレンディピティの3つの条件。 行動、気づき、受容。 最悪の状況を思い描ける人が最強。常にプランBを用意する。 自己評価とナルシズムはちがう。 ナルシズムは、自分の実力を実際以上に高く見積もる、高く見せる。自己評価は、自分のありのままの実力を認め、向上するための努力を積んでこそ身についていくもの。自分へのダメ出し。 5年後、10年後の未来の先読み。 人工知能に負けない力は、コミュニケーション能力。 好きにこだわれば、感性は磨かれる。 寄せ集めが脳を育てる。 命令されると、脳は自分から動けない。自分自身の課題として内面化すること。 脳に遊び心を持たせる。ご褒美をつける。脳のドーパミン。 恥ずかしがらずに成功を喜ぶ。 フローの状態に入る。 他人を意識しないこと。 todoリストをイメージ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
メモ ・ベストエフォート方式(最善努力)でもっと前へ! ・公言することで自己プレッシャーをかけろ ・「行動」「気づき」「受容」を循環させて偶然って言われる機会を引き寄せろ ・常にプランBを用意しとく ・迷ったときは利他の視点で そして最後に私も大好きなアインシュタインの言葉が。 「何かを学ぶためには、自分で体験する以上にいい方法はない」
Posted by
難しい表現や単語はなく、一つの章も短いのでリズムよく集中して最後まで読めました。結果を出せる人になれるかは「?」ですが、すぐやる人になるために「脳の抑制をはずすこと」「小さな成功体験を積み重ねること」など実践できそうなことも多く書かれていますが、「脳内に柔らかいTO DOリストを...
難しい表現や単語はなく、一つの章も短いのでリズムよく集中して最後まで読めました。結果を出せる人になれるかは「?」ですが、すぐやる人になるために「脳の抑制をはずすこと」「小さな成功体験を積み重ねること」など実践できそうなことも多く書かれていますが、「脳内に柔らかいTO DOリストをつくる」など少し難しいかなという内容もありました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
正直期待外れ。脳科学の観点から脳のメカニズム的な話を聞けるのかと期待していたが、どこぞの自己啓発本とほぼ変わらない内容で、特に脳科学者でなくても書ける内容である。 また、内容がとっちらかっていて、結局何を言いたいのかまとまりがない印象を受ける。いいことも書いているので、もう少しテーマを絞った内容で、さらに脳科学の知識をもっとふんだんに盛り込んでほしい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
図書館。2015年5月発行。茂木さんの本、ちょくちょく読んでいるのでその一貫で。 「空き地」の話を読んで、自分の過去を思い返して、仕事や職場に「余裕」が無いことが仕事がうまく回らない原因のひとつだと思っていた時期もあったことを思い出した。また、子育てしていく中でも子どもの頭にこのフロンティア精神やチャレンジ精神が生まれる領域、つまりワクワクできる「空き地」をしっかり作ってあげられるよう、うまくサポートできればと思った。 力の弱い大学の廃止や反転授業の話、娘に直接関わることなので興味あり。もう少し知りたいので調べてみよう。2017/7/27 ◆引用 「栄養のある食事を取り、十分な睡眠を取り、しっかりと体を鍛える。これは、脳の働きをよくするために必要不可欠なことであり、仕事で結果を出していく上でも大事なこと…p37」 →規則正しいは、健康のみならず頭にもいいのね。やっぱり何ごとも生活が基本なんだなぁ。 「(中学生や高校生に英語で一分間スピーチするよう指示し、さらに難しい質問もし、脳に負荷をかけ、「こんなスピーチしたことないんだよね、人生で最初の1分だったんどよね。そしたらうまくいかないのは当たり前だと説明したあとで) 一万時間の法則って知っているかな?1日3時間、それを10年やると、だいたいその道のエキスパートになれると言われているんだ。キミたちの一万時間は、今始まったばかりなんだよ…p40」 →今始まったばかり…娘が大きくなって、何かにチャレンジする中でくじけそうになった時、そんな言葉をかけてあげられたら。 「時間とは圧縮する、つまりやることの密度を濃くするほど、内容の質が高くなると言われます…p45」 →最近読んだ宇都出氏の『速読勉強術』と似たようなことを言ってる! 「チャンスは納得いかない、しんどい「無茶ぶり」としてあなたのもとにやってきます…p53」 ・p65…脳がリスクを楽しめるか、不安に思うかは、神経伝達物質であるドーパミンのレセプター「DA-2」の変異の仕方によって分かれるものと言われます。(中略)リスクをポジティブに考えるのが正しく、ネガティブに考えるのが悪いということではありません。リスクの取り方、つきあい方は、ひとつではありません。自分の個性を十分に生かす方法を選ぶことにより、人生は何倍も有意義なものになっていくはずです。 ・p94…英国のオックスフォード大学で人工知能の研究を行うマイケル・A・オズボーン准教授が、同大学のカール・ベネディクト・フライ研究員とともに著した『雇用の未来 コンピュータ化によって仕事は失われるのか』という論文が今、世界中で話題になっています。 →医者も弁護士も人工知能に取って代わられる、というような言葉をときおり耳にするけれど、元ネタはこの論文だったのか!(?)
Posted by