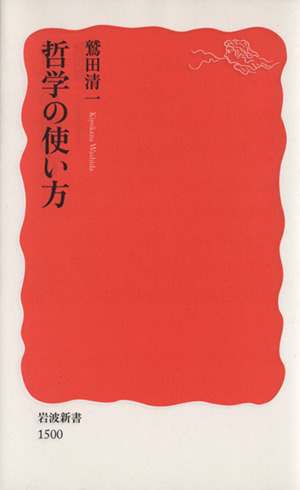哲学の使い方 の商品レビュー
哲学とはなんだろうか。 哲学を使うということはどういうことだろうか。 この本を買ったときに思いました。 読み終えた後もこの疑問に対する答えが得られたとは言えません。 けれども、なんとなく、哲学というのは考えに考えて考え抜くことなんじゃないかと思えました。 当たり前のことを当たり前...
哲学とはなんだろうか。 哲学を使うということはどういうことだろうか。 この本を買ったときに思いました。 読み終えた後もこの疑問に対する答えが得られたとは言えません。 けれども、なんとなく、哲学というのは考えに考えて考え抜くことなんじゃないかと思えました。 当たり前のことを当たり前で済まさないで、もうちょっと先まで考える、そんな思考の行為を習慣にすることが哲学を使うということかな、と感じています。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
後半はよくわからなかった為、第一章のみまとめ 哲学とは「〇〇である。」ではなく、「哲学とは何か。」という問いから始まる。例えるならばスタートラインに立った時、ここは本当にスタートラインだろうかと問うことこそ哲学なのだろう。カントの「哲学を学ぶことはできない、人はただ哲学することを学びうるのみだ。」という言葉はまさに的を得ている。 人が哲学に焦がれるのは直面している困難をうまく解決できないときだ。そしてそういった困難は正解でないことがある。それに対し我々が紡ぐべき思考というのは、わからないけど大事だということをわからないまま正確に対処することだ。ここで重要なのはわからない問題に対して安直な理論で片付けないことだ。たとえわからない問題が出ても問題が立体的に見えるまで耐え忍ぶことが重要。 わからない問題を正確に対処するためにはあらゆる方向から問題を見る必要がある。つまり多くの視点が必要だ。人は都合の良い視点で世界を捉えているため、 その視点のままでは正確に対処できない。 自分の知らない真逆からの視点や思いもつかない視点から見なければならない。そういった自らの視点を自らの関心の「外」の視点とをつなぐことで理解している枠組みを解体し組み変えることができる。
Posted by
とてもおもしろい。 哲学に興味があり、本を読む中でもともとおもしろい哲学者だと思っていた。一つ一つの話は短いが、説明がわかりやすく、それでいておもしろいと思う。 当たり前だと思っていた常識、生活などについて鋭く切り込んでおり、疑問を投げかけたり、矛盾点を洗い出したりしていた。そ...
とてもおもしろい。 哲学に興味があり、本を読む中でもともとおもしろい哲学者だと思っていた。一つ一つの話は短いが、説明がわかりやすく、それでいておもしろいと思う。 当たり前だと思っていた常識、生活などについて鋭く切り込んでおり、疑問を投げかけたり、矛盾点を洗い出したりしていた。そのため、ハッとされられた話がいくつもあった。世界の見方が変わった。 違いの章は仕事について考えされられ、この章の話は、考えさせられた。専門性の罠、悲しい目、水筒、うなぎが良かった。
Posted by
哲学は何か深遠な問題と出会った時に頼りたくなるような、そんな学問だと思っていた。今日まで書かれてきた夥しい哲学書を繙けばそこに正しい答えが書かれているような気がする。しかしそれは否だ。問題解決の手がかりがあるだけだ。哲学するとは部屋に閉じこもって膨大な文献を読み、書かれた言葉を精...
哲学は何か深遠な問題と出会った時に頼りたくなるような、そんな学問だと思っていた。今日まで書かれてきた夥しい哲学書を繙けばそこに正しい答えが書かれているような気がする。しかしそれは否だ。問題解決の手がかりがあるだけだ。哲学するとは部屋に閉じこもって膨大な文献を読み、書かれた言葉を精査し研究するだけにあらず。さまざまな言説や理論が交わされる場所、立ち上がる場所にこそが哲学の居場所だと著者は説く。他者と対等な立場で対話を重ねながら問題の所在を探ること、問いが書き換えられてゆくプロセスそのものをシェアすることが哲学の議論であり、哲学的対話が目指すのは合意ではない。そして今ひとつ大切なことは、わからないもの、正解がないものに、わからないまま、正解がないまま、いかに正確に処するかということだ。解らないでいることの耐性、すぐに結論を出さず、また解りやすい説明や論理、物語にすぐ飛びつこうとしないこと。安易な、短絡的な思考は考えることの放棄だ。社会には不条理が溢れ、そう簡単に答えが出ない難問が山積している。寧ろ答えが容易に出る問題の方が遥かに少ない。そこで求められるのは哲学することだ。多角的に問題を捉えること、他者の言葉にじっくり耳を傾けること。自分とは異なる価値観や異文化、興味のない事柄にも普段から関心を持つこと。私が思うのはSNSがこれだけ発達し、色々な人と、世界と繋がれるようになったけれど、結局繋がっているのは自分の興味関心があるもの、自分と共通点があるものが大半で、自分の関心が低いものは弾かれているのではないか、ということだ。勿論、人との繋がりはネット上のSNSだけではないれけど。哲学するのいうこと、思考し続けるには一箇所に留まっていてはいけないのだなと思った。本書で紹介されている哲学カフェがとても楽しそう。参加してみたい。
Posted by
via Twitter​ http://ift.tt/​1wH3dFi ​ 理論​がそのままでは...
via Twitter​ http://ift.tt/​1wH3dFi ​ 理論​がそのままでは通​用しない、そのような​場所をひとはしばしば「​現場」と呼んでき​た。▼『​哲学の使い​方』 鷲​田清一(岩波​新書2014)p140​ —​ inamura fu​miya (...
Posted by
「文学部唯野教授」を読んだ直後だったからか洗練されてなさが目立つ本だった。そもそも、使い方というより使われ方や捉えられ方見られ方、一般的な印象というものが冒頭に来る。ここで作者は初学者はえてしてその難しい専門用語や膨大な語群に撥ねつけられる。と何度となく語る。が、その愚を著者自ら...
「文学部唯野教授」を読んだ直後だったからか洗練されてなさが目立つ本だった。そもそも、使い方というより使われ方や捉えられ方見られ方、一般的な印象というものが冒頭に来る。ここで作者は初学者はえてしてその難しい専門用語や膨大な語群に撥ねつけられる。と何度となく語る。が、その愚を著者自らやってしまっている感じ。哲学用語は仕方がないにしても、普段見ない漢字やカタカナ用語が散見された。文脈から言って平明に言い換えても伝わる箇所だと思うが、どういうわけかそういう書き方になっている。何を書いているのかハッキリしない。取捨選択が不徹底で、知ってる言葉を書けばいいってものではない。順序立てもあまりなく、トピックの立て方もタイトルと中身の印象が違うのと同様に適切ではない。が、第三章以降、哲学カフェを話題にしたあたりから話が具体的かつ平明になってくる。哲学を語る場所を持つことについて色々話ししていてそこのところは面白かったように思う。
Posted by
うーん、まあ、「エンゲージド・ブッディズム」みたいなもんかなあと思いながら読んだ。 世代を超えた人たちが、ある問題について真剣に話し合うことは素晴らしいことだと思うけれど、一方で、過去の議論の積み重ねを知らずに、単に自分(たち)の中だけでの思いつきを思考することと勘違いする危険性...
うーん、まあ、「エンゲージド・ブッディズム」みたいなもんかなあと思いながら読んだ。 世代を超えた人たちが、ある問題について真剣に話し合うことは素晴らしいことだと思うけれど、一方で、過去の議論の積み重ねを知らずに、単に自分(たち)の中だけでの思いつきを思考することと勘違いする危険性も感じる。 いや基本的にはいいことだと思うんだよ。
Posted by
著者が「臨床哲学」を提唱していることは以前から聞き及んでいたのですが、本書を読んで、ようやくその概要を知ることができたような気がします。 著者が主催する「哲学カフェ」の具体的なエピソードも紹介されており、〈現場〉から紡ぎ出される知恵に耳を傾けようとする繊細な知性の息吹を、ほんの...
著者が「臨床哲学」を提唱していることは以前から聞き及んでいたのですが、本書を読んで、ようやくその概要を知ることができたような気がします。 著者が主催する「哲学カフェ」の具体的なエピソードも紹介されており、〈現場〉から紡ぎ出される知恵に耳を傾けようとする繊細な知性の息吹を、ほんの少しですが、垣間見たように思いました。
Posted by
あれほどじぶんを震撼させたものが時とともにあまりにも速やかに褪せゆくことに愕然としもする。時間はあらゆるものを洗い流してゆく。 ほんとうに大事なことは、ある事態に直面して、これは絶対手放してはならないものなのか、なくてもよいものなのか、あるいは絶対にあってはいけないものなのか、そ...
あれほどじぶんを震撼させたものが時とともにあまりにも速やかに褪せゆくことに愕然としもする。時間はあらゆるものを洗い流してゆく。 ほんとうに大事なことは、ある事態に直面して、これは絶対手放してはならないものなのか、なくてもよいものなのか、あるいは絶対にあってはいけないものなのか、そういうことをきちっと見極めるような視力である。 長くて苦しい議論、譲れない主張の応酬の果てに、そんな苦しいなかで双方が最後まで議論の土俵から下りなかったことにふと思いがおよぶ瞬間に、はじめて相手に歩み寄り、相手の内なる疼きをほんとうに聴くことができるようになるのだろう。 専門家が「特殊な素人」でしかありえなくなった時代 どの価値を優先するのか ほんとうのプロというのは他のプロとうまく共同作業できる人のことであり、じぶんがやろうとしていることの大事さを、そしておもしろさを、きちんと伝えられる人であり、そのために他のプロの発言にもきちんと耳を傾けることのできる人 これまでじぶんの視野になかった問いをじぶんの中に叩き込んでゆく 理解しあえなくてあたりまえだという前提に立てば、「ともにいられる」場所はもうすこし開かれる。 対話は、他人とおなじ考え、おなじ気持ちになるために試みられるのではない。語りあえば語りあうほど他人とじぶんとの違いがより微細にわかるようになること、それが対話だ。「わかりあえない」「伝わらない」という戸惑いや痛みから出発すること、それは、不可解なものに身を開くことである。対話のなかでみずからの思考をも鍛えてゆく。よくよく考えたうえで口にされる他人の異なる思いや考えにこれまたよく耳を澄ますことで、じぶんの考えを再点検しはじめるからだ。 「どんな専門家がいい専門家だと思いますか?」返ってきた答えは、「いっしょに考えてくれる人」 専門家への信頼の根はいつの時代も、学者がその知性をじぶんの利益のために使っていないというところにある。
Posted by
この本さえ読めば素人でも哲学の使い方、仕方がわかると いうようなハウツー本、マニュアル本ではないので要注意。 この現代という時において哲学とはどのような役割を果たす べきか、どのようにあるべきか、そもそも哲学は意味ある ものとして存在しうるのかどうか。哲学者が哲学者として 哲学...
この本さえ読めば素人でも哲学の使い方、仕方がわかると いうようなハウツー本、マニュアル本ではないので要注意。 この現代という時において哲学とはどのような役割を果たす べきか、どのようにあるべきか、そもそも哲学は意味ある ものとして存在しうるのかどうか。哲学者が哲学者として 哲学と向き合う上で発せざるを得ない「悲痛な叫び」として 私はこの本を受け止めたのだが、さほど間違ってはいないと 思っている。 日本の教育には宗教教育(ある一つの宗教の教義を教え込む のではなく、人間として宗教というものとどう向き合うか を教える教育)が欠けているのが大問題であるのと同様、 哲学教育も欠けているのは大問題である、と思う。
Posted by