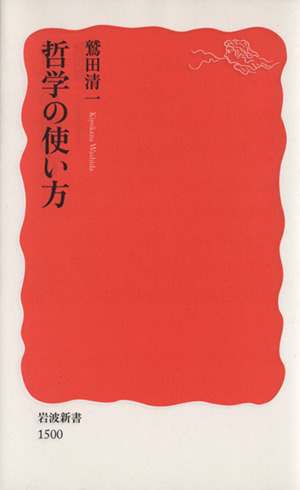哲学の使い方 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
哲学界のたこ八郎、鷲田先生による言葉の拾遺集が朝日新聞の連載で始まったのは、この春の喜びである。まだ一週間ほどだけど、八面六臂の参照先は、先生らしくもあり、意外にも感じられたり、とにかく行く末が楽しみです。 確か東北震災後のことだったと思うが、あるシンポジウムで科学者が集まるなか、鷲田先生ひとり人文系として出席されていて、議論が科学者の専門家としてのありかたというようなあたりに及んださい、先生が発言されたことがいまでも強く印象にのこる。 「何でも答えてくれる人というのはあまり信用がおけないわけです。自分の持ってる知識の範囲内で言ってるだけだろうと思うから。思考の限界まで考えに考えてる人は、あっさりと、わからないことはわからないと言う。こういう人は信用できる」 この言葉はそのまま本書のエッセンスである。哲学者も全く同じである。先生が長く取り組まれている、一般市民による哲学カフェに至る道は、臨床というキーワードの周辺にいるあらゆる人びとに参照してもらいたいものだ。 パスカルの系列は現代にこのように生きている。
Posted by
哲学に対して抱かれている世間の認識が、哲学かを敬遠するものになってしまっていて、しかし人が活動するうえで哲学は欠かすことが出来ないものでもあります。その哲学というものに対してどのように接していけばよいのか。そもそも哲学とは何なのか。そういう疑問に対して、哲学の正体、使い方、付き合...
哲学に対して抱かれている世間の認識が、哲学かを敬遠するものになってしまっていて、しかし人が活動するうえで哲学は欠かすことが出来ないものでもあります。その哲学というものに対してどのように接していけばよいのか。そもそも哲学とは何なのか。そういう疑問に対して、哲学の正体、使い方、付き合い方、という語り口で書かれています。 哲学の難解な書き方や言葉にはそれなりの理由があるし、またそれと対局に位置する対話などの方法も必須だということを、その全てに丁寧に説明をされていて、本書を読むと、自然と哲学するようになるのではないかと思えてしまいました。 哲学を勉強できる(そういう意味で入門書)という内容ではありません。哲学を使えるようにするための本です。そういう意味で非常に重要な本だと思います。
Posted by
「ほしいものが、ほしいわ」。糸井重里が西武百貨店のために制作した広告コピー、哲学者の鷲田清一さんによると、時代の根源語と云う点で哲学と相通じるものがあるのだと云う。時代の大きな変容、しかし感触としてはあっても何なのか判らない、そのもやもやを一瞬にして結晶させるもの、それが哲学...
「ほしいものが、ほしいわ」。糸井重里が西武百貨店のために制作した広告コピー、哲学者の鷲田清一さんによると、時代の根源語と云う点で哲学と相通じるものがあるのだと云う。時代の大きな変容、しかし感触としてはあっても何なのか判らない、そのもやもやを一瞬にして結晶させるもの、それが哲学の言葉であり、広告のコピーと云えるのだ、と。 確かに、この「ほしいものが、ほしいわ」のコピー、これは単純に「欲しいものが欲しい」というただの反復語ではない。今、この刹那に欲しいと思うものが欲しいのであって、翌日にはもう欲しいと思っているとは限らない。例えば、女子学生がルイヴィトンのバッグを欲しいと思うその瞬間が欲しいときであって、では六ヶ月アルバイトをして買うかと云えば、まずNoに違いあるまい。モノが飽和状態にあるこの現代で、目まぐるしく刺激を受けながら人間の欲望自体もその刹那に変化するという事実。これらの根源はいったい何なのか。 鷲田清一「哲学の使い方」。現代の哲学の恐るべき閉鎖性の反省に立ち、哲学はどうあるべきなのかを優しく説く。とかく難解な言葉を駆使してメタフィジカルの壁の中の世界だけに停滞する今の哲学の世界だが、実際にはこの世の本当の真実とは何なのか、世の中の現場に降りて時代の中で哲学するとはどういうことなのか。提唱されている「哲学カフェ」とは・・・!? 哲学を哲学する学問に閉じ込めず、世間のフィールドで生じている出来事を一歩振り返って本当の意味を問う、曖昧に流されがちな意味の根源の真実を問う。そうすることで人間として本当のあるべき姿が見えてくるのではないか、との強い思い。日本の哲学者にもこんな人がいるのかというなかなかに興味深い本。勿論、難しい言葉も多く、やや四苦八苦しながらではあったが、哲学の何たるかを示す覚醒の本と云えるのではなかろうか。
Posted by
読むのに凄く時間がかかりました。内容を飲み込めた自信は全くないですが、エッセンスはなんとなくわかったかなぁと…。 忙しい暮らしをしていると早急に結論を求めがちというか、結論がなきゃダメという雰囲気に流されてしまいがちですが、問いを考えて考え抜くことで問題を解体するということも大...
読むのに凄く時間がかかりました。内容を飲み込めた自信は全くないですが、エッセンスはなんとなくわかったかなぁと…。 忙しい暮らしをしていると早急に結論を求めがちというか、結論がなきゃダメという雰囲気に流されてしまいがちですが、問いを考えて考え抜くことで問題を解体するということも大切だと再認識させられました。本当の意味で「聴く」というのとも、やっぱり大事。 哲学は学者や大学のものではなくて、みんなのものです。
Posted by
響く言葉がたくさんあり、かなりメモを取ったのだが、即実用的かは分からない。でも考えるためのヒント、鷲田さんが本書で哲学することについて語る時に言ってた“補助線”のようなものを、与えてくれる本だった。よく引用されるアドルノやメルロポンティの原書を読みたくなる。よくわからん部分もあっ...
響く言葉がたくさんあり、かなりメモを取ったのだが、即実用的かは分からない。でも考えるためのヒント、鷲田さんが本書で哲学することについて語る時に言ってた“補助線”のようなものを、与えてくれる本だった。よく引用されるアドルノやメルロポンティの原書を読みたくなる。よくわからん部分もあったので、図書館で借りたけど、買っておいて時々読み返すのもいいと思った。後半になればなるほど、それまで読み進めてきた事柄が繋がっていく感覚を得られておもしろい。 鷲田さんの言葉じゃないけど引用されてて気に入った部分。元気が出た。 C・カストリアディス「思考することは、洞窟から出ることでも、影の不確かさをもの自体の際立った輪郭で、また炎のゆらめく明りを本物の太陽の光で置き換えることでもない。それは、「空を向いて、花のなかに横たわって」(リルケ)いられる時に、迷宮に入ること、もっと正確には、ある迷宮を存在させ、かつ現出させることである。また、我々がたゆまず奥へ進むからこそ存在する回廊をさまようことであり、我々が入るとまた入口が閉まる袋小路の奥でぐるぐる回ることであるーーこの堂々めぐりが、説明不能なままに、仕切り壁に通り抜けられる亀裂を生じさせるまで。」 「哲学カフェ」には非常に興味が湧いた。生き方に迷っているとか、進路に迷っているとか、そういう大きなことがらに直面してうろたえているときだけではなく、ちょっとした人間関係、仕事のミスで打ちひしがれているときでも、そっと手にとって心の穏やかさを取り戻させてくれそうな本でした。
Posted by
非常に難解。特に中盤あたりはとりわけ難解で 理解するのが一苦労でした。まだ全部がわかったわけ ではないと思いますが。また哲学の本質的な書物を 読みたいと思います。 ”答えがすぐにでない、あるいは答えが複数ありうる、 いや答えがあるかどうかもよくわからない、 そんな問題群が私たちの...
非常に難解。特に中盤あたりはとりわけ難解で 理解するのが一苦労でした。まだ全部がわかったわけ ではないと思いますが。また哲学の本質的な書物を 読みたいと思います。 ”答えがすぐにでない、あるいは答えが複数ありうる、 いや答えがあるかどうかもよくわからない、 そんな問題群が私たちの人生や社会生活を 取り巻いている。そんなとき大切なのことは、答えが まだ出ていないという無呼吸の状態にできるだけ 長く持ち耐えられるような知的耐久性を身につけること” このことは非常にいい文章だと思います。が。。 本の中で哲学的殺し文句として紹介されている文書 『自己とは何であるか?自己とは自己自身に関係する ところの関係である、すなわち関係ということには関係 が自己自身に関係するものなることが 含まれている。』(キュルケゴール『死に至る病』) 最初に読んだ時はさっぱり何のことやらでしたが。 最後にもう一度読むと少し(少しだけ)わかる気が きがしました。
Posted by
自分の中に準備がないと、読んでも読めない本というのはあるのだ。 この本は今の私にはおおいに「刺さる」内容で、反芻しなくてはと思わされるものだった。 にもかかわらず、そういう言い方になるのは、私にはとても滑らかに、そうだそうだと読めてしまうこの文章が、読めない人にはまるで具体的な...
自分の中に準備がないと、読んでも読めない本というのはあるのだ。 この本は今の私にはおおいに「刺さる」内容で、反芻しなくてはと思わされるものだった。 にもかかわらず、そういう言い方になるのは、私にはとても滑らかに、そうだそうだと読めてしまうこの文章が、読めない人にはまるで具体的なイメージがわかないであろうこともまた鮮明に想像できてしまうからなのだ。 私は私の分野において、その知識の「使い方」を考えなくてはならないのだろう。
Posted by
鷲田さん、書下ろしなんて久しぶりじゃないのか。 大好きな著者なので、読んでみた。でも、ちょっと読んでみてこれはむずかしそうだと思ったので、それから少し間を空けての再チャレンジ。 結果、わかったりわからなかったりの部分があって、理解できたのはたぶん全体の二割くらい。 でも、それでも...
鷲田さん、書下ろしなんて久しぶりじゃないのか。 大好きな著者なので、読んでみた。でも、ちょっと読んでみてこれはむずかしそうだと思ったので、それから少し間を空けての再チャレンジ。 結果、わかったりわからなかったりの部分があって、理解できたのはたぶん全体の二割くらい。 でも、それでも、このひとにくらいついていけば何かが見えてくるんじゃないか、と、そんなふうに思える数少ないひとです。 いつかまた読みます。すばらしい文章を、ありがとうございます。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
日本人の書く哲学入門書というのは、とかく、西洋の哲学のおおざっぱな解説に終わりがち。 本書は哲学は学問のみに終わらず、人間や世界のあらゆる問いを立てるという活動すべてが哲学になる、その対象領域は科学,倫理、芸術、政治、経済さまざまに及ぶ。哲学が近寄りがたいのは、ときに一般人をけむに巻く難解な言術のせいであるが、社会生活を営むうえで欠かせないものである。 臨床哲学者というだけであって、社会のさまざまな身近な事象やときには村上龍のようなエンタメ文学からも素材をとり、哲学への入口へと誘う。 すべてをまったく理解するのは難しいが、この著者には読者を難解な用語で遠ざけるよな俯瞰的な思考が感じられず、読みあたりがよい。こんな哲学書に出会いたかった。
Posted by
臨床哲学と名付けられた哲学を知る必要はある。 哲学とはモノローグではなく、ダイアローグなんですね。 哲学をわかりやすく解説してくれる鷲田清一。それほどに哲学を愛されている雰囲気が伝わってきます。
Posted by