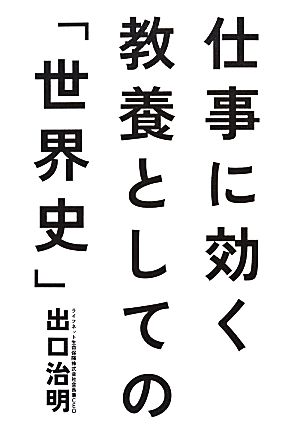仕事に効く 教養としての「世界史」 の商品レビュー
どのように仕事に効くのか興味があったので読んでみた。内容としては、多くの歴史書を読んだ著者が、歴史書には書かれていないが事象から考えると、このような事実が隠されていたのではないかという考察が現代にも通じるものがあると教えてくれている。歴史というと、1国だけの歴史を追いがちだが、複...
どのように仕事に効くのか興味があったので読んでみた。内容としては、多くの歴史書を読んだ著者が、歴史書には書かれていないが事象から考えると、このような事実が隠されていたのではないかという考察が現代にも通じるものがあると教えてくれている。歴史というと、1国だけの歴史を追いがちだが、複数の国の歴史を重ねてみると新しい発見がある。モノの見方の勉強になったが本自体は歴史に詳しくないと読みづらいかと。。。
Posted by
出口さんの見方で世界史をきったらこうなったらという感が強いものの、一つ、一つの地域の歴史だけではなく全体のシステムの中で説明しているところが非常に興味深い。 とても、この一冊で教養といえるレベルにはならないが(人名など全然頭に入っていかないが。。。)、世界システムとしての動きはす...
出口さんの見方で世界史をきったらこうなったらという感が強いものの、一つ、一つの地域の歴史だけではなく全体のシステムの中で説明しているところが非常に興味深い。 とても、この一冊で教養といえるレベルにはならないが(人名など全然頭に入っていかないが。。。)、世界システムとしての動きはすこし理解できた。 しかし、東・西ローマのあたりの歴史ははげしいなあ。 そこへ行くと日本は他の民族との交わりが薄い。いま国際化がなかなかできないのもこのあたりが原因かな。 まあ、歴史的にみると日本単独での魅力は世界から見ると本来この程度というものでしょうかな。
Posted by
外交は友人の頭数。アメリカへの外国人留学生(中国人23万人、日本人2万人)。「ウミガメ」帰って来る中国人留学生。 林則徐がウルムチに左遷される時に友人の学者に『海国図誌』を依頼した。明治維新は林則徐のリベンジ。 国も人もピークがあり寿命がある。 1820年のGDP は206...
外交は友人の頭数。アメリカへの外国人留学生(中国人23万人、日本人2万人)。「ウミガメ」帰って来る中国人留学生。 林則徐がウルムチに左遷される時に友人の学者に『海国図誌』を依頼した。明治維新は林則徐のリベンジ。 国も人もピークがあり寿命がある。 1820年のGDP は2060年予測とほぼ同じ。中国とインドが元に戻っただけ。 紀元100年のローマ、500年のコンスタンチノープル、800年のバクダット、長安。歴史的な大都市は経済活動のピークに人口が最大に。 東京、ロンドン、ニューヨークも今がピーク。 最盛期、ピークの長さは国も人間も同じ。だいたい20代から50代までの20〜30年。 戦後の日本はもっと高く評価されても良い。普通に戻っただけ。 負け戦をニヤリと受け止められるような骨太の知性。 多少の成功で舞い上がってしまうような幼さを捨てる。 「自分が生まれる前のことについて無知でいることは、ずっと子どものままでいること」(キケロ)
Posted by
衝動的に本を読み、感想を書かずに放置、結局内容忘れて読み直し、みたいな展開を無限ループでこなす毎日です。 日本を知りたければ、世界の歴史を知るべきだ。 昨今、ビジネスの世界で求められることが多いのは、世界の情勢もさることながら、我々が住んでいる『日本』そのものに関する知識である...
衝動的に本を読み、感想を書かずに放置、結局内容忘れて読み直し、みたいな展開を無限ループでこなす毎日です。 日本を知りたければ、世界の歴史を知るべきだ。 昨今、ビジネスの世界で求められることが多いのは、世界の情勢もさることながら、我々が住んでいる『日本』そのものに関する知識である。 しかしながら、いわゆる日本史に囚われた知識では、「外から見た日本の視点」は手に入らない。 今、教養を身に着けるため真に学ぶべきは、世界史である。 著者は、生命保険会社のCEOを務める傍ら、世界中の1,000を超える都市を訪れた経験を生かし、京都大学で歴史に関する特別講義を受け持っていた方だそうで。 義務教育でありがちな、○○年に△△があった、◇◇が××を行った、という「覚えるための歴史」ではなく、「ストーリーとしての歴史」を意識した構成になっており、非常に読みやすい本になっています。 触れられているのは、中国における王朝の変遷、キリスト教のルーツ、ローマの皇帝と教皇etc...。 今まで名前くらいしか頭に留まらなかった歴史上の人物が、キャラクターを伴い紙面上で踊りだすようなおもしろさです。 特に、長きに亘って日本の文化に影響を与え続けてきた中国の変遷は、中国大陸だけでなく、中央アジアやヨーロッパまで含めた俯瞰的な視点で見つめることによって、新鮮なものになっています。 教養書籍としてだけでなく、読み物として純粋におもしろく読める本でした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
文化文明や歴史、五行、宗教などの成り立ち、現在へのつながりを教えてくれる名著。 <メモ> ・交易は必ず双方を豊かにする。昔から行われてきたキーワードで、人が行き交って、交易が成立して、世界が動いて、歴史のひとこまがつくられていく。 ・長い歴史的経緯の中で、お互いの生態系にいろいろなものを持ち込んで、人間は豊かになってきた。すでに生態系はかなりの程度まで混ざり合っている。いまさらこの段階で一つでも違うものを入れたらいけないと考えるのは何か変。 ・長く続いてきたものはかならずグレーが存在する。ある意味灰色の効用が存在する。英国には成文の憲法が存在しない。長い伝統と知恵があったため。アメリカは伝統も慣習もないところからスタートして国を作らなければならないため、世界中のいたるところから、さまざまな過去を持つ人々が集まってつくった国です。理性と理屈で憲法を作り、契約をして建国した人工国家です。ここでは灰色はなかなか通りません。伝統的な社会では 灰色というのが一つの決着のつけ方。ゼロから作る場合は必ず白黒になる。
Posted by
教科書の事実の羅列だけの無機質な歴史ではなく、 その当時の時代背景や人の心理にまでが考えられた有機質な歴史という印象です。
Posted by
世界の歴史が表面的な事実だけでなく、その背景から理解出来る良い1冊。こういう本が増えると教養もさらに増すと思う。
Posted by
世界史の概観をつかむのに良い本だと思います。作者の方は歴史を趣味で学んでいる方で、学者さんとかではないのですね。だからこそ、ご自身の自由な解釈を本にできるのかなという印象です。いわゆる教科書に書かれている出来事の背景にはこういうことがあったのでは…と、読者に考えさせる内容になって...
世界史の概観をつかむのに良い本だと思います。作者の方は歴史を趣味で学んでいる方で、学者さんとかではないのですね。だからこそ、ご自身の自由な解釈を本にできるのかなという印象です。いわゆる教科書に書かれている出来事の背景にはこういうことがあったのでは…と、読者に考えさせる内容になっています。私は、歴史は全く詳しくないので、だからこそそういう背景も書いてあるとひとつひとつの出来事が印象に残ります。
Posted by
208頁:南極に近いフェゴ島。 Tierra del Fuegoのことであれば「フエゴ島」。 参考文献リストがないのが残念です。
Posted by
人間にも国にも栄枯盛衰があって、それは多分に偶然や外部要因に左右されている。 運や偶然に振り回されて当然で、順風満帆が寧ろまれなのだと割り切って逞しく生きる力を与えられる本です。 上手くいかないことを嘆くよりも建設的ですね。
Posted by