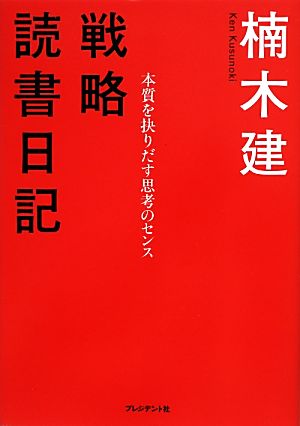戦略読書日記 の商品レビュー
経営ストーリーの本を書いた著者が、経営戦略やストーリーに触発された本を紹介している本です。 経営関連の本ばかりでなく、人伝やダイエット本などもあるのが興味深いです。 難しくて飛ばし読みしてしまったところもありますが、自身の経験や紹介した本の著者との話などもまじえつつ、解説が面白く...
経営ストーリーの本を書いた著者が、経営戦略やストーリーに触発された本を紹介している本です。 経営関連の本ばかりでなく、人伝やダイエット本などもあるのが興味深いです。 難しくて飛ばし読みしてしまったところもありますが、自身の経験や紹介した本の著者との話などもまじえつつ、解説が面白くて読んでみたくなる本がたくさんありました。Kindle化されていない本も多数なのがちょっと残念。 本書はKindle unlimitedで読みましたが、しばらく手元に置いておいて、紹介されていた本を読んだらまた解説を読み直したいです。 『クアトロ・ラガッツィ』『直球勝負の会社』『おそめ』『ホットペッパーミラクルストーリー』『最終戦争論』など 巻末のロングインタビューで、著者が好きな本のジャンルの話をしているのも面白かったです。ここでも本がたくさん紹介されます。自伝や日記が好きで当時の生活ルーティンや世の中の文脈を理解してるというのは確かに面白そうですね。歴史小説も面白いけど、日記も読んでみようかな。
Posted by
自分の読書のスタイルとか感想がいかにチープかと思い知らされる。たぶん読書をしている限り自分でも読んだ本から何かを感じたり考えさせられたり関心が深まっていることは確実にあるとは思うけど、それを言葉にする能力に圧倒的な差があることを突きつけられる。しかし言語化能力の差はつまりは感じる...
自分の読書のスタイルとか感想がいかにチープかと思い知らされる。たぶん読書をしている限り自分でも読んだ本から何かを感じたり考えさせられたり関心が深まっていることは確実にあるとは思うけど、それを言葉にする能力に圧倒的な差があることを突きつけられる。しかし言語化能力の差はつまりは感じる力とか考える力の差なのかとも思う。 でもそんなことは抜きにしても、やっぱり読書はとてつもなく有意義だということが強く共感できて、自分なりに読むことを続けていこうというモチベーションが上がったというか、読書が好きでよかったと思った。 読書の効果を大きくするためにも、読んだ本について書くことをしていかないとなとも思った。
Posted by
具体と抽象。センスとスキル。 自分の興味関心と離れた章は読みにくかったけど、この2つのキーワードは今の自分には引っ掛かった。 そして巻末のインタビューが面白かった!論理に触れるのが好きと仰っていて、まさにそんな本だった。 本を重量級、中量級、軽量級で分けて並行して読むのは私もやる...
具体と抽象。センスとスキル。 自分の興味関心と離れた章は読みにくかったけど、この2つのキーワードは今の自分には引っ掛かった。 そして巻末のインタビューが面白かった!論理に触れるのが好きと仰っていて、まさにそんな本だった。 本を重量級、中量級、軽量級で分けて並行して読むのは私もやるなあ。 読みたい本が増えたので、これから読んでいくのが楽しみ!
Posted by
書評が本になるというのも面白いですね。 しかも著者が好き勝手に書いているという。。。 いくつか良い内容がありますが一つだけ代表して抜粋。 長所と短所は全く同じもの。 長所を伸ばして短所を直すという考え方はそもそもありえないと思っています。 無邪気にそう考えている人は、トレード...
書評が本になるというのも面白いですね。 しかも著者が好き勝手に書いているという。。。 いくつか良い内容がありますが一つだけ代表して抜粋。 長所と短所は全く同じもの。 長所を伸ばして短所を直すという考え方はそもそもありえないと思っています。 無邪気にそう考えている人は、トレードオフというものが理解できていないのです。 人はすべて、三角形や四角形であり、長所を伸ばして短所を直そうとすれば、 三角形や四角形の中に収まるちいさな円になってしまうだけではありませんか。 (「直球勝負の会社」出口治明)
Posted by
抽象化と具体化 バカなる 完全分業と一貫型の違い 歴史に学ぶ 直列型のシナリオ 冷たい経営 豪放磊落 自分の色 学びを一言で綴っていくとそう言うこと。 プロフェッショナルマネージャーとレイクロックの自伝は読んでみなくてはと思う。
Posted by
著者の好みの本とともに、繰り広げられる世界。 この方、かなり本がお好きだとわかります。 読みたくなった本がまた増えた。
Posted by
6章の石原莞爾についての考察が特に良かった。石原はナポレオンとフリードリヒ大王を思考の「極」として捉え自らの立ち位置、ひいては大日本帝国の立ち位置を模索する。ヘーゲルの弁証法やポーターのマトリクス分析等を思わせる石原の発想と行動力に感動。
Posted by
本書は 楠木建の前作「ストーリーとしての競争戦略」の内容を書評で具体化するというコンセプトです。文章はゴツゴツしているけれども、内容はとても良かったです。 本人が面白がっていること。自分で心底面白くなければ、人がついてくるわけがない。ただし、誰もが喜ぶということは、本当に喜ぶ人...
本書は 楠木建の前作「ストーリーとしての競争戦略」の内容を書評で具体化するというコンセプトです。文章はゴツゴツしているけれども、内容はとても良かったです。 本人が面白がっていること。自分で心底面白くなければ、人がついてくるわけがない。ただし、誰もが喜ぶということは、本当に喜ぶ人は誰もいないのと同じこと。優秀な人というのは面白がる才能の持ち主だ。面白がる才能は人間の能力の本質のど真ん中といってもよい。時間をかけてでもそうした才能を開発できるかどうか、ここに本質的な分かれ目がある。自分が好きなこと、面白いと思うことを仕事にする。面白いからのめりこめる。普通の人にはできないような努力を投入できる。好きこそものの上手なれで優れた成果が生まれる。だから世の中と人の役に立つ、やりがいを感じる、ますます仕事が面白くなる。 自分にとって切実なものは何か、理屈抜きの自分の血の騒ぎは何なのか、そういう自問自答が戦略ストーリーの起点にあり、終点になければならない。自分にとって切実なもの、それが戦略の原点であり、頂点である。 自分でよくわかっていることしか書いていないということ。中途半端にしか理解していないことは書いていない。 情報の豊かさは注意の貧困をつくる。情報は、集めるな・整理するな・覚えるな。情報のインプットを増やしていけば、自然とアウトプットが豊かになるということは絶対にない。 物事の順番にこだわる。 勉強の王道読書。読書はコストパフォーマンスが最強。もう現代社会の奇跡といっていい。現代社会の到達した豊かさは読書に象徴されている。 勉強の面白さは、ひとえに知識の質に関係している。上質な知識とは何か。それは論理。論理化されていればことさらに新しい知識を外から取り入れなくても、自分の中にある知識が知識を生むという好循環が起きる。 知的活動とは、ようするに抽象と具体の把握だと僕は考えている。抽象と具体の往復の幅広さと頻度とスピードを指していることが多いと思う。具体をいったん抽象化して、抽象化によって本質をつかみそこから得られた洞察を再び具体的なモノなり活動に反映していく。 長所と短所はまったく同じもの(その人の個性)。長所を伸ばして、短所を直すという考え方は、そもそもありえないと思っています 人間として最上の美徳は素直さであること。実績や経歴や能力よりも素直さ。 深い洞察からくる信念に根差した哲学があれば思考と行動がぶれない。だから意思決定も早くなる。自分の持ち場で、一所懸命に生きることがいちばん自然な形。こちらがブレなければ相手が勝手にブレてくれる。 どんな仕事であれまずセンスありき。自分のセンスをつかみ、芸風を意識的に育て、それにフィットするように仕事をすることは決定的に重要だ。スタイルが決めて。芸風はただ一つ。仕事でプロとして生きていくことは、そもそも自分の芸風と心中するということだ。
Posted by
vol.215 あのベストセラー『ストーリーとしての競争戦略』の原点を発見!http://www.shirayu.com/letter/2013/000435.html
Posted by
ただの書評集なんだよね・・と思って読み始めたのだが、確かに書評集なのだが、何か違う。 一つ一つの本の紹介ではなく、いったん読みこ読み終わったた上で、その真髄を楠木節で語る本であった。 あーつまんないなぁと読むのやめようかと思いながら読了したのは、これが初めてだ。 読み出すとなぜか...
ただの書評集なんだよね・・と思って読み始めたのだが、確かに書評集なのだが、何か違う。 一つ一つの本の紹介ではなく、いったん読みこ読み終わったた上で、その真髄を楠木節で語る本であった。 あーつまんないなぁと読むのやめようかと思いながら読了したのは、これが初めてだ。 読み出すとなぜか心をつかむ楠木節。恐るべし。
Posted by