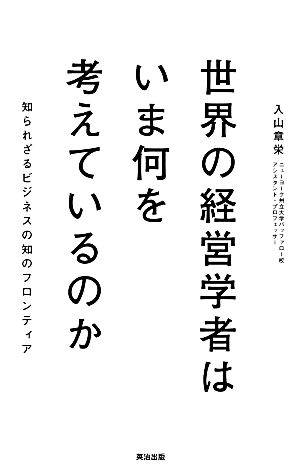世界の経営学者はいま何を考えているのか の商品レビュー
国民性の距離を図ることができる研究があるのを初めて知った。実に興味深かった。 ホフステッド指数 GLOBE指数
Posted by
経営学で世界の教授達はどんな事を教えているのか?をまとめた内容だが、結局MBAを取得した生徒達は、学んだ経営学を会社で実用していない事が多く、統計も言い方次第で結論がすり替わる事があると最後にあかされるし、結局は実践が学ぶ場であり経験する事の大事さを痛感した本。
Posted by
日本ではあまり知られていない、世界の経営学のフロンティアをわかりやすく解説してくれている。経営学に興味が湧き、知的好奇心が刺激されるとともに、普段の仕事などにも活かせそうな知見がいろいろ得られた。 特に、組織の記憶力においてトランザクティブ・メモリー(組織の各メンバーが他メンバー...
日本ではあまり知られていない、世界の経営学のフロンティアをわかりやすく解説してくれている。経営学に興味が湧き、知的好奇心が刺激されるとともに、普段の仕事などにも活かせそうな知見がいろいろ得られた。 特に、組織の記憶力においてトランザクティブ・メモリー(組織の各メンバーが他メンバーの「誰が何を知っているか」を知っておくこと)が重要という話、知の探索と知の深化の「両利きの経営」がイノベーションを促すという話、ソーシャルな関係のストラクチュアル・ホール(構造的な隙間)が重要という話、リアル・オプション(段階的な投資)の考え方を事業計画に応用するという話、リソース・ベースト・ビューは経営理論といえるかどうかの論争の話などが印象に残った。
Posted by
(勉強になった事) ・分析の結果論理的に導かれた事が、内生性を含んでいる可能性があるという事(A→Bではなく、A→B→C) ・ちまたにあふれている経営理論はどの学派にわかれているかでかなり考えの根本がちがう事 (疑問に思った事) この本を読むのは2回目だが、やはりなかなか強烈に内...
(勉強になった事) ・分析の結果論理的に導かれた事が、内生性を含んでいる可能性があるという事(A→Bではなく、A→B→C) ・ちまたにあふれている経営理論はどの学派にわかれているかでかなり考えの根本がちがう事 (疑問に思った事) この本を読むのは2回目だが、やはりなかなか強烈に内容が記憶に残らない。多分自分はやはり「どれだけ、役にたっていると自覚できるか」という事に重きをおくのだろう... (今後) 間をあけてもう一度読んでみる
Posted by
経営学という学問がそもそも何をしているのか、どこに向かっているのかを非常にわかりやすく解説した良書。 著者の説明は、経営学の理論や経営学者の考え方を、実際のビジネスシーンに照らし合わせながら、平易な言葉で、しかも事実と私見を分けて展開されるので、きわめてわかりやすい。こういう説...
経営学という学問がそもそも何をしているのか、どこに向かっているのかを非常にわかりやすく解説した良書。 著者の説明は、経営学の理論や経営学者の考え方を、実際のビジネスシーンに照らし合わせながら、平易な言葉で、しかも事実と私見を分けて展開されるので、きわめてわかりやすい。こういう説明ができるのは、きっと研究内容を広く深く理解されているからなのでしょう。 紹介されている内容も、競争戦略から組織論、海外展開、買収など幅広く網羅されていて、実際のビジネスにも役立つ内容が多いと思います。 可能であれば、数年おきに最新の内容を紹介した続編を出してもらえないかと思うくらいです。おススメ。
Posted by
5分の4くらいまで頑張って読んでたけど、どんどん理解ができなくなって本を閉じました。 自分の今後やっていくことに必要な知識なのかどうかと言のを考えながら読んでたんだけど、そう思えなかった。 もう少し簡単な本から上げていくとします。
Posted by
経営学における世界の先端研究を紹介してくれる本書、著者の謙虚で丁寧な説明もあり先端研究の要旨を分かりやすく解説。話が多岐にわたるため、興味の薄い分野もあるものの、全般として非常に興味深く好奇心を刺激され、また読み物としても面白い。先端研究であるがゆえに結論が出ていないことも多いな...
経営学における世界の先端研究を紹介してくれる本書、著者の謙虚で丁寧な説明もあり先端研究の要旨を分かりやすく解説。話が多岐にわたるため、興味の薄い分野もあるものの、全般として非常に興味深く好奇心を刺激され、また読み物としても面白い。先端研究であるがゆえに結論が出ていないことも多いなかでも、著者なりの示唆があり、尻切れ感が少ないのも好印象。イノベーションにおける知の在り方を説く「両利きの経営」からは多くの着想を得られた。
Posted by
ほぼここ10年ぐらいの経営学のサーベイ論文です。全体を俯瞰できて非常に良かったです。重要な参考文献も沢山紹介してあって有用。 最初に紹介される経営学の分類(マクロ・ミクロ、3つのディシプリンとそれぞれの主要論文誌)だけでもかなり参考になりました。 ハイパーコンペティションと競争...
ほぼここ10年ぐらいの経営学のサーベイ論文です。全体を俯瞰できて非常に良かったです。重要な参考文献も沢山紹介してあって有用。 最初に紹介される経営学の分類(マクロ・ミクロ、3つのディシプリンとそれぞれの主要論文誌)だけでもかなり参考になりました。 ハイパーコンペティションと競争戦略、トランザクティブメモリと組織学習、内生性と因果関係の誤謬にモデレーティング効果、知の深化と知の探索にコンピテンシートラップ、ホフステッド指数とGLOBE指数、プランニング派とコンテンツ派とリアルオプションにコーポレートベンチャーキャピタル、リソースベースビューにエビデンスベーストマネジメント。 いっぱい紹介してくれた。更に、平均的な傾向分析(ガウシアン統計分析)から、複雑系・ノンパラメトリックな特異点を分析対象とするトレンドへのシフトという最近の流れで締め。 さて、参考文献読まなきゃな。
Posted by
○制度的な枠にはめずとも社員同士が自然にwho knows whatを意識できているような組織を作っていくことではないでしょうか。(82p) ○知識の幅を広げると同時に特定の知識を深めることを実現した企業がもっとも優れたイノベーション成果を上げている。(142p) ○一つのテ...
○制度的な枠にはめずとも社員同士が自然にwho knows whatを意識できているような組織を作っていくことではないでしょうか。(82p) ○知識の幅を広げると同時に特定の知識を深めることを実現した企業がもっとも優れたイノベーション成果を上げている。(142p) ○一つのテーマについて深く情報を得ようとするならば強い結びつきが効果的であり、逆に多様な情報を効率的に集めたいときは弱い結びつきが効果的である。(169p) ★最先端の経営学をわかりやすく教えてくれる本。まだ評価の確定していない理論も、経営学者の総意ではないと断りながら、どのように実際のビジネスに活かしていけばよいかを教えてくれる。
Posted by
経営学の紹介本 とても面白かった。経営学は何をどんな風に研究してきているかが、多くの論文と研究者の紹介とともに述べられている。個人的に入山教授が好きなので、なお面白く感じられたのかもしれない。 また読みたい。
Posted by